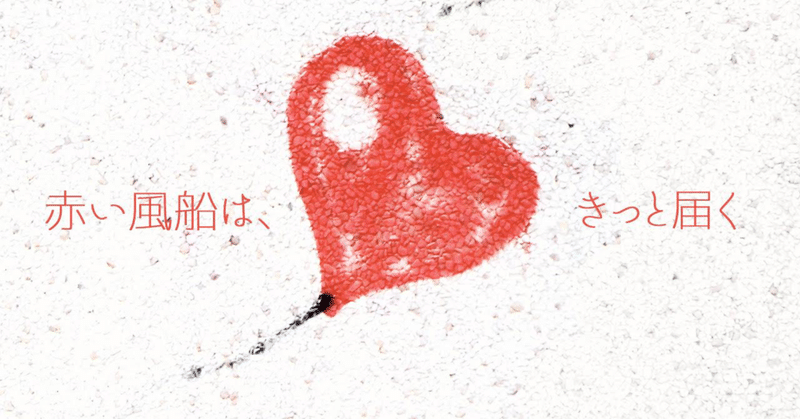
赤い風船は、きっと届く
ある日、僕の家の壁に、落書きが描かれていました。
オフホワイトの凸凹した壁面に、突如現れたその絵は、いわゆるグラフィティというジャンルの、カラースプレーで描く、不良チックな絵。
ステンシルで型を抜いたような輪郭と、リアルだけれど少しコミカルなネズミが、鞄のようなものを隣に置き、傘をさして斜め上を眺めているようでした。
その落書きは、すぐに消すべきだろうか。
その本を読んでいるあいだ、僕はずっと問い続けていました。驚かせてしまっていたらすみません、もちろん、たとえば・・の話です。
バンクシー アート・テロリスト
毛利嘉孝
バンクシーという作家について、以前、こんな投稿をしていました。展覧会をレポートされた投稿を引用し、僕の知っている限りで作家のことを考察したものでした。
受け手にとっては、その作品を見聞きすることで、アーティストを“知る”というひとつの経験をするわけですが、書籍としてまとまっている情報に接する(つまり、読書する)と、さらに見え方が変わってくるような気がします。
半生、作品の特徴、そして作品の作り方などを読むことで、自らの体験が「観た」だけで終わることなく、続いていくように感じるのです。
世界を驚かせた、シュレッダー事件。
密かに来日していた、ネズミ。
どちらも、日本人にとって、バンクシーを知る機会でした。かく言う僕も、知らないままだったこともあり、ちゃんと本を読もう、とページを繰り始めたのでした。
本書のタイトルにも採用されている、彼の紹介は”テロリスト”です。個人的には、とても物騒でふさわしくないと感じているのですが、見た人に与える影響力や、事件の表面ではなく、本質的に何が起こっているのかを伝えるジャーナリズムなどの視点から、彼の活動が強力な主張であるとみなされているのです。
また、彼が(性別は不明ですが)秘匿性を強固に守り続けて活動していることは、アーティスト活動そのものが違法性を内包しているという事実を忠実に物語っているわけです。しかしながら、それが、受け手にとって一種のスリルを与え、彼の存在を誇張する理由になっているのだと感じました。
彼の作品の多くは、街なかの壁に描かれ、それはグラフィティと呼ばれるジャンルのストリート・アートであることを知りました。
いわゆる「落書き」で、額縁に入れて室内に飾るような作品ではなく、本来、街なかにあって、消えてしまう、書き換えられてしまう、そんな脆い芸術作品なのです。
筆者は、「落書き」こそ人類が持っている欲求の発言方法として原始的なものであると主張しました。まさに、グラフィティと呼ばれるまで成長した文化的な結果から見ても、なるほどと思うのです。文字が書けなくても、何かを発信できることは価値があるのです。たとえ、自己満足であったとしても。
何かの発信として政治的な意図が皆無であったとしても、描いていく行為と、権力側の消す行為、そのやりとりが、良くも悪くも脈々と続いているのだと理解ができるのでした。
さて、彼は、バンクシーは、いったい何がしたいのでしょうか。
少なくとも、多くのグラフィティ・ライターが目指しているであろう「自己存在の発信」はもはや不要になりました。
政治的な意見の表明であるとか、権力に対する抵抗の意思表示であることは、すでに多くのニュースが伝えているところです。
彼は、作品を保存してほしいわけでもないし、ましてや売買して欲しいわけではない、と僕は考えます。
彼の作品のほとんどは、難解なモチーフを様々な視点から切り取って再構築するような、いわゆる格調高いアート作品とは異なり、街なかに現れた単なる「落書き」なのです。それは大前提というか、むしろそこが彼の舞台なのです。
世界を変えたいのでしょうか、きっとそうではないはずです。
誰かを救いたいのでしょうか、それも“落書き”の意図とは違うような気がします。
筆者は、多くのグラフィティがある都市、つまりグラフィティが“蔓延”している都市ほど、クリエイティブで民主的で先進的のように見える、と唱えています。
たしかに、僕もグラフィティは秩序なく殺伐として良識からは外れたものとして考えていました。だって、綺麗じゃないのですから。しかしそれは、支配する側の視点が内面化されている結果としての考え方であり、ある意味では不寛容だったのです。
グラフィティを受け入れるような、寛容な都市であることは、若者を受け入れ、不安も含め、まだ見ぬ萌芽を生む場所になり得るのではないかと思います。それが評価されるかは別として、さまざまな意見がとりあえず出せる空気感が、そこにはあるのかも知れません。
僕は、冒頭で紹介した投稿を書いてから、ずっと信じていることがあります。
彼の絵は、消されたり、書き換えられたりすることが予定されている
地元の英雄として、彼の名前を新しい校舎に付けた子らに贈った作品には「気に入らなかったら書き換えて」と添えられていたそうです。
一度は消された場所に、再び姿を表した死神もいました。
落書きをして、見つかって怒られた経験、幼い頃の記憶にある方はどのくらいいるでしょうか。
僕は、バンクシーの本質はそんな「いたずらっ子」なのではないかと考えています。
彼が「落書き」をしているのは、批判や皮肉、非難や否定と言った、オトナの事情ではなくて、感謝や自己顕示、そして呼びかけなのではないでしょうか。
落書きを見つけて、しかめっ面をする“キャンバス”の持ち主を、どこかから眺めては喜んでいるだけなのではないかと思うのです。
通りかかって“なんだこれ”と会話するのを、陰から聞いているかも知れません。
彼の作品の中でも、もっとも有名で、人気のある、ハート形の赤い風船が少女の手から離れて行く、「風船と少女」。(シュレッダー事件の主役も、この絵でした。)
その光景は、一見寂しげですが、赤いハートが感謝の気持ちや、温かな祈りだとしたら、その少女の横顔は悲哀ではなく、相手に届くことを切実に願う、真剣な眼差しなのではないでしょうか。
冒頭の問いに戻りましょう。
その落書きは、すぐに消すべきだろうか。
筆者は、彼の作品(と思われる“落書き”)を保存するかどうかは、権力者が決めるべきではなく、そこに暮らす、その作品に触れる人々によって方向づけられるべきだと書いていました。
ネズミのために、傍らにチーズを描いてみたり、晴れた空を描いてもいいのです。オフホワイトの塗料で、全てを消してもいいのです。
僕なら、彼が描いたネズミのとなりに、もう1匹、ネズミを描いてあげたいなと思います。
一緒に旅をする仲間として。
バンクシーとは何者か、いったいどんなことをしてきたのか、さまざまな作品を知ることができて、美術館で観る絵画とは違う、ストリート・アートの美学にも触れる旅でした。
彼の作品を通して、自分が何を考えるのか、あなたの周囲はどんな景色なのか、少しづつ自分と周囲が見えてくる感覚。それは、いままでにないアートとの出会いかも知れません。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました! サポートは、子どもたちのおやつ代に充てます。 これまでの記録などhttps://note.com/monbon/n/nfb1fb73686fd
