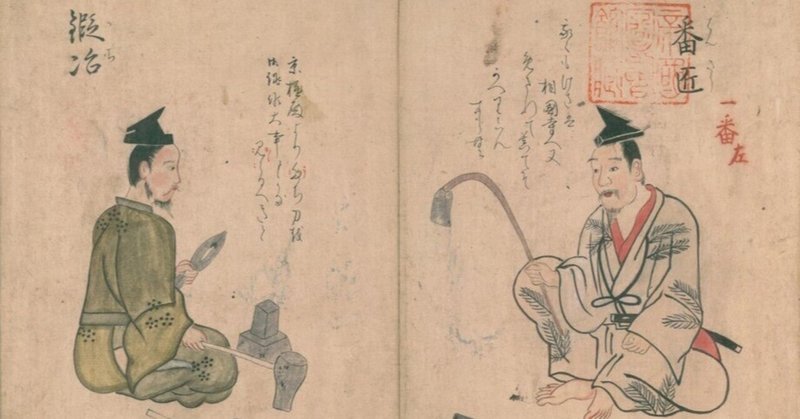
職人尽歌合 1~9番
一番 番匠 対 鍛冶

番匠
我ゝも けさは 相国寺へ 又 めされて
暮てそ かへり候はんすらむ
鍛冶
京極殿よりたち刀を
御誂候 大事にかな 欠かるべきと
※ 「番匠」は、大工のこと。
※ 「相国寺」は、京都にある臨済宗相国寺派の大本山。京都五山のひとつ。
※ 「京極殿」は、藤原師実(藤原頼通の六男、藤原道長の孫)の別名。
二番 壁塗 対 檜皮葺

壁塗
やれやれ うはらよ いへにて
こて●とりて
こかべの大くまいりて候
したちとく候はゝや
檜皮葺
此 むなかはら かおそき
※ 「こて」は、鏝。漆喰などの壁材を塗るときに用いる左官道具。
※ 「こかべの大く」は、小壁の大工。
※ 「したち」は、下地。
※ 「むなかはら」は、棟瓦 。屋根の棟を葺くための瓦のこと。
三番 硎 対 塗士

硎
さきか おもき 今におさえや
ぬしに問申さん
はばゆきはいかに 手をきるそ
塗師
よけに候 きがきの うるし けに候
いますこし 火とるへきか
※ 「塗師」は、漆塗りの職人。
※ 「きがき」は、木掻。漆の木に傷をつけて樹液を採取する漆掻きのこと。
※ 「いますこし火とるへきか(今少し火どるべきか)」は、採取した生漆に熱を加えて水分を飛ばす工程で、もう少し火にあぶるべきか、と言っているのでしょうか。
四番 紺掻 対 機織

紺掻
ただ 一しほ染よと 仰らるゝ
機織
あこ やう くたもて こよ
※ 「紺掻」は、染物屋のこと。
※ 「一しほ」は、一入染のこと。染汁に一度だけ浸したごく薄い藍染め。
※ 「あこ」は、吾子。わが子のこと、または、子供や乳母を親しみを込めて呼ぶ言葉。
※ 「くた」は、機織り道具の管のこと。よこ糸を巻く木製の管。
五番 檜物し 対 車作

檜物し
湯桶にも 是は ことに大なる ゆのために
あつらへ 給ふやらん
車作
ひりやうの 輪とて よくつくれと仰候
※ 「ひりやう」は、飛龍でしょうか。
六番 鍋売 対 酒作

鍋売
播磨鍋 かはしませ 釜もさふらうそ
ほしかる人あらば ●られよ
つるをもかけてさう
酒作
先 さけめせかし はやりて候
うす濁り●候
※ 「播磨鍋」は、播磨国で作られる銅製の鍋のこと。
※ 「うす濁り」は、濁り酒の一種。
七番 あぶら売 対 もち井うり

あぶら売
きのふから いまだ山崎へも かへらぬ
もちゐうり
あたゝかなる 餅まいれ
※ 「山崎」は、京都の大山崎郷のこと。鎌倉時代から戦国時代末期にかけて、荏胡麻油の製油・販売を独占した「大山崎油座」の本拠地でした。
※ 「もちゐ」は、餅。餅と同じ。
八番 筆ゆひ 対 筵うち

筆ゆひ
うのけは 毛のうら面みえぬが
大事にて候
筵うち
てしまむしろ かうしまへ
御さも候そ
※ 「うのけ」は、兎の毛。
※ 「うら面」は、うらおもて。
※ 「てしまむしろ」は、手島筵。摂津国の豊島郡で作られていた茣蓙のこと。
※ 「御さ」は、御座。ここでは、上げ畳(貴人の座所や寝所の畳のうえに敷く畳のこと)の意味でしょうか。
九番 炭やき 対 小原め

炭やき
けさ いて さうまうたか
小原め
あこせは まいり●てけるか
※ 「小原め」は、小原女。京の都で、薪を頭のうえにのせて売り歩く女性の行商人のこと。大原は、山城国の大原。
※ 「あこせ」は、あごぜ。女性を親しんで呼ぶときに用いた古語。ごぜは、御前。
筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖
