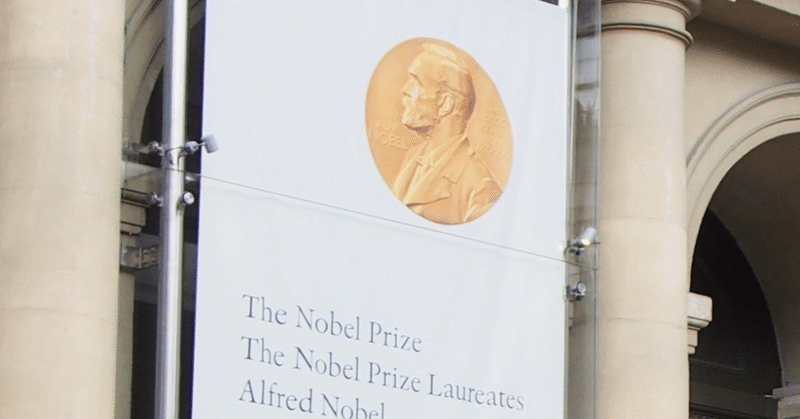
選択と集中より放牧と拡散
◉ノーベル賞級の研究は、少数の研究者に高額な研究費を与える選択と集中よりも、多数に少額ずつ分配する方が良いという研究が、筑波大学から出てきたそうです。狭く深くより、広く浅く。ううむ、今後の科研費の在り方に、議論が湧いてきそうですね。選択の対義語がないので、ここは意味的に、家畜を自由にさせる放牧にしました。放置にしようかと思ったんですが、放置だとそもそも研究費を分配していませんから。牧草地は与えるけれど、特別な飼料は与えていないイメージで。
【ノーベル賞級成果は研究費を「広く浅く」配るほうが増えると判明!】ナゾロジー
日本だけの傾向なのでしょうか?
筑波大学で行われた研究によって、日本の生命科学・医療分野におけるノーベル賞級成果や画期的発見につながる研究成果を増やすには、少数の研究者に高額の研究費を集中するよりも、500万円以下の少額の研究費を多数の研究者に「広く浅く」分配したほうが、投資効果が高いことが示されました。
より高額の研究費になると、1つの成果あたりにかかる費用が逆に増加し、金銭効率が下がっていたのです。
多額の研究費を要する「大きな研究」と少額の研究費でも行える「小さな研究」のどちらに重点を置くべきかについては長年にわたる議論ですが、今回の研究は1つの答えを提示するものと言えるでしょう。
研究内容の詳細は2023年8月17日に『PLOS ONE』にて公開されました。
ヘッダーはnoteのフォトギャラリーより、ノーベル博物館の写真だそうです。
◉…▲▼▲▽△▽▲▼▲▽△▽▲▼▲…◉
■誰が選択と集中を決める?■
例えば、カミオカンデのような、大掛かりな設備が必要な研究は、極端な話、紙と鉛筆だけでもできる理論物理学とは、意味が違いますよね。このカミオカンデに関しては、京都大学にノーベル賞を数多く取られ続けた東京大学閥が、官民一体となって予算をつけて、東大初のノーベル賞を獲りに行った……なんて、酷いことを言う人もいます。そんなわけあるわけないぢゃないですかー。
最初の段階では広く薄く、いろんな可能性にベッドし、その中から可能性がありそうなものが台頭してきたら、選択と集中もありでしょうけれど。最初から皆がこれは行けると褒めそやし、選択と集中を押したがるような研究というのは、ノーベル賞のような世紀の大発見には、向かないのでしょうね。
島津斉彬公の遺訓に、誰もが褒めるような人間は八方美人で、重要な決断ができないので要職に就けてはいけない──というものがありますが。研究もそうでしょう。そういえば 一時期話題になった科研費も、分度って来るのが上手い教授と下手な教授がいるようですが。誰にいくら配分するかを、誰が決めるかという問題はあるでしょうね。とてもまともな研究をしてるとは思えない 文系学者に、無駄にばら撒いていたりする危険性。
■佳作デビューは出世する?■
自分が属する漫画業界では、「佳作デビューは出世する」という言葉があります。実際、高橋留美子先生とか佳作デビューですしね。その時の 漫画賞の審査委員長であった藤子不二雄先生(F先生の方)が、才能を絶賛しながら佳作だったわけですから、評価が分かれたのでしょう。あるいは審査員の中で、入賞や大賞を強行に反対した人がいた可能性。日本人は満場一致が良いと考えがちですが、それは違います。
『後宮小説』や『墨攻』で知られる酒見賢一先生は、プロになって伸びるのは評価が分かれる作家だと、明言されていましたね。例えば、審査員が3人いて、評価が◎◯△✕の4段階評価だとして。3人が◎って作家は、滅多にいませんね。星野之宣先生や諸星大二郎先生のレベルでないと。で、入賞をもらいやすいのが3人とも◯のタイプ。欠点が少なく、完成度が高いですが。悪く言えば、小さくまとまったタイプ。
佳作になるタイプは、◎✕◎の両極端な評価をもらってしまうタイプです。100点か0点かの、中間がない評価と言ってもいいのかもしれません。でも、プロの審査員の0点は、50点や75点より実は価値があるんですよね。その審査員が認めたくない種類の才能があるから、極端な評価をしてしまうわけで。あるいは、間違いなく才能はあるけれど、 致命的な欠点を持っているタイプ。逆に言えばその欠点を克服できれば、一気に伸びます。佳作デビューが出世する理由です。
■優れた研究は理解されない■
たぶん、ノーベル賞を取るような研究というのもまた、極端に評価が分かれるタイプの研究 なのでしょうね。それまでの研究を踏襲しつつも、誰も踏み込んだことのない領域に踏み込むようなものでないと、人類の生活を変えるような画期的な発明や発見には、至らないでしょうから。アインシュタインが相対性理論を発表した時のジョークで、これを理解できるのは世界に3人しかいないと。
その3人の中に、アインシュタイン博士は含まれていない、というオチなのですが。ある高名な物理学者が、相対性理論は世界で3人しかは理解できないと言われていますが……と質問を受け「3人目が思い浮かばない」と切り返したそうですけれど。アインシュタインと自分以外には理解できない、という学者としての自負と茶目っけが混ざった、ブリティッシュ・ジョークですね。
現実問題として、アインシュタイン博士は相対性理論で、ノーベル賞を受賞されていないんですよね。発表当時は、当時の物理学の常識をひっくり返す内容でしたし、どんな形で応用できるか分かりませんでしたから。後に相対性理論は、原子爆弾やGPSやカーナビなど、応用されていくのですが。そんなものなのでしょうね。ただ その場合、どれぐらい広く薄くするか、という問題がまた出てきますが。広すぎても薄すぎても、ダメでしょうからね。
どっとはらい( ´ ▽ ` )ノ
売文業者に投げ銭をしてみたい方は、ぜひどうぞ( ´ ▽ ` )ノ
