
東大生の米談義 番外編 -最近のお米動向- #2
Podcast「東大生の米談義」の番外編となるお米News #2です。
現在クラウドファンディングに挑戦中です!ご興味・関心等ございましたらぜひお願いします!(Instagramも更新中!)
ローソンで被災地支援 「石川県のブランド米おにぎり」
2024年5月7日から大手コンビニチェーンのローソンから「買って食べて、被災地支援」をキャッチコピーに、石川県のブランド米「ひゃくまん穀」のおにぎりが発売される。
来月3日まで販売されるおにぎりは2種類。
一つは、お米本来の味を楽しめる「塩にぎり」。
そして富来漁港で獲れるサワラを使った「鰆(さわら)の柚庵焼(ゆうあんやき)ほぐし」である。
2017年にデビューした新しいお米で、“加賀百万石”で知られる石川県のお米であることが伝わるように「ひゃくまん穀」と命名され、9年の開発期間を経て誕生した。
これまでは震災のあった能登半島や、広大なブナの原生林が残る白山連峰で生産されてきた。
全国のローソンで購入可能で、日常生活の中で被災地支援に少しでも貢献できる機会を実現した大変素晴らしい企業活動である。
お米の紙”kome-kami”
様々な分野でSDGsが注目され、「印刷」や「紙」においても環境に配慮した素材が取り入れられつつある。
例えば、インキ。
大豆油やヤシ油などで作られた植物性インキもサステナブルな素材として挙げられる中で、最近では米ぬかを使ったライスインキという印刷用のインキも開発されていると聞く。
原料の植物が成長する過程でCO2を吸収するため、廃棄の際に燃焼しても「カーボンニュートラル」の考え方により地球温暖化の原因となるCO2量を増やさないことが特長だ。
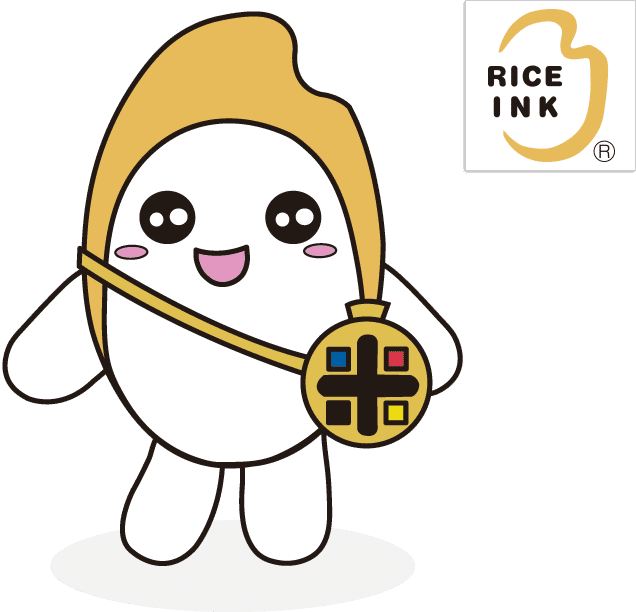
また、サステナブルな紙素材のジャンルもある。
”再生紙”という言葉をさほど珍しく感じないほど、牛乳パックや新聞紙、ダンボールなどの古紙を再利用して作られる紙素材は浸透してきている。
一方で、”混抄紙(こんしょうし)”と呼ばれる、紙の原料となる木材パルプと異素材を混ぜ合わせ、木材パルプの消費を削減して作られる紙素材は未だ一般人には縁遠い言葉だ。
2022年3月、経済産業省「『トランジション・ファイナンス』に関する紙・パルプ分野における技術ロードマップ」によれば2019年度における日本のCO2排出量のうち、木材パルプが占める割合は35%。
こうした状況を改善するために各メーカーで研究されているのが混抄紙、中でも脱炭素系紙素材としての植物由来の機能紙(ボタニカルペーパー)である。
日本においても、お米を使った日本の伝統的な糊や紙への利用に着目した研究により「kome-kami」という紙が開発されるなど、植物由来の機能紙の開発事例が増えてきている。

「kome-kami」は、適切に管理された森から得られ、結果的に地球環境保護の貢献につながる木材の使用を保証する「FSC認証」を得た木材パルプと、食用にはならなかった米を化学薬品の代替原料として活用している。
親と兄の影響で歴史が好きな自分としては、「kome-kami」の2種類それぞれの開発ストーリーが魅力的に思えた。
ナチュラル色は、日本古来の”お米を接着材として使う文化”から着想を得て、化学薬品に頼ることなくお米の力で紙を繋ぎ合わせる「コメバインド」という技術を使用。
浮世絵ホワイトは、江戸時代の「浮世絵の発色を良くするために紙にお米を塗った文化」を現代風にアレンジした紙。表面をお米がコーティングし、紙の繊維の間の隙間を埋め表面を滑らかにすることで、美しい色彩表現を可能にしているという。
この伝統を現代の印刷や加工に活かせるように研究を重ね、お米を使った塗工液「コメグロス」を表面に施した紙素材だ。
kome-kamiは明治23年創業の老舗紙屋である株式会社ペーパルのSDGs推進プロジェクト。
日本発の温故知新な素材として、サステナブル時代の「ジャポニズム」を起こし、未来のデザインに新たな表現力と可能性を広げたいという願いが込められている。
ペーパルはCO2排出量削減を目的とした森林保全活動に取り組む地域の活動をサポートし、その地域の資源を活用することで得られた価値をクレジットとして保有している。「ZERO CO2 PAPER」の費用にはクレジットが含まれており、購入によってCO2削減に対する貢献が可能となる。
地球温暖化が加速する中で「紙」の業界でもサステナブルな製法が注目される。
意識的にサステナブルな紙素材を選ぶことで、CO2削減やフードロスなどに貢献したいものだ。
マレーシアで日本食輸出支援
マレーシアは元々ASEANの中でも比較的高い購買力や良好なビジネス環境だそう。
そんなマレーシアへの日本産農林水産物・食品の輸出額実績が過去10年で約3倍に。日本食レストラン数も大きく増加する等、日本産食品への人気が高まっている今を好機と見たのだろう。
マレーシア向けの輸出の一層の促進を図るためには、「マレー系マーケットを視野に入れたハラル対応」「未開拓の現地商流へのアプローチの強化」が必要ということで、5月2日、マレーシアに輸出支援プラットフォームが設置された。
ジェトロ海外事務所と在外公館等が主な構成員となり、日本産農林水産物・食品の輸出事業者や現地に進出している国内の食品関連事業者等を、現地発の視点で継続的に支援する枠組となる想定だ。
具体的な活動方針としては(1)ハラル市場への戦略的売り込みのための調査、(2)現地バイヤーの日本への招へい、(3)地方都市(ジョホールバル、ペナン等)の販路開拓に向けた現地事業者の発掘を挙げている。
コロナ後フードデリバリー定着化する一方で、食品小売市場全体におけるEC売上割合は1%未満と、オンラインPRx実店舗のベストミックスでの市場拡大が期待されるそう(JETROクララルンプール事務所)。引き続きオンライン活用状況には注目しておこう。
立ち上げ式には高橋農林水産省大臣政務官、高橋駐マレーシア日本大使、森下ジェトロ農林水産食品部長、高野ジェトロ・クアラルンプール事務所長、現地の日本食品関係事業者、アーサー・ジョセフ・クルップ農業・食料安全保障副大臣、マレーシア政府関係者等ら合計約120名が出席した。
現在β版を運用するRICE DAOにはフィリピンやシンガポールのユーザーもおり、東南アジアの日本食の波にも乗り遅れないようにしたい。
「おかゆメーカー」で健康的な朝食を
おかゆは病床で食すイメージが強いが、「おかゆメーカー」のメニューの多さとその機能に日常生活に割って入る可能性を見た。
おかゆ作りは、ずっと見ていないと吹きこぼれてしまったり、理想のとろみが出なかったりと意外と難しい。
そこで小泉成器が発売したのが「おかゆメーカー」(8778円)だ。
自宅で理想の柔らかさのおかゆが作れる調理家電で、お米からでもご飯からでもOKな豊富な調理モード。(おかゆにとろみを出したい時は“やわらかモード”/具材をプラスしたい時は“再調理モード”などなど。)
調理法は“湯煎炊き”で焦げ付きや吹きこぼれがしにくく、ほったらかしでもおいしいおかゆを調理する。
抹茶粥、かぼちゃ粥、トムヤムクン粥、海鮮粥、玄米粥など広範なメニューに対応し、お粥研究家・鈴木かゆさんの監修「世界のおかゆを作れるレシピブック」まで付いてくるそう。
サイズはW185×D195×H190mmとコンパクト設計かつマグネットプラグで収納にも配慮。水洗いも可能で機能性は抜群。
予約や保温機能も付いているので、風邪など体調不良の時以外にも、前もってセットして朝食に軽く食べるのも良いなと思った就寝前であった。
ここまで読んでいただきありがとうございます!
次回もお楽しみに!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

