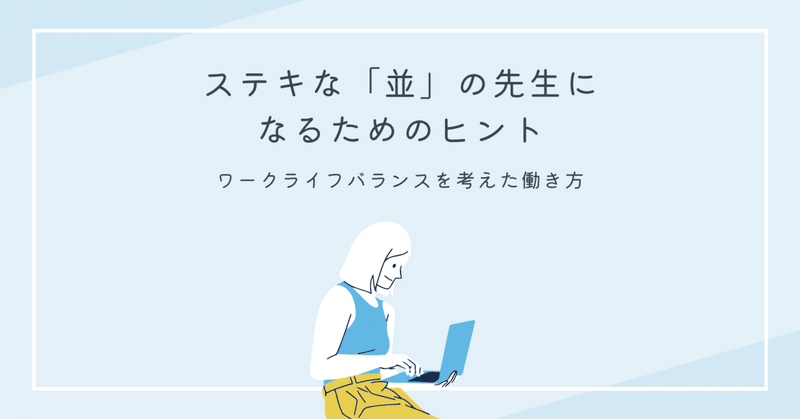
上手な「並」の先生は学習指導要領を度々確認する
皆さんは 学習指導要領 ってよく読まれますか?
私個人で言うとあんまり読んで来なかったなあという風に思うのですが
近年は上手な並の先生に教えてもらって読むようになりました。
もっと具体的に言うと それぞれの教科の目標を確認するようなことを
するようになりました。
というのが 教材を教える時に、最後は何をゴールにするかというのが
あると思うんですが、これが人によってバラバラなんですね。
そして 学習の主体である子どもたちが、比較的能力にも
ばらつきがあるので 全員をゴールさせるのはどこなのか
そしてそれを行うための指導は何なのかというのを考えないと
最近はやっていけないなあ という風に思うようになりました。
今日はそんな話をしたいと思います。
教科書の最後の方から確認する
最近 小学校の国語の教科書は各単元の学習の最後に
何を勉強してどんな力をつけるのかというところが
明確に書かれています。
最初はそこをやればいいと私も思っていたのですが、それでは不十分で
もう少し深めると何のためにこれを行って
どんな風になればいいのかというのがわかると ただやっただけじゃなくって子供たちに考えや 力をつけることができるのではないかと
思うようになりました。
そこで必要になってくるのが 学習指導要領です。
学習指導要領の教科の目標は、学年ごとにだいたいどの辺までやるのか
というのがよくわかります。
私の失敗談ですが 1年生の学習指導の目標には
「お話のだいたいがわかる」と 書いてあったのを見逃しており
かつて「どうして登場人物は そのように考えたのだろう」というような
心情に迫る部分を聞いてました。
当然 何人かは答えられたのですがほとんどの子たちは 答えることが
できず 子供たちの発達段階に合わせた指導になっていないので
大変な失敗をしたことがありました。
そうならないように学習指導要領の目標の部分と
教科書の最後のところを照らし合わせるのは大事だと思います。
次の学年にどのようにつなげるのかを考える
学習指導要領には低学年 中学年 高学年でそれぞれ
似た目標ですが求めるレベルが違うことが分かります。
これ 逆に言うと例えば 2年生から3年生にあげる時に
ある程度3年生になってから学ぶことを意識して
2年生の後半を過ごすと3年への接続がうまくいくということです。
過去に2年生のことで手一杯だった時期もあったのですが
近年は少し余裕が出たのと、指導が若干上手になったので
時間的に余裕を生み出すことができて、
3年への接続ということで 予習的な取り組みをしたこともあります。
そうすると子どもたちが面白がって興味を持つこともありますし
成功する体験をしたり、さらに新しいことにチャレンジする面白さを
経験したりすることが多くあり、子どもたちの意欲が
とても上がりました。
ここで ポイントになるのは何でも OK というわけではなくて
次の学年への接続 というのがミソ です。
学習指導要領はさすがに たくさんの事例やたくさんの学者さんが
考えておられるだけあって 非常に いいところをついてるように思います。
無理なく子供たちの成長に合わせて指導するには
大変貴重な資料になると思うので これは外さないように
読んだ方が良さそうです。
終わりに変えて
学習指導要領を読み込んで覚えているという人は
大変素晴らしいと思います。
ただ普通の先生からするとなかなか全部を覚えるほど
読み込むというのは難しいと思うので
自分が担当している教科の目標や 何をするのかというところを
確認しておくとそこまで大きくかけ離れたことをしなくて
済むのだと思います。
必ず 職員室のどっかにあって誰でも見れるようになっていますので
ちょこちょこ 見て授業されるのをおすすめします。
今日も読みいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
