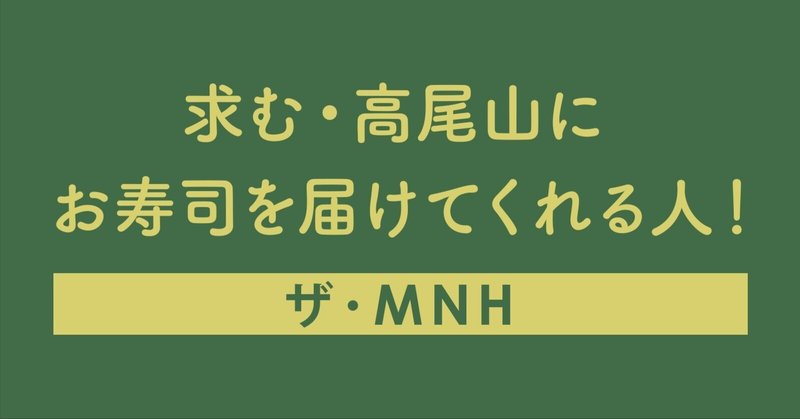
求む・高尾山にお寿司を届けてくれる人!
MNHの小澤です。
こうして「なっぱ寿司」を自ら高尾山へ届けて、好調な販売を続けること、半年。

2014年のゴールデンウイークを前に、自ら配達することに限界を感じ、求人を出すことにした。「朝、国立の工場までお寿司を取りに行って、高尾山口まで届けて欲しい」というシンプルな依頼だった。
すると、70代の男性2人が応募してきてくれ、しばらく配達をお願いすることになった。定年後に時間があった彼らにとって、ちょうど良い仕事となったようだ。
しかし、メーカー側が応援販売(店頭で自ら売ること)を辞めると、たいがい売り上げは下がるものだ。例えば「山の上の食堂は混むから弁当を買っていったほうがいいですよ」といった積極的な声かけもなくなるからだ。そして次第に発注量が減っていった。
もともとお弁当は賞味期限が最大のネックであり、確実な売上が見込めないとできない事業だったゆえに、年間300万人が訪れる高尾山以外での展開は考えられなかった。
そして最終的には、コロナを機に完全に販売を中止することになった
しかし、この「なっぱ寿司」を通じていろいろと気づきがあった。
まずぼくは、放っておいても観光客がなだれ込む山だからこそ、もっと観光客をもてなすべきだ、と強く感じていた。
関東ではほとんど目にしない高菜に包まれたお寿司は、それまでコンビニと同じような品揃えだった高尾山口駅の売店のなかで、一躍注目を集めた。風情あるお弁当を観光客も潜在的に求めていたようで、みんな目を輝かせて買っていった。
何なら今まで「山に来てまで、なんでコンビニのおにぎりなんかを食べなきゃいけないの?」と思っていたのではなかろうか。
そして薬王院の人にも「軽食などを提供してみてはいかがですか」とアドバイスをしてみた。するとじきに敷地内でいなり寿司を売り始めた。言わずもがなだが、売れていたようだ。改めて自分の直感は当たっていたと感じたのだ。
さらに、今回はたまたまぼくが庄内で「めはり寿司」に出会えたからこそなのだが、西の文化を東に持ってくるのは、関東人に受けがいい気もした。
また、地域内物流に対しても、より関心が高まった。
現在、物流業界ではハブアンドスポーク方式(*)が主流だが、ベストな手段ではない気もしていた。例えば、MNHから発送したものがいったん東京都心の物流センターに集約され、高尾山に輸送されるとしたら、直送に比べ無駄が出る。
一方、仮に地域で手が空いている人たちが組織化されたら、もう少し地域の中で物流はまわるんじゃないか、と。つまり大手の配送会社に頼らずとも、ウーバーイーツのように地元の個人の配達パートナーがいれば配送ができるかもしれない…
この事業でも、後半は手の空いてる男性の労力を活用させていただいたのだが、それもこういった妄想の延長でのことだった。
(*)中心拠点(ハブ)に貨物を集約させ、拠点(スポーク)ごとに仕分けて運搬する輸送方式。路線を簡素化することができる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
