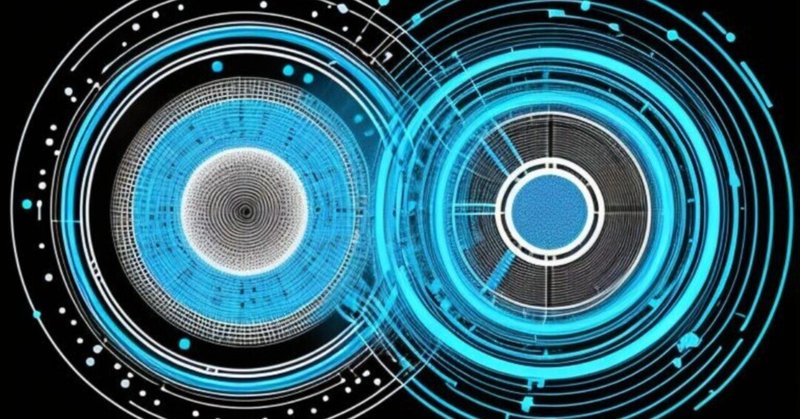
MIMI / HANATABA カバー
こんにちは、作曲家の村松昂です。今日は簡潔に、今年の初めに作ったMIMI作曲、「花束」のカバーを共有したいと思います。
まずは演奏動画
記事の最後に、音源があります。ぜひ最後まで読んでいってください。
—————————
自己紹介の記事でも書きましたが、普段は大学で音楽の研究をしながら現代音楽を作曲しています。
ボーカロイドは声?楽器?
アカデミックな作曲の界隈にいると、ポップスを聴くとか言うのは憚られる風潮があるのですが、何を隠そう私はポップス大好きです。子供の頃から宇多田ヒカルやCarpentersを聴いて育ちましたし、ポップスの曲から作曲のアイデアを得ることもたくさんあります。近年の洋楽のサウンドのクォリティの高さはすごくて、まずその"音"の良さに対してクリエイターとエンジニアの方々に尊敬の念しかありません。J-Popもいろんな良さがありますけど、私は特に日本人ならではの世界観というか、歌詞にしても音楽にしても、"日本人っぽい"、独特の捻くれ方とか、繊細さが好きだったりします。結局日本や日本人が、好きなのかもしれない。
ボーカロイドは世代的に私がちょうど中高生くらいの時に一気にブレイクして、今では世界的に認知される一つの音楽ジャンルになりました。機械音声という意味では、もちろんシンセサイザーに連想される電子音楽の流れを組んでいて、例えばvocoderなどといった20世紀後半の、「人の声を機械に読ませる」技術が頭に浮かびます(classicなvocoderの音の例を作りました。以下にリンクあります)。ボーカロイドの面白いところは、そうした機械音声を、あくまでリリックに、人の"声"を代弁する媒体として扱っていることです。それは、機械音声といえばエイリアン!というようなSFとの結び付きが顕著だった1970年代からは明らかに違うものです。多数の人が、ボーカロイド特有の音に、感情、いわゆる"エモ"を感じるというのはとても面白い話です。明らかに人の声の特徴を持ちながら、機械的にクォンタイズされたサウンドは、一種平坦なニュアンスにも繋がるのですが(その極端な例がvocoderですね)、それが何故かむしろ生の人の声より優しく響く時があるのです。(近年のボーカロイドは以前に比べてはるかにリアルな声に近づきましたが)
またテクニカルな話では、生のボーカルがボーカロイドに取って代わられることで、ボーカルにとっての技術的な制約、例えばメロディーの跳躍やブレスの限界はほとんど問題ではなくなります。声のために書くか、楽器のために書くか、という区別は、西欧音楽でも1600年より以前から存在していた作曲の前提条件の一つでした。それだけ声と楽器というものは異なる性質を持っていて、音楽家にとって技術的・本質的な違いがそこにはあります。ボーカロイドというものは、その前提条件、そしてそこから付随する声・楽器のアイデンティティやエスセティックを、いとも簡単に打ち破ってしまいました。最近のポップスを聴いていると、ボーカロイド音楽の影響、例えば長いフレーズラインや、ピッチとピッチがスムーズでなく階段状につながっていく(弦楽器というよりピアノを弾くような歌い方、といえば伝わるでしょうか)がメロディーや歌唱法に顕著なのは明らかです。YOASOBIやZUTOMAYOが思い浮かんだ方もいらっしゃると思いますが、こうした音楽からは、声と楽器の新しいアイデンティティの可能性を感じます。ボーカロイドは声なのか楽器なのか?それはもはや問題ではないのか?そんな問いかけも、ボーカロイド音楽の面白さの一つです。
しかしそれでも現実として、ボーカロイドの音楽が市場に流れるのは、おそらく日本だけです(間違っていたらご指摘ください)。YAMAHAやRolandのシンセサイザーはもちろん世界中で使われていますし、そもそもYAMAHAのDX7といえば、ポップスや現代音楽も含めた音楽史全体の中でも、重要な転換期を作った楽器でした。それだけ、日本の電子音楽技術は、世界で一線にあって、広く認知されていたものだと思います。そんな中、ボーカロイドの影響が圧倒的に日本で強いのは、やはり日本人特有の感性、価値観といったものが、ボーカロイドにマッチしているのではないでしょうか。私はそこに平安時代の文通文化などを連想しますが、さすがにこれ以上は妄想がすぎるのでここでストップします笑
(ボーカロイドは人の声のサンプリングが基になっているので、vocoderみたいな電子音ベースの技術とは根本が違うだろとか、そもそもKAFUはボーカロイドじゃないだろとか、そういったご指摘もあるかと思いますが、今回はあくまでアコースティックvs機械音声という大雑把な比較でお話ししていることをご容赦ください)
参考までに、YAMAHA DX7についての解説動画。英語ですが、いくつか実際の曲での使用例を聴いて確認できます。
音源を作りました
いろいろ書きましたが、まとめると、ボーカロイドは面白い!ここ何年も自分ではあまり聴いていなかったのですが、友人におすすめを教えてもらって聴いていて、改めていいなと思いました。そんなわけで、大学の冬休みの間、お休みしながらもだらけないように何か作ろうと思って、今回のカバーを制作しました。音楽的には、曲全体を通してコード進行が一定なのが特徴的で、カバーではライブパフォーマンスっぽく、最初に演奏した音をループさせてそれに音をどんどん足していくことで演奏を完成させいています。ボーカロイドをライブで、というのをなかなか見たことがないので、面白いかもしれないなというのが最初の思いつきですね。エド・シーランやパット・メセニーみたいなシーケンサ演奏にも実は昔から憧れていたので、それっぽいことをできて楽しかったです笑 原曲のグルーブ感も特徴的で、カバーでは原曲とは違う形でのリズムの特徴に取り組もうとしていました。
元々は、冬休み中の一日だけ使って終わらせる!という自分なりのルールで、どんなに納得いかないところがあっても戻って直さない、と決めていたのですが、とある友人から音源が欲しいと頼まれたこともあり、一部演奏を録り直して、ミックスも見直してちゃんと音源を作りました。Bandcampのリンクを貼っておきます。無料でダウンロードできます!Bandcampの仕様で、ダウンロードするときに金額を指定して購入することもできますので、もしよければ投げ銭していただけるととても嬉しいです。

https://mm1414.bandcamp.com/track/hanataba-cover-arr-for-live-perform
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
