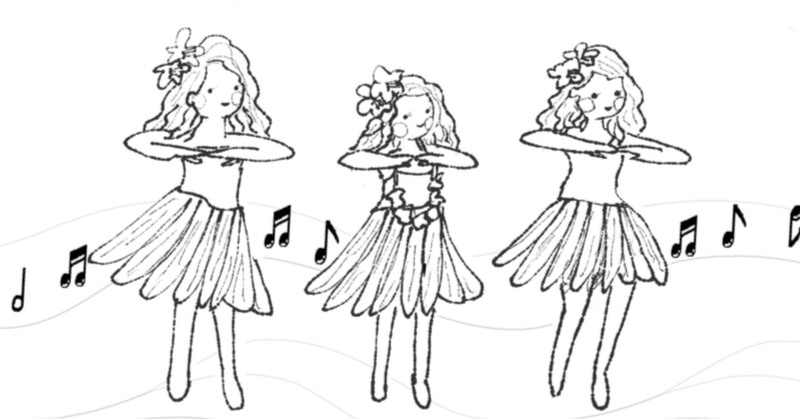
田口ランディ『ハーモニーの幸せ』を読んで 『雨とフラダンス』
何事にも積極的な著者がフラダンスを習い始めます。
しかし、何事にも積極的だと思っていた著者でも、「気分の上がり下がりというのがある。たまたま上り調子のときだったので、ついその気になった。別のときだったら『そうねえ』と言ったまま行動しなかったかもしれない。そういう、タイミングというのは人生にはとても大事だ」と述べている。
タイミングをつかみ取るのも気分次第ということなのだろうが、私には著者にはタイミングを引き寄せる能力があるように思えてならない。
フラダンスの先生から「みなさん、この一週間、いろいろあったでしょう。悲しいこともあったかもしれない。だけど、みなさんはこの一週間で成長しているの。もう一週間前のみなさんとは違うのよ。いっしょうけんめい一週間生きたから、先週とは違う存在なのよ」と言われ、涙を流してしまう著者。
ただなんとなく1週間を過ごしてしまう自分に少し反省する。一生懸命生きていれば人間は必ず成長する。人間は死ぬまで成長を続けていく生き物なのだから、私も一日一日の生きる意味を考えなければいけない。
先生のフラダンスの動きはとても優しい。筆者は、優しい行為を真似ることは、けっこう恥ずかしいし、なんだか偽善っぽく感じるが、「優しい動きを真似るときは、とても素直になれる。」「そうか。動きって、それを真似するだけでもすごいことなんだ。優しい仕草、優しい動きを真似ていると、自分のなかに優しい感情が生まれてくるんだ。発見だった。」「感情をコントロールしたり、変えるのはとても骨が折れる。感情は流れのようなもので、無理強いされるのをとても嫌うし、無理に流れを変えようとするとあふれ出す。だけど、動きに身をまかせてみると、動きから生まれる感情がある。どんな仕草、どんな動きを自分で選ぶかだけでも、もしかしたら人生って変わってしまうのかもしれない。」と思う。
『健全な魂は健全な体に宿る』というが、体を動かすことがポジティブな感情を呼び覚ます効果を与えるのだろう。
著者はこのエッセイで、自分の性格分析を行っている。
「私は、基本的に常に『傷ついている』ほうだ。物心ついた頃からそうだった。いつも、胸のあたりのかさぶたから血を流している。それが私であり、そういうキャラクターなのでしょうがない。」
「私という性格は常に他者をなんとか理解し、他者と共に可能性を模索しようとかなりがんばるほうなので、それが挫折したときのダメージは大きい。そして、その挫折を徹底的に反すうし、分析するまで回顧し続けるので、その副産物として文章が書けるのだ。」「基本的に真面目で暗い。ハメをはずすときも多々あるけれど、とんでもなくはずすことはない。エキセントリックだが大胆ではない。いつも、ちょっとだけ痛い、それを耐えているので、酒とかが好きなんだろう」と思う。
小説家にとって、自分を見直し、分析していくことは必要不可欠な行為なのだろう。私自身も似たような性格で、だから「酒とかが好きなんだろう」という箇所には同感してしまった。
「しょせん他人なんて、誰もそんなに私を必要としてるわけじゃないのだ。そのことを思い知ると、かえって気が楽になる。誰にも答えなくたって、私は生きてていいんだな、って。この取るに足りない自分でいいんじゃん。半ばヤケくそにそう思ったときの、不思議な爽快」さを感じ、「他人でもなく、社会でもなく、私は個性に従って生きてていいのだ、って」と悟る。
自分が必要とされていないという気持ちは、人間にとって一番悲しいものだが、開き直ることによって前向きに生きる筆者の性格がよく現れているエッセイだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
