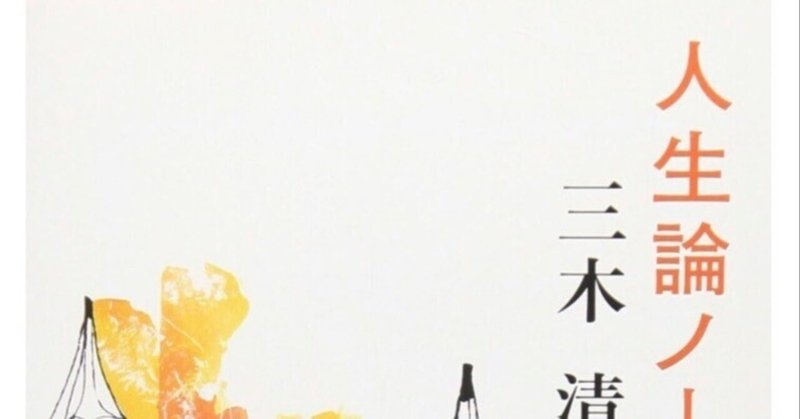
ずっと前に読んだ三木清「人生論ノート」の読書メモが出てきた。確かに今、三木が言う「いかに社会を動かすか?変えるか?というような手だてとしての修辞学」がない。
ノートというだけあって、あまり体系的にまとまっていないけど内容が濃い。何度も読み直してしみじみする。ただ文体は散文集のような本当にメモ書きのような、それでも月刊誌「文学界」に掲載されたのだから、結構な驚きである。
何故今、三木清を読む気になったのか、それは小田実が「彼(三木清)の言う修辞学というのは、つまり社会を分析するんじゃなくて、社会をいかに動かすか、いかに変えるか、というような手だてとしての学です。そういう修辞学がわれわれには欠けているということを三木氏は力説しているんです。」と『対話篇(中村真一郎との対談)』1973で言っていたからである。
死は観念であり、生は形成である。人生は運命であり希望である。人生は希望の生成力である。幸福は人格である。良き習慣が人格を作る。アランの幸福論もヒルティの幸福論も、この良き習慣を作るためのもの(ラッセルの幸福論は読んだことがないのでわからないが)。
「神でさえ自己が独立の人格であることを怒り(その怒りが現れるのは正義が蹂躙された時であり、天変地異であり)によって示さねばならなかった。」 と三木が言うように、最後の審判のあるキリスト教は、素晴らしい思想である。あの権力を欲しいままにしたフェリペ二世も、グレコの絵画が示すように、最後の審判では神妙な顔をしている。(宗教画だから当然と言えば当然であるが)
結局、人事を尽くした後は神頼み。運は人智を超えたところにある。
以上が以前読んだ時の感想で、このメモを読んでの感想は、
