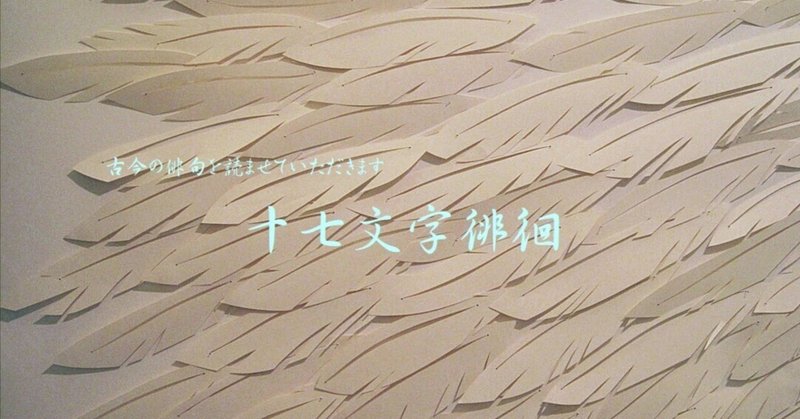
#6 桃さくや片荷ゆるみし孕馬 井月
井上井月の句を見ていると、句に大袈裟なことばの身振り手振りがないところに一番惹かれる。自分のような生半可な俳句初心者でも、概ね理解できる作品がほとんどである。
一定の事前知識等というか文化的素養をもたない人であっても、わかる言葉で俳句を作ったのは一茶であるが、少し時代を下がって井月もそうであるように思う。
といっても、一茶も井月も当人は、詩歌についてはそれ相応に知識や修練の時期が基盤にあった、特に一茶は博学の人であったという人もいる。どのように学識を身につけたかはつまびらかではないが、そのことは残された作品で明らかである。
さて、この句のことだ。
桃さくや片荷ゆるみし孕馬 井月
岩波文庫版の「井月句集」は、手にとって当てもなく数ページ読んでみるのが好きだ。そんなことで、この句を見つけた。
句の意は、見て通りだ。桃が咲いている。傍らに腹の膨れた馬が繋がれている。「片荷」というのは、左右に振り分けらてあるうちの片方の荷。その荷がゆるんで、ずり落ち落ちかけているのか、バランスがよくない。「孕馬」とは妊娠している馬だというのは、言うまでもない。そういう場面が、そのまま句になっている。
井月は、このお腹が大きくなっても荷を背負わせ働く働く馬に同情していと、すぐにわかるだろう。「片荷ゆるみし」というのを放置している馬方か飼い主かの不注意を気にかけている。そこで「桃の花」をそっと贈って、せめてもの慰めとしている、そんな感じに読める。
井月が暮らした伊那地方のことだが、こんな記事も見た。
中馬(ちゅうま)
江戸時代、信州の農民が行った馬の背を利用した荷物輸送業のこと。17世紀、伊那地方の農民が農閑期の副業として数頭の手持ちの馬で物資を目的地まで運送したのに始まる。18世紀初めには活動範囲は広がり、重要な陸上輸送手段となった。輸送物資は米、大豆、たばこなどを移出、茶、塩、味噌、蚕繭などを移入した。中馬は一人で数匹の馬をひき、途中での荷物の積み替えなしに、物資を目的地まで直送したので、その隆盛につれて、宿場で継ぎ送りをしていた宿場問屋側と荷物の争奪戦が生じ、対立した。延宝元(1764)年には、いったん幕府により公認されたが、18世紀中頃に再び紛争が生じた。明和元(1764)年幕府の裁許により完全に公認されたが、明治時代になって衰退した。
この句の馬が、中馬という業務に従事した馬であるかどうかはわからないが、いづれにしろ「孕馬」としては大いなる苦役であったろう。
おなじく信州人の一茶は、たくさんの馬を詠んだ句を残している。なかでも、こんな句。
古郷や馬も元日いたす顔 七番日記
万歳や馬の尻へも一祝
農耕馬は家族と同じ屋根の下に暮らし大切にされていた。
代かくやふり返りつゝ子もち馬 八番日記
田の代掻きには、母馬の後について子馬が田んぼまでついてきたのだ。
そして、こんな句がある。
なぐさみに馬のくはへる桃の花 七番日記
この句、井月が読んでいたかもしれないと、・・・、どうであろう。
井上井月 いのうえ-せいげつ
1822-1887 江戸後期-明治時代の俳人。
文政5年生まれ。天保10年江戸にでる。のち信濃を中心に漂白をつづけ,乞食井月とよばれた。明治20年3月10日美篶村(伊那市)で病死。66歳。越後(新潟県)出身。本名は勝造(克三)。通称は勝之進。別号に柳の家,狂言道人。編著に「家つと集」など。
何処やらに鶴の声聞く霞かな(辞世)
デジタル版 日本人名大辞典+Plus
