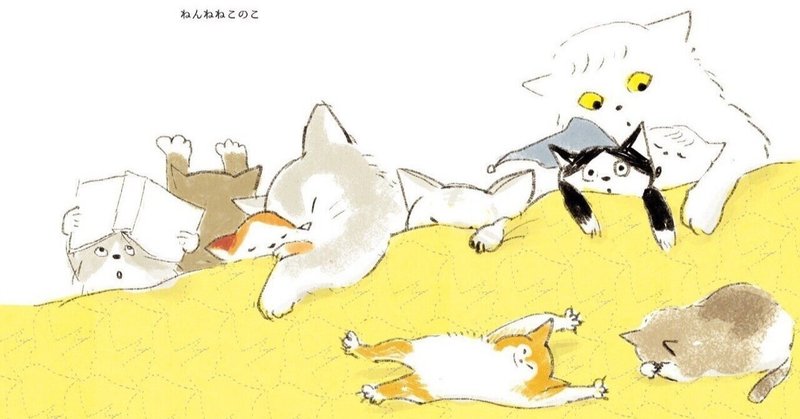
文章のリズムは絵本で学ぶ/「読みやすいね」と言ってもらえる文章を書くコツ③|#112
しばしば「読みやすいね」と言っていただきます。それが有難くて嬉しくて、書くときの脳内整理を試みています。
▽ これまでの記事はこちらから ▽
コメントもいつもありがとうございます!励みになっています。
みゆなさん!こんにちは🌞
— ビーくん🌞@世界史×読書 (@kataru__) January 31, 2021
はじめまして、ビーくんです。
なんて読みやすい文章なんだろう。こんなにスラスラと読める文章は久しぶりに見ました😊
そして即フォロー決定です。これからよろしくお願いします🙇🏼♂️
さすがです!!
文章で伝えることがいかに難しいことかを自覚することがスタートなんですね。ライターさんの仕事、とても美しく感じました。
ー たっちーさん(@banana2)
第2話、お待ちしておりました!ふむふむ🤔すごーく納得です!ペルソナ設定した方が良い記事とそうじゃない記事。たしかにありますね!
伝える気持ちの大切さ、改めて実感しました。。
ー ともきちさん(@lt0218xs)
コピーライターを生業にしているライデンさん(@powercopywriter)にもご紹介いただいちゃいました!
「理路整然とした文章を書く能力があり、しかしながら親しみやすく優しい」ですって、きゃっ、嬉しい!
褒めていただくと調子に乗るタイプなので、「読みやすいと言ってもらえる文章のコツ」をまとめていきましょう!
今日は「表現力を高めるトレーニング法」を紹介します。
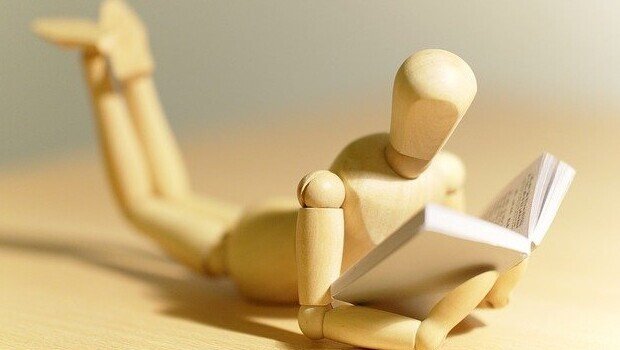
絵本は最高の教科書!
以前、こんな記事を書いたことがあります。
そう、誰もがお世話になった、そして子育て世代にとっては戦友である”絵本”。忘れられない1冊というのは、誰にでもあるのではないかしら?
絵本は「分かりやすく・しっかり伝わり・印象に残る表現力」を鍛えるのに格好の題材だと思っています。だって語彙も文法も習得していない乳幼児を惹きつけるんですから。情緒豊かな絵と【美しくリズミカルな日本語】がぎゅっと詰まっています。
ぜひお家にある絵本を「表現力を学びとる」視点で見直してみてください。お家にない方は、ぜひ書店で!(迷ったら「福音館書店」を選んでね、どの1冊でも間違いないです!)
「あぁ、なるほど…」
そう感じるフレーズに、きっと出会えます。
そして『絵本からリズミカル表現を学びとろう!』というのがこの記事の主旨です。
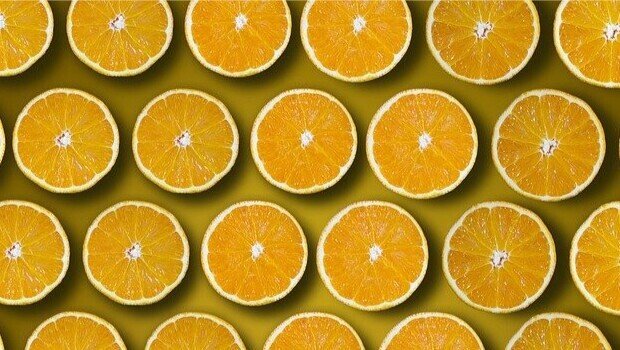
文章のリズム感とは
ありません?テンポよく読み進められる文章って。
逆に内容は良いはずなのに、テンポが悪いがために好きになれない文章も。
文章のリズム感とは、まさにそれ。テンポのことです。テンポよく読み進められる文章と言うのは、論理的でわかりやすいのはもちろん、リズム感が整っていることが多いもの。
「この人の文章、好きだな」と日頃から感じる人の文章を、リズム感・テンポという視点で見てみてください。文章の長短とバランズ、文末表現、感情表現、擬音語や感嘆詞の配置…、全体や部分を一貫する「その人ならではのリズム」に気づくと思います。
◆ 余談
「その人の持つリズム」の発見には、初見ではない文章の方がいいですよ。初めて読む文章(最新のnoteなどですね)は、内容を把握するのに脳内回路の大半が使われてしまうため、文章を”味わう”回路がとても少なくなっているんです。一度読んで内容は知っているものの方が、文章を味わう方に脳のメモリを沢山使えます。
そして心地よく印象に残るリズム感(テンポ)は、絵本でたくさん見つけられます。何冊かご紹介しますね。
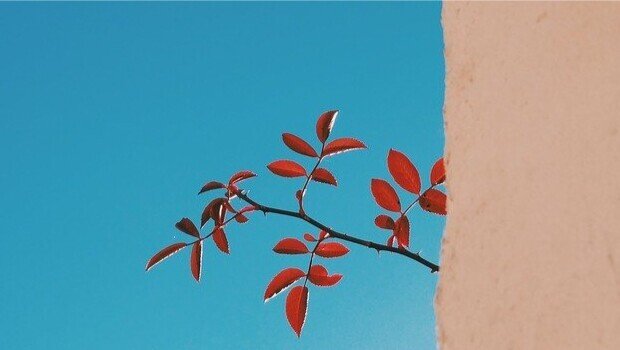
『こぐまちゃん いたいいたい』|表現のミニマリズムが作るテンポの良さ
書版は1971年!ロングセラー『こぐまちゃん』シリーズから。
こぐまちゃんが、子どもあるあるの「痛いよぉ!」というシチュエーションで試行錯誤し、「痛くなくなる方法」を見つていくお話です。
こぐまちゃんシリーズ(しろくまちゃんも同様ですが)は、絵もストーリーもシンプルな分、文章のリズムが際立ちます。有名な『しろくまちゃんのほっとけーき』でフライパンで焼くシーンはその象徴。
さて『こぐまちゃん いたいいたい』から、一節を。
つみきの くるまが ひっかかった
どうして てんぷく したのかな
つみき いたいって いったかな
つみきが すとん
あしに こつん
あ いたい
前半では、積み木を乗せた台車がひっかかって崩れ落ちた様子が、台車を持ち上げた拍子に積み木が足に落っこちてきたのが後半です。
前半3行は、ほぼ同じリズム「4・4・5」。3行目の冒頭だけ「3」にし、テンポを変えています。前半ではまだ客観度が高く、こぐまちゃんと積み木の間に距離がある感じがしますね。
後半は3行で「逆三角形構造」なのがわかりますか?
4・3=7
3・3=6
1・3=4
どんどん短くなるフレーズ!「つみきが おっこちた」なんていいません。「つみきが すとん」です。十分意味が通じ、情景が目に浮かびます。
言葉が少なくなるのに合わせて、積み木とこぐまちゃんの距離もどんどん近くなり、緊張感が高まります!
『こぐまちゃん いたいいたい』は、同じリズムで言葉を重ねると、安定・客観・落ち着きを感じさせ、短い言葉をテンポよくつなげるとスピード感や気持ちの高ぶりを表すことができる。そんなことが学べる絵本です。
『クリスマスには おくりもの』|日本人の遺伝子に刷り込まれたリズム
五味太郎さんの絵本、おすすめです。どれを選んでも、絶対に外れません。1冊1冊、その絵本固有の世界観があり、リズムがあります。迷ったら五味太郎を!
数多い五味太郎さんの絵本の中でも、「リズム感・テンポ」という視点でピックアップしたいのが『クリスマスにはおくりもの』、注目はタイトル。
『クリスマスには おくりもの』、声に出して読んでみてください。
気づきましたか?「7音と5音の連続」で組まれていますよね。説明の必要ないですね、7音と5音の連続は日本人は遺伝子レベルで好きです。落ち着きます。
絵本の内容から考えると『クリスマス”の”おくりもの』でも良いんですよ。でも五味太郎さんは、きっと敢えて『クリスマス”には” おくりもの』にしたと思っています。
五味太郎さんは言葉のリズム感を大切にした方です。全主観の推測ですが、きっと当たっているはず。それほど言葉の並びの美しさはずば抜けています。だからタイトルも「クリスマス”には”」とし、7音と5音の連続で印象を強めたかったたんだろう、そう私は考えています。
迷ったら 7音と5音 つかおうね。
『まちには いろんな かおがいて』|独自のリズムを一貫させる
「シミュラクラ現象」って聞いたことありますか?3つの点が集まると人の顔に見えるという脳の働きだそうです。たしかに、子どもと歩いていると思わぬものを「顔みたい!」と指さしますよね。
そんな街の「あちこちに隠れた顔」を集めた絵本。
この絵本では初夏の風のような、軽やかで楽しげなリズムが初めから終わりまで一貫して使われています。
ぼくが てくてく あるいていくと
まちには いろんな かおがいて
つぎつぎ かおが かおを だす
よう げんきかい
とかおが いう
おでかけですか
と かおが きく
-ちょっと そこまで さんぽにね
たしかに7音+5音の組み合わせは美しい。耳になじむ。かといって、誰もが全てをそのリズムで作れるわけではありませんよね。
この『まちには いろんな かおがいて』が教えてくれるのは、「リズムというものは、初めから終わりまでテンポを一貫させることで全体の印象を整えてくれる」ということです。
この絵本には7音も5音も登場しません。しかし絵本の始まり(先の引用部分)で作られたテンポが終盤まで一貫しています。それは見事なまでに。冒頭で与えられた印象が、最後まで裏切りません。読んでいてとても安心し舞す。
文章全体の調和は、冒頭のリズムを最後まで保つことで作られる。そんなことを教えてくれる絵本です。
『オニのサラリーマン じごくの盆休み』|韻と会話が作る独特のリズム感
オニがサラリーマン!設定だけで大人心がくすぐられますね。大人が読んで面白い絵本、大人だからわかる描写もあちこちにあり。しかもこのオニ、なぜか関西弁!
さて本文から。
オニたちが地獄の掃除をするシーンです。(なぜそんな展開になっているかは、ぜひ絵本を読んでみてください!超お勧めです)。
「ここのゴミ、とってや!
チリトリ、チリトリ!
せきとりと ちがう、チリトリや!
あやとり ちゃうねん、チリトリや!」
「ヤスリを かけて シュシュシュっと」
「みがきを かけて キュキュキュっと」
「韻」はあるだけでリズムがよくなります。音楽のラップは典型ですね。この絵本では、「韻」を「会話表現」に盛り込み、さらにテンポアップさせています。
「会話表現」は、地の文よりもくだけた表現にしやすく、テンポも作りやすい便利パーツです。適度に使うと、文章にメリハリが出ます。ちょっと説明が長くなったな、と感じる直後に入れると、読み手も飽きないんですね。
この絵本はそんな「韻」と「会話」の相乗効果で、楽しげな雰囲気がぐっと高まっています。
文章のリズムを良くしたいと思ったら、「会話表現」と「韻」は活用できる方法です。

絵本を子どもだけのものしておくのはもったいない
日本で1年間に発行される絵本(児童書含む)は、どれくらいの数になるかご存じですか?なんと、年間5000~6000タイトル!(※国際子ども図書館データより|2015~2017年集計)
そして書店には、内容・ストーリー、挿絵、仕掛けなど、昔からは想像できないような工夫が施された絵本の数々。子どもの絵本を探しに来たのに、つい自分が楽しくなって見入ってしまうこともしばしばです。
子どもの興味を引くために、あるいは子どもの好奇心を刺激するために、児童心理を研究して作られた絵本も数多く、その在り様は大人の表現力を高めるためにもとても役に立ちます。
子どもに読み聞かせをするときに、ふと立ち止まって表現を観察してみる。あるいは一人でページをめくってみる。そんなひと時から新しい発見と出会いが生まれます。
絵本はいいですよ。
今日はここまで。あと書いておきたい「読みやすい文章を書くコツ」はこちらです。
✔ 難しい言葉をわかりやすくするコツ
✔ 感情表現の仕方
✔ SEOは必要か?
✔ 一番大切なのは「イイタイコト」
✔ カッコつけない
お楽しみに!
一緒に楽しみながら高め合える方と沢山繋がりたいと思っています!もしよろしければ感想をコメントしていただけると、とっても嬉しいです。それだけで十分です!コメントには必ずお返事します。
