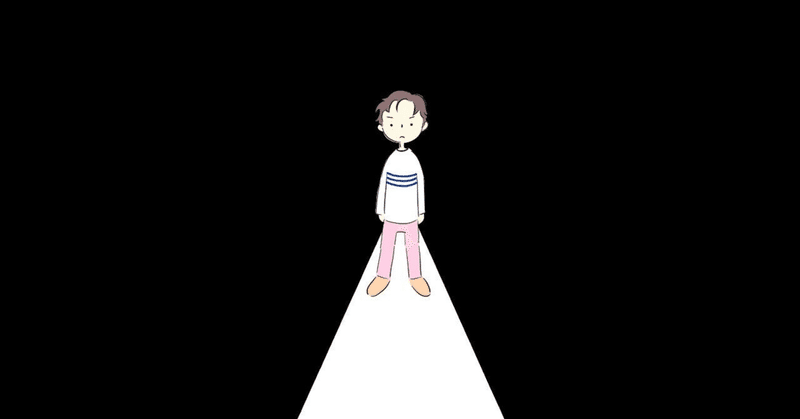
ひとりと、目を合わせたことのないバーの店員
「ひとりと、」シリーズの概要は以下投稿の前書きにて
ひとりは好きだけど孤独が好きじゃないから街に出る私は、それでもときどき孤独を感じることがあった。それも、部屋に籠っていた方がまだましだったと思えるくらいの深い孤独だ。
少し前の話だけれど、月に数回足を運ぶバーがあった。そこは立ち飲み形式で、カウンターテーブルしかないこじんまりとした店だった。決まった店主というのがいなくて、仲良くしてくれる店員もいれば目を合わしたことのない店員もいた。仲良くしてくれる店員はとても趣味嗜好が合い、彼と話すのが好きだったのでそれ目当てでときどき顔を出していた。
とある訪問日、カウンター越しにいたのはその彼ではなく、一瞥もくれない店員の方だった。少し残念に思ったけれど、別にその店員が嫌いなわけではなかったので問題はなかった。ただ心細さを感じてしまったのは正直なところだった。
こじんまりとした立ち飲みバーはその構造上、隣客との距離が近く、ひょんなきっかけで話しかけたりかけられたりすることもあれば、最後まで特に関わらずに時々肘と肘がふれ合うだけのこともあった。私は誰かと絶対話したいという想いがあるわけではなくて、どちらかといえばひとりで喧騒の中で空想にふけっている時間の方が好きなのだけれど、立ち飲みバーというのはどうも“ひとり”が悪目立ちする。もし周りにもひとりの客がいて、その客も空想にふけってくれていたら安心するのだけれど、その日は私の他に同じような客はいなかった。
通されたのはわかりやすく空いていたカウンターのど真ん中で、それは楽し気に話しているふたつのグループの中間だった。さりげなく聞き耳を立てると、右隣はひとり客とふたり客がちょうど心を開いたところのようだった。もしかしたら、タイミング次第では私がそのひとり客側だったかもしれない。別々でわかりやすく盛り上がっているふたつのグループの中間で、私はそんなことを思いながらひとり立っていた。とりあえず声を発したくなって、一瞥もくれない店員に生ビールを一方的に注文すると、彼は返事もせずに冷蔵ショーケースからグラスを取り出した。
私はそれまで、その不愛想な接客を嫌に感じたことはなかった。彼は彼なりに、ひとりでくる客の気持ちを慮って、ひとりの時間を謳歌してほしいと思ってくれているのかもしれないし、もしくは「ひとりで来る客はどうせ出会いを求めてきてるんだろうから好かん」と思っているかもしれなくて、前者であればありがたくもあるし、後者であればそういう客もいるだろうから気持ちもわかる。あるいはそれよりも単純に、私の整えられていない髭面を不快に思われているだけかもしれない。とにもかくにも彼は、両隣のグループに笑いかけていて、私にだけ顔すら向けてくれなかった。その日は私だけひとりで周りがあまりに盛り上がっていたからか、いつもより余計にその態度が気になってしまっていた。
店員は左隣のグループと会話を続けながら、ノールックでカウンターにグラスを置いた。すると生ビールが波を打ち、次第に泡があふれ出してきた。私はそれをどうすることもせず、ただただ見つめる。私なりの静かな抵抗だった。じんわり湿っていくカウンターに罪悪感を抱きはじめた頃には、生ビールの泡はもうほとんどなくなっていた。カウンターと泡はなにも悪くないし、もしかしたらその店員も悪気はないのかもしれない。そう思うと、悪者は私だけのような気がして急に悲しくなった。半分はこぼれ、もう半分は消えていったかつての泡たちに心の中で謝りながら、ようやくビールを口にする。おいしさを約束されていたはずの、私が好きな銘柄のそのビールがおいしく感じられなく思えて初めて、私はその店員を嫌いになった。
相変わらず両隣は盛り上がっていて、時折卑劣な言葉が店内に響き渡る。その度に湧き上がる笑い声も含めて、いつもは別にただの喧騒として宙を漂っていたはずなのに、その日はやけに気に障った。そんな自分の勝手さに嫌気がさす。
「今日はダメだ」
そう思ってすぐに店を出ることも考えたけれど、店に入ってまだ十分も経っていないのに帰るのはなんだか負けたような気がして、せめて一回はおかわりしてから店を出ようと思った。そんな自分の変なプライドにも嫌気がさす。
「生ビールお願いします」
としか発していない男が、店のど真ん中に堂々と立っていることが次第に恥ずかしく思えてきて、背筋を少し曲げてみたりする。そんな自分の自意識にすら嫌気がさす。
一日中家に籠もって仕事してへとへとになって、終わった瞬間孤独に包まれそうになって外に逃げ出したはずなのに、人がたくさんいるところにいながら孤独に囲まれてしまった感覚があって、あぁこれならもっと馴染みの店にいけばよかったとひとり反省会を心の中で始めたりもした。
そのバーにたどり着く直前まで聞いていたラジオがあって、店内に入る前に一時停止してそのままにしていたイヤホンを無意識にふれる。そのイヤホンは骨伝導だから耳の穴は塞がれていなくて、だから何も聴いていないのにつけたまま忘れていることが多かった。ノイズキャンセリングのイヤホンは個人的に少し怖くて、心地よさを約束されない喧騒と、自分次第で約束させられるラジオ(や音楽)を交わらすことができるその骨伝導イヤホンを、私は特段気に入っていた。
その時もつけていることを忘れていて、その私の指はなんだか白雪姫にとっての白馬の王子様のように思えた。王子様の唇が白雪姫の唇にふれるように、左手の人差し指はイヤホンの再生ボタンにふれていて、白雪姫がふと目を覚ますように、イヤホンから先ほどまで聞いていたラジオが急に(無意識だったから少し驚いた)流れ始めた。心地よさの欠片もない周りの卑劣な会話や笑い声は相変わらず聞こえていて、その中に(私にとっての)心地よさが約束されたラジオから流れる芸人の声が交ざりはじめる。その瞬間に初めて、「こういう逃げ方もあるのか」と気づかされた。
孤独から逃げてたどり着いた先でより深い孤独に包囲される。ひとりで街に出るのだからそういうリスクがあることは知っていたけれど、それまではむしろうまくいきすぎていたのだ。今思うと、逃げ道の先にもまた別の逃げ道が続いているということに気づいたその日から、私はひとりで街に出ることがさらに好きになった気がする。孤独との上手な付き合い方を見つけられたともいえるかもしれない。そう思うと、そのきっかけをくれた不愛想な店員のことが少しだけ嫌いではなくなった。
それからもう二杯お酒をおかわりして会計をして、相変わらず私に一瞥もくれないその店員の目のあたりを一方的に見つめて、「ごちそうさまでした」とはっきり声に出した。ドアの方を向く直前、一瞬だけその店員と目が合ったような気がしたけれど、それは私の都合の良い勘違いかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
