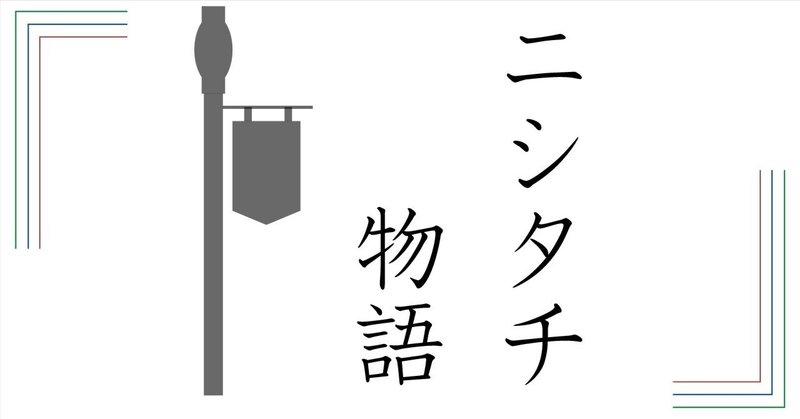
【連載企画】ニシタチ物語
このコンテンツ「ニシタチ物語」は、2016年9月15日から2017年4月21日まで宮崎日日新聞社本紙・県央面連載されていたものです。登場するお店や、登場される方の職業・年齢等は掲載当時のものです。ご了承ください。
「にしたち」は宮崎市の西橘通りの略称だったが、最近は中央通りや西銀座通り、一番街、高松通り、上野町通りなども含めた橘通り西側に広がる歓楽街全体を「ニシタチ」と呼ぶようになった。
宮崎市観光振興計画(2015~19年度)でも同様に位置付け、観光地としてのブランド確立を目指している。

~第1章 変わりゆく街
居酒屋やバー、スナックなどがひしめく宮崎県内最大の歓楽街ニシタチ。仕事の疲れを癒やすサラリーマン、はやりの店で食事を楽しむ若者、名物料理を求める観光客…。人々はなぜこの街に引き寄せられるのか。人と店と街とが紡ぎ出す物語や歴史を掘り起こし、ニシタチの魅力を解き明かすことで、地域資源や観光資源として生かす道を探る。第1章では、変わりゆくニシタチの今を切り取る。
1.店舗
■「食」の色合い強まる
週末の午後11時前。一番街商店街の飲食店「コーナー」は客足のピークを迎える。帰る前にもう1軒、待ち合わせまで軽く一杯…。今でこそ一番街の日常になったが、通りに飲食店が増え始めたのは、ここ数年のことだ。

色合いが強まっている=2016年9月、宮崎市
同店は2008年9月、待ち合わせ場所として親しまれる「ミスド前」の空きビルで開業。老舗すし店や喫茶店などを除けば、洋品店や雑貨店など物販店が中心だった当時の一番街で、新規飲食店は異色とも言えた。
「最初は赤字続き。街に人があふれていても店はがらがらなこともあった」とオーナーの村岡浩司さん(46)。しかし、同店をきっかけに通りには飲食店が増え、「食の街」の色合いを強めていく。
「飲食店が増えることに抵抗がないと言えばうそになる」。約40年前から一番街で靴店とたばこ店を営む浅岡日支生さん(78)の言葉には、県内随一の商店街とともに歩んできた自負がにじむ。「でも、そんな時代じゃなくなった。飲食店がなければ空き店舗ばかりになっていたかもしれない」
1997年に1万5千人以上だった一番街の休日通行量(宮崎市調べ)は、郊外に大型ショッピングセンターがオープンした2005年以降、急速に減少。13年には4800人にまで落ち込んだ。買い物客の減ったアーケードで新たに物販の店を立ち上げようとする人は少ない。代わって進出してきたのが大型店と競合しにくい飲食店だった。
こうした傾向はニシタチ全体でも同様で、国の統計によると、09年にエリア内で188事業所あった小売・卸売業者が、14年は160事業所に減少。一方、飲食店がほとんどを占める飲食店・宿泊業は1063事業所から1129事業所へと増えている。
みやぎん経済研究所の主任研究員・杉山智行さん(45)は「景気回復の兆しが見えない中、限られた所得を物より体験に使う傾向が続いている。飲食店の集積は今後も進む」と予測。「物販とのバランスも大切」と前置きした上で、「1次産業主体の宮崎で、ニシタチは地元の食を体験できる重要な拠点。集積によって街の魅力はさらに高まるだろう」と見通した。
2.宴の形
■少人数で個室 主流化
「昭和のニシタチは大口の宴会が多く、あちこちでどんちゃん騒ぎがあり活気があった」。1947(昭和22)年から続く、老舗居酒屋「たかさご」=橘通西3丁目=の3代目社長山本健治さん(67)は懐かしむ。現在の店内は少人数の利用が主流となり、以前とは随分と様子が違っているためだ。

40~50人規模の大きな宴会が減少している
「平成に入ってバブル経済が崩壊すると接待は減り、飲酒運転撲滅のため飲み会の自粛も始まった。上司と飲みたがらない若者も増え、趣味やスマホに金を回すのか飲む回数も少ない。40~50人規模の大宴会は忘年会シーズンを除けば激減した」。大宴会が減った理由を、山本さんはこう考えている。
同店は1~3階のフロアに160人を収容する大型店。大人数で訪れる客に対応するため使っていた宴会場は、92年の建て替えを機に少人数で利用しやすいようにパーティションで仕切りを入れた。今では宴会場を利用するのは若者より高齢者が目立ち、職場のOB会や仲の良いグループが現役時代の懐かしい話に花を咲かせているという。
県内の飲食店を数多く紹介する情報誌「パームス」=宮崎市田吉=編集長の国府秀紀さん(48)は「気心知れた少人数の仲間で楽しむ、というのが時代の流れ」と分析。
居酒屋が繁盛する条件として(1)飲み放題コース(2)掘りごたつ(3)個室-を挙げる。「支払う金額が分かり、快適に過ごせるプライベート空間でくつろぐのが今のニシタチスタイル」と解説する。
2013年7月にオープンしたおでんダイニング「花歩」=中央通=は、その条件を満たす店の一つだ。客は20代半ばから60代の男性が7割を占め、85人を収容できる2階建ての店舗は、仕事帰りのサラリーマンを中心ににぎわっている。

高く、平日も多くの予約が入っているという
20代からニシタチで働き念願の独立を果たした社長の神足(かみたり)奈歩さん(41)はにこやかに接客しながら「2、4、8人に対応する個室は平日も予約で埋まる」と、酔客のニーズを感じ取っている。
「昔のニシタチには、一人でもふらりと立ち寄れてくつろげる店が多かった」と話すのは、8月に小料理屋「護隆庵」=橘通西3丁目=を開店させた池田隆二さん(46)。カウンターとテーブル席二つに20人も座れば満員になるコンパクトな店だが、その雰囲気に誘われて、上々の滑り出しという。
客の評判は「オープン直後『一人ちびちび飲める店ができてうれしい』と言ってもらえた」と池田さん。大宴会が減り、はやりの小宴会にターゲットを絞る店もあるが、「こぢんまりした空間で知らない者同士が楽しく語らう。それもニシタチの飲み文化。しっかり継承したい」と話す。店内に流れるのは石原裕次郎と美空ひばりの曲。この趣向も、昔からの酔客に楽しんでもらえるという。
3.若手の台頭
■こだわりの店で新風
松田温郎さん(28)は中学卒業後、何軒かの飲食店で働いた後、ニシタチのバー店に入った20歳ごろから夜の街に興味を持ち始めた。すると働きぶりが認められ、21歳の若さで店長に。それからわずか2年後の2012年8月には独立し、ビールバー「ビアマーケットベース」=上野町=を開店した。
店の売りは、80種類にも及ぶ国内外のビール。店内には職人らが味や製法にこだわって造るクラフトビールを中心に並べている。近年は「飲食店が提供する酒類のうちビールの割合はここ20年で6割から4割に減った」(吉野酒店相談役・寺原博志さん)といわれていることを考えると、時代に逆行している。しかし、そのこだわりが評判を呼んだのか店内はにぎわいをみせており、松田さんも「宮崎にない新しいビール文化をつくりたい」と力強い。
ニシタチでは今、松田さんのような若い経営者たちが、自分たちなりの工夫を凝らした料理やサービスで新風を吹かせている。
13年4月、スペイン居酒屋「ハイヴォレ」=中央通=を開いた西本昌義さん(38)もその一人。

サイズのかわいらしい料理で人気が高い
西本さんは都農町出身。15歳から7年間、山口県のホテルで西洋料理を学び、さらに宮崎市内の店で12年間働いてきただけに腕には自信を持つ。人気メニューはピンチョス。肉や野菜、魚介類などさまざまな具材を串に刺した一口サイズの料理だ。見た目がかわいく種類が多いこともあって、口コミで評判が広がった。
「(妻の真由美さんと)2人で対応できる広さと家賃の兼ね合いを考えて決めた」という店内は、カウンターや個室に26席を設け、白と赤を基調にしたおしゃれな内装で好評。週末にはよく女子会が開かれるという。
サーフィンが趣味の福吉正明さん(37)は、本県海岸の波に魅せられて大阪から移住してきた。生活のためもあって大阪の焼き鳥屋で修業を積み、08年11月、貯金を元手に焼き鳥屋「しろきじ」=中央通=をオープンさせた。

「ワインの飲める焼き鳥屋」として客の評判を呼んでいる
店を構えた場所は、広さ6坪(20平方メートル)ほどの小さな店が軒を連ねる「人情横丁」という通り。店を選んだ決め手は、「調理場に立つとまだ見ぬ客の姿が浮かび、『成功できる』と根拠のない自信が生まれた」こと。さらに、大阪で勤めていた店と同様に「ワインの飲める焼き鳥屋」としたところ、予感通り、これが受けた。
ニシタチで夢をかなえようと次々に参入する若手経営者。同市内の店舗物件を多く手掛ける不動産業者トライスター=宮田町=社長の渡邊将史さん(39)は「家賃の値下がりも後押ししている」と見る。景気の低迷もあり「2階以上の物件は10年前の7~8割。中には敷金を抑えたり、改装費の一部をビルオーナーが負担するものもある」。
福吉さんも「中心部から少し離れれば、挑戦しやすい家賃の物件は多い。意欲ある若い人にぜひもっと進出してきてほしい」と一緒に盛り上げる仲間を求めている。
4.進む浄化
■居心地良さ求め一丸
「40年近い警察人生の中でも、あの2年間は特に大変だった」。宮崎北署の鳥井宏一署長(59)は、ニシタチの前線基地・同署橘通交番に勤務していた1985(昭和60)年当時を振り返る。
夜間の忙しさは県警随一と言われる同交番。飲食店からみかじめ料を巻き上げ大手を振って歩く暴力団、絶えない酔客同士のけんか…。年末には応援も含めた警察官20人全員が出払うこともあった。身長180センチ、体重90キロの機動隊上がり。体力に自信はあったが「週末の夜勤前になると胃が痛んだ」。

「楽しめる街を守るのも飲食店主の役割」と話す
あれから30年。署長として県内最大の歓楽街をあずかる立場になり、気付いたことがある。「路上で酔った女性が寝ていても、何事もなく周りが通報してくれる。過ごしやすい街になった」。私服警察官による巡回を強化するなど署を挙げてニシタチの治安維持に取り組むが、「通りの方々の努力あってこその変化だろう」と感謝する。
2000年代初めのニシタチは、人によっては居心地の悪い街だった。露出の多い女性の写真とともに、性的好奇心をあおる言葉をプリントした「ピンクちらし」の配布が横行。性風俗店などのしつこい客引きや、ラウンジなどで働く女性をスカウトするための声掛けが日常だった。
「これじゃ、人を連れて来られないよ」。西橘通りにスナック「夕鶴」を構え、県社交飲食業生活衛生同業組合宮崎支部長を務める矢野和昭さん(66)は、常連客の言葉を鮮明に覚えている。温かい街の雰囲気が失われることを危惧した矢野さんら飲食店主有志らは一念発起する。

たち。飲食店主らの要望もあり、規制が強化された
=2009年11月(一部モザイク加工しています)
昭和60年代から暴力団追放など街の浄化へ向けて協力してきた店主らは、市や市議会議員、県警に対策を要望。05年にわいせつなチラシ配布を禁じる市の新たな条例が、10年には客引きの規制を強化した県の改正迷惑防止条例が施行されることになる。
「街を守るのも飲食店の役割」。矢野さんらは今も、県警と連携して街を毎年巡回。暴力団の追放や飲酒運転の撲滅を呼び掛け続ける。
こうした取り組みもあって、昨年の橘通交番管内の刑法犯認知件数は268件で10年前から3割近く減少。風営法に違反する時間外営業や、通りの統一感を乱す派手な看板など課題は残るものの、誰もが安心して楽しめる街へ一歩ずつ近づいている。
ニシタチ愛好家でつくる異業種交流会・宮崎燦々会は3年前から毎年1回、通りを清掃している。会長を務める会社員の高橋俊一さん(64)は年々少なくなるごみの量に「街の雰囲気が良くなったことで、飲む人の気持ちにも変化が起こっているのではないか」と感じ取る。
「今のニシタチなら、誰にだって自信を持って紹介できる。どうか、ずっとそうあってほしい」。高橋さんの願いは、この街を愛する全ての人の願いでもある。
5.意識
■魅力創出へ店主連携
8月下旬。中心市街地のビルの一室で意見交換会が開かれた。顔を並べたのは、県内最大の歓楽街ニシタチを形成する通りや商店会の代表ら10人。これまで、一つの街という発想や意識は薄く、こうして一堂に会し、同じ視点で語り合い、将来を考える場を持つのは初めてだった。

設置したが客足は遠のき、店主らは連携を模索し始め
ている
「週末以外は人通りがほとんど無くなった」「客が高齢化している。若い人を呼び込む仕掛けが必要」-。厳しい現状を訴える声とともに、連携に前向きな意見も出た。参加した青空通り商店会長で、創業84年の「まつをうなぎや」4代目松尾樹則さん(48)は「情報を共有し知恵を出し合うことで、人を呼び込む起爆剤を生み出せるのでは」と期待を込める。会合は今後も定期的に続け、集客イベントなどを計画していく予定だ。

会の発起人は、西橘通りでバー「KURA」を経営する岩元久俊さん(59)。同通りや中央通りの飲食店主らを中心に立ち上げた「ニシタチまちづくり協同組合」の3代目理事長でもある。同組合では街灯を設置したり道路の補修をしたりなど、環境整備を進め集客に取り組んできた。
しかし、シェーカーを模したレトロな街灯が、通りのシンボルとしてなじんでいく一方で、取り巻く状況は年々厳しさを増している。「個人消費の低迷や娯楽の多様化などいろんな要因がある」と岩元さん。売り上げ減少を訴え、廃業する仲間も増える中、動かずにはいられなかった。「個人や一つの通りだけではどうにもできない。各団体の垣根をなくして、アイデアを出し合い現状を打開したい」
ニシタチが歓楽街全体を指す言葉として認識されるようになって久しい。中央通商店街振興会長の岩崎幸治さん(56)は、通りへの愛着やプライドから、会員にはニシタチと総称されることに違和感を持つ飲食店主もいると明かす。しかし、「お客さんにとっては同じ一つの歓楽街。それならば、県内外に定着した“ニシタチ”という名称や広がりを生かさない手はない」と前向きに捉えている。
ここ数年は、隣接する西橘通りや高松通りの店主らとゴルフコンペや感謝祭を開くなど交流を深めてきた。「行きたくなるような店や通りを作る各自の努力はもちろん必要。その上で、街に行けば何かがある、というかつてのワクワク感を皆で取り戻したい」。“ニシタチ”の旗印のもと、街は解け合いながら前に進もうとしている。
=第1章おわり=

~第2章 老舗の記憶
ニシタチには40~50年続く店も少なくない。老舗の記憶をたどりながら、県内最大の歓楽街が積み重ねてきた歴史に触れる。
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
