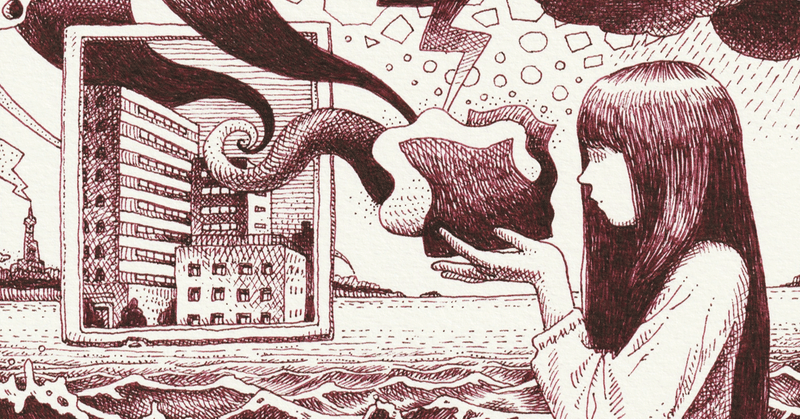
声を合わせ、歌える日々
1991年第58回NHK全国学校音楽コンクール(通称Nコン)で、高校生の部、合唱課題曲だった『聞こえる』。作詞 岩間芳樹 、作曲 新実徳英 。
この年、高校2年生だった私は、合唱部でNコン出場のためにこの曲のピアノ伴奏をした。
高校に入学して、運動が苦手なのにイキって某運動部に入部してしまい、でも案の定、トレーニング段階からまるでついていけず、その上OBコーチのパワハラまがいの指導と怪我でボロボロになり、結局1年持たずに退部してしまった。そんな時、同じクラスの合唱部の子が、ピアノが弾けるなら伴奏者として入部しないかと声をかけてくれたのだ。
申し出は、ありがたいと感じる反面、私は多分ものすごく視野の狭い傲慢な子だったから、運動部という今で言えば陽キャの集団からこぼれ落ちたことにわだかまりを抱いていた。合唱部のような文化部=陰キャの集まり、なんて失礼極まりないレッテルを貼り、あくまで片足は外に出しておこうと、練習参加も全体の6割くらいで歌うのは頑なに拒否していた。小学生の頃に合唱団に所属していたのだから、本当は一緒に歌ってみたくて仕方なかったくせに。
それでも、夏休みには、部の合宿に参加した。茨城の森の中の合宿所でたしか2泊3日。合唱部は人数が少なくて、他部との兼部やコンクールだけの助っ人全員あわせても15人ほど。けれど、先輩も含め部員は皆穏やかで優しくて怖いOBも来ない。和気藹々とした雰囲気は、前年参加した運動部の殺伐とした合宿とは真逆だった
私は、自分が歌わないのをこれ幸いと、他の部員がランニングや腹筋などのトレーニングに励むのを尻目に、涼しい練習スタジオでひたすらピアノを弾いていた。伴奏を担当する課題曲はもちろん、それ以外の譜面のある自曲や、合唱定番曲など。高校入学と同時に、ピアノ教室は辞めていたけれど、辞める前でもこれほど朝から晩まで一日中ピアノを弾いていたことはついぞ無かった思う。
全体練習の時はだいたい指揮者を中心に本番と同じ配置で練習をすすめる。けれど合宿中は時間がたくさんあるから、それ以外でも伴奏があれば、いつのまにか誰かが歌い始める。
大地讃頌
混声四部合唱
グランドピアノの周囲をぐるっとかこんで、大地讃頌などの合唱定番曲を私の伴奏で歌ってくれる。そして、課題曲『聞こえる』の歌声。
時代が話しかけている
世界が問い掛けている
見えている 聞こえている 感じている
だけど なにもできないこの部屋で
膝を抱いてうずくまっている いらだち
教えてください 何ができるか
光っている道を 心開いて歩いていきたい
何ができるか教えてください
鍵盤を弾く半袖の腕に鳥肌が立ち、譜面がぼやけてしまいそうになるのを必死にこらえた。自分のぐるり360度からきこえる歌声に包まれて、このときほど、ピアノが弾けて嬉しいと感じたことは無い。
私は、伴奏者として部に誘ってもらったけれど、ピアノの力量は本当はたいしたものでは無くて、部内に私よりもずっとレベルが高く情熱的な演奏をする男子部員がいたし、指揮をとる部長の女子も余裕で私より上手かった。なのに、私に伴奏を委ね、その伴奏にあわせて歌ってくれた。彼らは、私に何ができるのか教えてくれた。
コンクールの後、それぞれの譜面にメッセージを書きあうのは音楽系の部活の定番だと思うけれど、何人もが私の譜面に「優しい伴奏だった」「穏やかでとっても歌いやすかった」と書いてくれて、私はそれまで自分のピアノの弾き方は結構独りよがりの好き放題弾く系だと思っていたから、お世辞だとしても思いがけなくて嬉しくてまた泣きそうになった。
ひとつ「貴方はきっと良い声だから、次は是非歌ってほしい」というメッセージがあった。歌いたいという私の本心を見抜かれていたのかも、となんだかそれも嬉しくて、声を合わせ思う存分歌えるということが、どれだけ尊く幸せだったかと思い知らされた今、30年越しでその言葉に導かれてみようかなどと考えている。
◇
この頃に出会えた、素晴らしい合唱曲たち。
混声合唱組曲「筑後川」 より Ⅴ.河口
丸山 豊 作詩 / 團 伊玖磨 作曲
花に寄せて
1:たんぽぽ 2:ねこじゃらし 3:しおん 4:つばき やぶかんぞう あさがお 5:てっせん どくだみ 6:みょうが 7:ばら きく なずな -母に捧ぐ-
星野冨弘 作詩 / 新実徳英 作曲
エトピリカ(合唱組曲「海鳥の詩」より)
廣瀬量平/ 横浜紫友会合唱団
◇
#思い出の曲 #部活の思い出 #音楽 #合唱 #エッセイ #高校生 #歌 #ピアノ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
