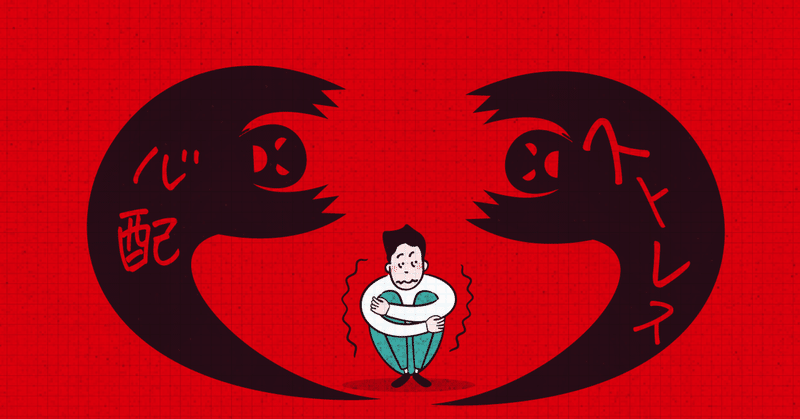
委員長の予定者がはじまるあなたへ
こんにちは!
光秀マインド足立聖忠です!
昨日は単年度制である青年会議所の役職による新旧交錯の話をしました。私にとってたしかに新旧交錯する2回目の理事も大変でしたが、一番大変だったのは初委員長の時でした。
年初に私の役職を受けた時の記事を少し書いていますが、予定者が始まるこの時期のことを改めて書こうと思います。
私が最初の委員長を受けた時予定者でまず頑張ったことは
①活動方針の作成
➁委員会メンバーのドラフトと第一回委員会の開催
③第一回理事予定者会議と初上程、初審議
の3つです。
活動方針とは、1年間の活動を800字にまとめるものです。最近はサマリーというものに変わってきていますが福知山はまだ活動方針を書きます。
自身の委員会設置の背景。その背景課題を各例会でどのように解決もしくは目的達成していくかの記載。そして委員会の1年後の目指すべき姿でまとめます。この文章がとても難しいです。主語が無かったり、複数あったり、目的がぼやけたりと指摘されているうちに自分も良くわからなくなります。そんな時は文章の整理が有効です。主語をしっかり書くことと、1文を100~150字くらいにしないと読みにくくわかりにくい文章になります。
理事会では文章の1文1文に意見というよりは質問が沢山きます。これは自分の想いに対して答えたり伝えたりできるかを試されています。自身が無かったり、不安になるようならそれはまだまだ自分の想いを強く固めれてない証拠です。
次に委員会のメンバー選びです。福知山はドラフトをする場合が多く、委員長が集まり自身の副委員長をしてほしい人、その次に幹事を任せたい人と順に決めていきます。そして第一回の委員会の招集です。第一回の予定者委員会は理事長専務が志をもって挨拶に来られるのが福知山の通例です。本年度の予定があるのかで次年度の動きやスケジュールを合わせるのが至難の業ですが、この委員会メンバーが全員集まり、方向性や今後を一緒に話せる場はとても重要です。この予定者のまとまりや気持ちの入り方が本年度が始まった時の委員会の盛り上がりにもなります。
私が委員会で重要にしてポイントは「委員会は実施時間と内容を決める」ことです。集まってからダラダラと意見の出し合いをするとエンドレスになります。メンバーは仕事に家庭にプライベートと忙しい人ばかりです。集まった時の時間の使い方が非効率だったり、生産性が無いと2回目からの優先順位を下げられてしまいます。
集まって一緒に頑張る仲間ですが、委員長は委員会メンバーにとって委員会が価値のあるものにする責任があります。それは楽しさなのか、学びなのかはその委員長次第ですね。
最後に初上程と初審議です。理事になった以上最大の学びであり試練は理事会の上程です。これは昨日の記事にも書きましたがしっかりと向き合う事です。ふてくされたり言い訳して一番損するのは自分です。
初委員長を頑張る皆さんのアドバイスになれば幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
