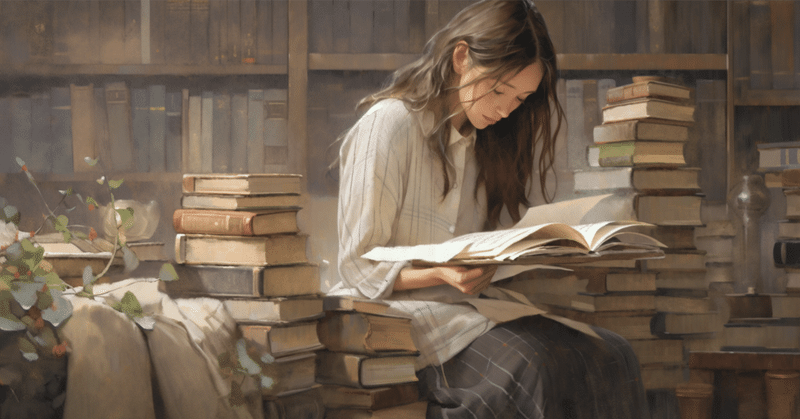
読書を仕事に活かす”併読合わせ技”。
おはようございます!今朝も勢いで書きます!
私はおよそ一カ月に15冊くらいの本を読む。それはコンサルタントの仕事をするようになってからの習慣だ。私がコンサルタントを目指すようになった頃は、まだ携帯電話も使い始めの時代。今のようにネットで情報を検索して調べるというようなことはできなかった。
なので、本は情報を得るための貴重な情報源だった。船井幸雄さんはもちろん、上司やトップコンサルタントからはとにかく本をたくさん読むように言われた。その習慣が今も続いている。
今は読んだ本を読書録としてフェイスブックで挙げている。そうすると、「よく本を読んでいますね。」と言っていただくことがある。本を読む習慣がない人にとっては、そのように思うのだろうが、コンサルタントにとって本を読むのは当たり前の話であり、その中では私の読書量は決して多いものではない。なかには、1カ月で100冊読むような人もいる。これは一日3冊ペースなので、相当な量だと思う。
さて、せっかく読書をするのだから、それを仕事など生活に活かしたいと考える。私もそうだ。特に、ビジネス本や自己啓発本は、一冊につき一つは実践するようにしている。
そのようにして活かす方法もあるのだが、他に私は二冊以上の本を組み合わせて実践することもしている。一冊の本のボリュームは200~300ページ。多いと感じるかもしれないが、著者にとっては、これぐらいのページ数だと言いたいこと、伝えたいことを絞り切らないと書ききれないボリュームである。
また、他の本との違いが感じられなければ売れないために、より尖った内容になる。様々なことを広く書くよりも、絞り込んで尖らせて書く。そうすると内容は面白いのだが片寄りも生まれる。
例えば、「優れたリーダーは部下は見ていない」という本がある。これは、部下のやりがいを高めようと考えるのではなく、まずはタスクを明確にして、それを実行させるようにしろ、という内容。そうすれば、部下のやりがいも高まる。やりがいは先にあるものではなく後にあるものという考えや、タスクマネジメントを進めるための実行法を紹介している。
確かに、そうだ。しかし、これだけを進めると部下とのコミュニケーションがうまくとれなくなる可能性もある。タスクを伝えるだけで実行してもらえれば、そんな簡単はことはない。しかし、部下は機械やロボットではない。感情もある。もし、タスクができなかった時は、どのようにフォローをすれば良いのか?その内容はこの本では紹介されていない。
そこで、もう一冊「だから僕たちは、組織を変えていける」という本を読む。これはコミュニケーション法やリーダーシップ法など人に寄り添った組織運営法が紹介されている。タスクマネジメントとは対極にあるような内容だ。しかし、これだけでは、実際の組織は変わらないとも思う。あるいは、多くの時間がかかり過ぎてしまう。
そこで、この二冊を組みあわせて実践する。タスクマネジメントを基本としながら、組織内の風土づくりはこの本で書かれていることを実行する。
大量の本を読んでいると、一冊の本からではなく、二冊以上の本を組み合わせたアイデアや考え方を実行できるようになる。このような「本の組み合わせ技」は、なかなか面白い。
読書量を増やして今日もステキな一日に。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
