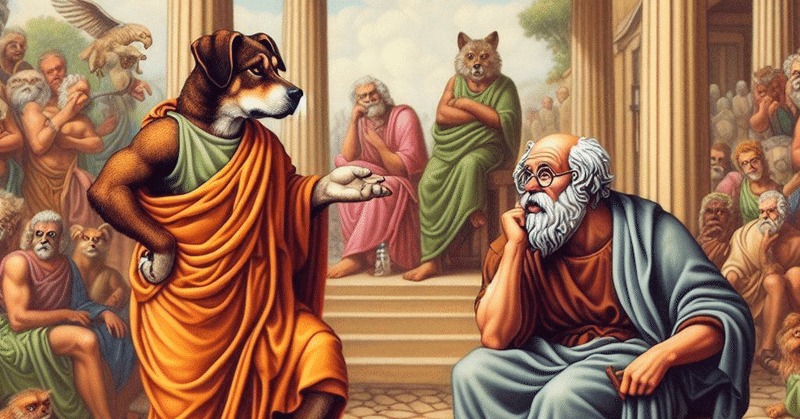
それは、延命治療?②
前回、体に酸素を届ける方法が、どの様な時に延命治療となり得るか?
体への負担(侵襲)という方向から説明しました。
今回は、どれだけ大掛かりか、という事を考えてみたいと思います。
要は、今居る場所、入院してたら病棟、救急で運ばれたら救急外来で対応するかどうかです。
体に酸素を届ける方法として、
①鼻カヌラ
②リザーバー付き鼻カヌラ
③普通の酸素マスク
④ベンチュリーマスク
⑤マスク型の人工呼吸器(非侵襲的陽圧換気)
⑥気管挿管をしての人工呼吸
⑦体外式膜型人工肺(エクモ)
をあげました。
これらは順番に、大掛かりになるし、治療のために関わる人数も多くなります。
①〜④は、酸素ボンベなり、配管なり、酸素を供給するものがあれば使えます。
⑤、⑥のマスクまたは気管挿管による人工呼吸は、急性期病院と言われるところは、ほぼ対応可能と思います。
ただし、病院でも、療養病院、リハビリ病院なんかは、そもそもの設置目的が違うので、対応できない事が多いです。
余談ですが、一言で「病院」と言っても、目的別に設置されていて、できる医療の範囲も決まっているのが、最近の医療機関です。
次に⑦体外式膜型人工肺(エクモ)に関しては、大学病院並みの大病院でしか対応できません。
で、
今いる場所でできる酸素投与方法では酸素が十分に体に送れなくなった時、
どうするか?
例えば、酸素マスクでは十分に酸素が体に送れなくなった時、人工呼吸器がその施設に無かったら、治療を強化するのであれば、移動するわけです。
ただ、移動は、本人に取っても、家族を含めた関係者にとっても、負担になります。そもそも状態が悪い時に移動すると、移動中に急変してしまう可能性もあります。
なので、治療を強化する事は、本人や周りの負担・危険性と、危険を犯して移動・治療する事で本人・家族が幸せになれるか
を、考える必要があります。
ただ、そういう時は、考える時間が限られています。
どんな危険性があるかは医療側から説明があるとしても、最終的な決断は、本人や家族なので、普段から何となく考えておくことが必要だと思います。
次回は、その治療は中断できるか?について考えます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
