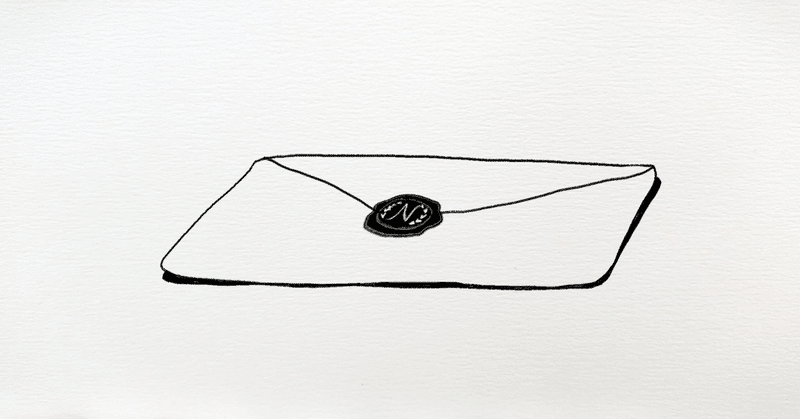
今までしてきたのは"勉強"じゃなかったかもしれない。と、思い知った院試 #受験体験記
#受験体験記 のトピックを見つけたので、懐かしくなって参加してみました。
最後の受験は、大学院入学試験=院試
文学研究科文化表現論専攻博士前期課程中途退学
これが私の最終学歴です(いかつい!)。大学で所属した研究室をそのまま内部進学し、修論書かずに辞めました。
ということで、私の最後の受験は院試です。
大学受験までには経験しなかった壁がいくつもありました。大学院進学率が低い文系学部の院試体験、こんなもんなんだ〜と思いながら見ていただけると幸い。とはいっても、10年前の話なんで、記憶は曖昧ですが。
①何を勉強したらいいのか、分からない
試験の科目は、専門分野の試験、英語、第二外国語、口頭試問でした。大学受験に比べると科目少ないやんって思うでしょ?
ところが、まずは「専門分野」の範囲が広大すぎる。という壁にぶち当たるのです。
音楽の研究室(注:文学部ですが)だったけど、音楽といっても…ボカロからグレゴリオ聖歌からお琴からタイのポップスまで、それはもう多種多様な「専門分野」が共存するような研究室です。
教授はハンガリーの民族音楽、准教授は戦後日本の大衆音楽、私は18〜19世紀の西洋クラシック音楽の演奏会史が専門でした。
「専門分野」の範囲、もはや無限大。
もう何をどのように勉強したらいいのか分からず、教授や先輩に泣きついてアドバイスを乞うた記憶があります。でも結局何をどのように勉強したのかは覚えていません(役立たず)。
②フランス語の単語が覚えられない
私は大学で選んだ第二外国語がフランス語だったので、試験もフランス語を選びました。そこで、高校受験から数年、脳の老化をひしひしと実感することになります。
内部進学者に対しては「専門分野と口頭試問は最悪どうにかしてあげられるけど、語学はどうにもできない。語学の足切りだけは自力で回避してくれ」ってスタンスだったので、余計に。
足切りの恐怖と覚えられない単語にうなされた大学4年の夏、とにかく仏検の単語帳と文法の参考書を頭に詰め込みました。
そして実際の試験で1問目の長文和訳の問題が「solitudeとは云々」で始まる文章だったの、今でも覚えています。なぜなら、その「solitude」の和訳をちっとも思い出せなかったから。
結局、「主語がわからない…詰んだ…」と絶望しながら残りの文を和訳し、文全体からなんとなく想像して、空けておいたスペースに「孤独」と書き込みました。終わるなり辞書をみて胸を撫で下ろしたのは言うまでもありません。
おかげでsolitudeが孤独ってこと、一生忘れない(でもきっと一生使わない)。
③口頭試問は研究内容に左右される
自分の研究テーマが、教授や研究室と親和性があれば、受かりやすい。そうでなければ、少し厳しい。これは同期の内部進学生同士の会話から、感じたこと。
ひいきではなく、「自分の専門がクラシック音楽ど真ん中なのに、最先端のゲーム音楽を専門にする学生の研究の面倒みなきゃいけない」っていう、教授の視点で考えるとおかしくないと思います。
その学生を自分の指導下に置いて、育てられるか?その影響で自分の研究が疎かにならないか(教えるだけじゃなく研究自体も仕事なので)?その学生の人生にとって大学院進学はプラスになるか?
それはとても重要な問題だと思います。
ただでさえ、所属したから資格がとれたり就職に有利になるような学部ではないから。
私の場合、そもそも教授の研究と親和性があったことで、かなり優しめの対応だったと思います。
あと、あくまで憶測ですが…女性の研究者を増やそう!という流れがあった時代、「この子、育てたら使えるかも」と思われていたのかもしれません。
まとめ
大学受験までは、教科書という範囲が明確に存在して、それをできる限り完璧に理解すればよかった。
それが院試になると。無限に広がる宇宙のなかに自分でピンを立てて、ステーションを組み立てていかなければならない。
私はそこではじめて、いままでやっていたことは「勉強」ではなくただの「暗記」だったのだと、知りました。それは、もう3年半も大学に通ったのに、勉強の仕方すら知らなかった自分にに絶望した瞬間でした。
大学院は中退してしまいましたが…院試を受けたから「勉強をする」とはどういうことか、それを知ることができたので、受けてよかったなと思っています。
(※これは大学院進学を推奨する記事ではありません。でも文系の大学院って、いいもんですよ)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
