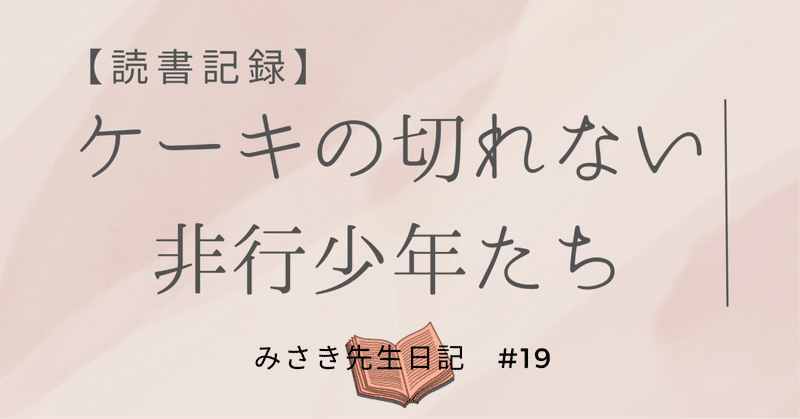
#19【読書記録】ケーキの切れない非行少年たち
こんにちは。
宮口幸治さん著の「ケーキの切れない非行少年たち」を読書記録をシェアします。
衝撃的な内容でした・・・ まさに目から鱗。
なるほど、どうにも手のつけられない「非行」の根底には、早期に手をつけなければならない教育課題があるのか、と。
そして、過ちを振り返らせる(反省させる)という再発防止への指導は、
ある意味で見当違いだったのか、と。
加害者になってしまう少年の多くが、障がいを持っていて認知機能に問題があるということも稀ではないようです。
文字通り、
「ケーキを3等分に切れ(書け)ない非行少年」
の姿から浮かび上がる現在の教育課題に踏み込みます
1. 全体マップ

2.認知機能の欠如 〜反省以前の子どもたち〜

矯正教育として、反省を促すことをしがちですが
実は反省以前に、そもそも認知能力が欠如しており、結果として犯罪に至るケースが多い。
そのような少年は「ケーキを3等分する」といういたってシンプルなタスクができません。また、計算や漢字の書き取りも苦手な傾向があります。
その根底には、認知機能の弱さ(=「見る力」「聞く力」「想像する力」の欠如)が。
筆者がまとめた非行少年の特徴6つは以下の通り。
認知機能の弱さ
融通の効かなさ(思いつきの行動、思い込みの強さ)
感情統制の弱さ(感情の理解と整理の困難)
不適切な自己評価(実情と自尊感情の乖離。他者との適切な関係欠如が起因)
対人スキルの乏しさ(認知機能の欠如により、相手の感情が読めない)
身体的不器用さ ※一部に当てはまる (力加減ができず、じっとできない)
これらの特徴により、
小学2年生頃から、学習について行くことが困難になったり、いじめられたりすることで、「非行」に走ってしまう。
3. 学校教育における現状 〜気づかれない子どもたち〜

現在、知的障がいはIQ70未満を指しますが、
以前(1970年代以前)はIQ85未満でした。なぜなら、多くの人(16%程度)があてはまりすぎてしうから。
それにより、クラスの下から5人は病名のつかない知的障がい者(=境界知能)と言われています。
必要な支援が受けられないまま、他の子どもと同じ教育を受け、見えないところで苦しんでいる。そして、自分も「普通」だと思っているから、声を上げられない。自分がダメなのだと信じてしまう悪循環。
それを防ぐためにどうしたらよいか?
それは、「小学生のうちにサインをキャッチすること」。
何に対して苦手を感じていて、どのようなが必要かを小学生のうちに見極め、支援をすることで、自身も自分の特性を理解することができます。
4. 解決への道筋 〜自己への気づき、自己評価の向上〜

誉めることは解決に導くか、という問いに対する筆者の答えは、「否」です。
では何が解決に導くか。大きく分けて2つあります。
1. 「自己への気づき」
大きな問題となるのは、「実情と自尊感情の乖離」
殺人をした少年に「自分はどんな人か」と問うと、「優しい人です」と答えた
まずは自分が何をしたか、どんな人かをまず理解させる
ありのままの自分を知り、受け入れる
そして、より多くの「気づき」体験を通して、「もっといい自分になりたい」(=自己規範)をもたせる
自己規範にそぐわない行動に不快感が生じ(自覚状態理論)、行動変容の動機づけとなっていく
2. 「自己評価の向上」
学習面、身体面、社会面など支援方法はありますが、
現在の教育で抜け落ちてしまっているのは「社会面」
どのように人間関係を築くか、感情のコントロールの仕方など
認知機能に問題がある個にとっては、当たり前ではないことばかり
だからこそ、友達との価値観の違いを感じながら、学校で教えられる必要がある
そして「勉強がわからない」ことは、非行に走ってしまう理由の一つ。だからこそ学習面の支援は大切。
筆者が少年院で指導する少年たち
初めは、「やっても無駄」と消極的な態度をとりますが、
「先生の代わりに友達に教える」という体験を通して、前のめりになって学習に取り組んだそうです
学ぶことに飢えた彼らも、実は「人の役に立ちたい」のです
このような支援を通して彼らの「できる!」が増え、自己評価が高まっていくことで、救われるべき人たちが犯罪に手を染めることから助けることができる
5. 最後に
教師という立場で読む時、なんともやりきれない思い。
担任する生徒の中にも、境界知能の生徒はきっといるでしょう、顔を思い浮かべながら読みました
私たちを「困らせる」人たちは、実は自身に「困っている」人なのかもしれない
現状の学校は「学習面」でのアプローチがメインだけど、
「認知機能(内向き)」や「社会面(外向き)」へのアプローチは、生きる上で大切なスキルを育てる必要不可欠な教育だと強く感じるきっかけとなりました
反対に、それらなしに行われている日本の教育を不思議に感じたし、そりゃあ「病む」わけだと納得もした。
教師として、なんとか卒業させたい、合格させたい
けれど、根の問題をうやむやにせず、その個に本当に必要な教育をしたい。
そしてその個を10年後、20年後に芯から支える教育をしたい、と思わされました。
6. 教育に携わるすべての人たちへ
3連休ですね。学年末考査前でそれどころではないかもしれませんが(笑)今週もお疲れ様でした!あと少しで年度も終わり。大変なこともきっとたくさんたくさんあったと思いますが、生徒も教師も笑顔で良い締めくくりとなりますように。先生方が蒔かれた言葉や行動の種はいつか必ず芽吹きます!尊い働きに感謝します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
