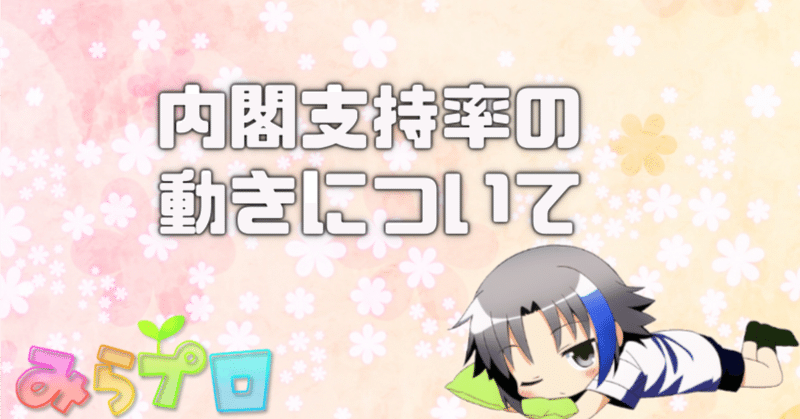
内閣支持率の動きについて
今回は大した話ではありませんが、世論調査の解釈について少し書いてみることにします。
JNNの支持率増加は変なのか?
今月の4~5日に実施されたJNNの世論調査で、内閣支持率が7.0ポイント上昇したという結果が得られました。このことは「明確な理由が見つからない予期せぬ支持率のアップに、与党内からも困惑の声があがっています」(TBS)などと報じられています。
しかし一見して不可解であったとしても、世論調査は科学なのですから、出てきた結果は受け止める必要があります。
この支持率の上昇はどのように説明されるのでしょうか。まず、JNNだけでなく最近の様々な世論調査について、内閣支持率と不支持率、およびそれぞれの増減を見てみましょう。
次の表は下ほど新しい調査となっています。内閣支持率と不支持率の増減の欄に表示したのは、同じ系列の調査の前回との差であることに留意してください。たとえばJNNの5月4~5日の調査の増減の欄に記されているのは、同じJNNの3月30~31日の調査と比べたものにあたります。

首相の訪米より前に行われた世論調査の内閣支持率とその増減を青枠で示しました。当時の内閣支持率がほぼ横ばいか、わずかな低下傾向にあったことが読み取れます。他方で赤枠で示した訪米直後の調査では、内閣支持率は一転して上昇傾向となっています。このことは、訪米が内閣支持率の上昇に寄与したことを示唆しているといえるでしょう。
赤枠よりも下に位置する読売、毎日、朝日、日経、JNNの調査は訪米から1~3週間たった後のもので、効果は薄れているようですが、やはり平均した支持率は上昇となっています。JNNの+7.0ポイントという数字は大きいものの、上昇自体は他の多くの調査でも捉えられていたというわけです。
訪米でなぜ内閣支持率が上がるのかというと、それは外交というポジティブな報道の量が多くなり、首相の露出が増えることが関係しています。政治に対して明確なスタンスを持っている人たちは、単に露出が増えたところで自身の態度は変わらないと思われるかもしれません。しかし支持と不支持の間を揺れ動くのは、その境目にいる態度の曖昧な人たちや関心の低い人たちであり、その人たちの動向こそが主要な増減をもたらすことに注意が必要です。
そうした態度の曖昧な人たちがどれほど調査に反映されるのかということは、各社に固有の傾向があります。
たとえば朝日新聞では、「あなたは、岸田内閣を支持しますか。支持しませんか」と質問し、「支持する」か「支持しない」かを答えさせています。対してJNNは①「非常に支持できる」、②「ある程度支持できる」、③「あまり支持できない」、④「全く支持できない」の4択から選ばせて、①と②の合計を内閣支持率とし、③と④の合計を不支持率とするやり方をとっています。4択だと回答者がいずれかの選択肢を選びやすくなるため、より態度の曖昧な層までが振り分けられることを結果します。実際に最新のJNNの調査について内閣支持率29.8%と不支持率67.9%の合計を求めると97.7%となり、非常に多くが態度を表明したことがわかります。
こうしたことから、JNNの世論調査は態度の曖昧な層を広く捉えており、内閣支持率の動きも不支持率の動きも激しくなりがちだと言うことができます。もっともこれはあくまで統計的な傾向であり、一回一回の調査の結果は、実施された時期が異なることや、避けられない誤差があることから、説明と合わない場合が生じることも少なくありません。しかし以上のような背景から、最新のJNNの結果は特に違和感があるものではないと考えられるのです。
世論調査の個性
先に示した表のうち、内閣支持率が最も高いのは最新のJNNの29.8%で、最も低いのは時事通信の16.6%となっています。この違いが何から生じるのかというと、それは主に日程、誤差、個性の3点によります。
日程は世論調査をいつ実施したのかということです。毎日豊富なニュースがあるので支持率は細かく変化します。特に訪米の前後では大きく変化したはずですが、時事通信の4月の調査は訪米の前のものでした。各社が行う調査はそれぞれ月に一回程度なので、支持率の上昇や下降が起きる前の調査と後の調査が常に混在していることに留意が必要です。
誤差はランダムに調査を掛けたとき、たまたま内閣を支持する人に多く当たってしまうか否かという問題です。この誤差は最大で±3ポイント程度が見込まれるため、同時期の調査でも内閣支持率や不支持率が異なったり、上昇と下落が混在するようなことを結果します。
そして個性は各社の世論調査のやり方によるものです。たとえば多くの調査が電話によって行われるなかで、時事通信は面接を貫いてきました。顔の見えない電話と比べて対面した状況では態度を示さない人が多くなりがちで、最新の4月5~8日の調査でも内閣支持率16.6%と不支持率59.4%の合計は76.0%にとどまります。態度を表明している割合が小さいということは、態度の明確な層が結果に反映されているわけです。内閣支持率16.6%というのは各社の中でも低い数字ですが、それはこうした背景とともに了解されるのです。
日程と誤差の影響は避けられないもので、個性は各社の方針が統一されていないことによっています。様々な個性があると、態度の明確な層から曖昧な層までのあり方を洞察することができるものの、それには丁寧な読み解きが必要となります。口当たりのいい結果のみを正しいと思い込んで他を切り捨ててしまう人をしばしば見かけますが、それは現実と向き合う態度ではありません。
平均でとらえる
他方で、個性を読み解くのではなく、統計的なやり方で打ち消してしまうことも可能です。次の図は、岸田内閣の発足から現在までの内閣支持率と不支持率について、そうした処理をほどこした結果です。表示された点の一つ一つが各社の世論調査で、太い線がその平均です。

平均においても訪米による内閣支持率の上昇が確認されることがわかります。けれどもその上昇の幅はそれほど大きくはありません。一年前には広島サミットに前後して内閣支持率と不支持率が逆転するほどとなりましたが、現在はそうした局面にはないわけです。
また次のような点からも考えてみましょう。まず、内閣支持率をそのままにして、不支持率の上下をひっくり返してしまいます。次のグラフは、内閣支持率は左の赤い軸の、不支持率は右の青い軸の目盛りで見てください。

さらに不支持率を上に平行移動すると、岸田内閣発足時の内閣支持率と不支持率を重ねることができます。

このようにすると、内閣支持率と不支持率の線は似た動きをしながらも、両者の差が徐々に開いていることがわかります。つまり内閣支持率の低下よりも不支持率の上昇の方が大きく、一度増加した不支持層は簡単には減らないということがいえるのです。これは、一年たてば内閣支持率の持ち直しがそれだけ難しくなることを意味します。今後の日程ではしばらく外交や定額減税などが続き、支持率は回復の局面となる可能性があるものの、その効果は限定的となるのではないでしょうか。
また、世論調査が発表されるとどうしても直近の増減が目を引きがちになりますが、次期衆院選に対する影響は、前回衆院選からの増減で見る必要があることも重要です。

今回はJNNの結果を題材として、世論調査の個性の話と、長い目で見た平均の動きに焦点を当てました。世界でも国内でも論じるべき重大なことが多い中でささいな話ではありますが、ぼくはこんなところで定点観測を支えていくつもりです。
P.S.
昨年から「世論の動向」や各種SNSに比例投票先の平均を掲載していますが、期間が直近1年程度にとどまっており、前回衆院選の時点が含まれていませんでした。そこで近いうちにこの期間を5年程度まで拡大する対応を行います。さらに各政党の支持率と比例投票先を同一のグラフに表示して、より深い考察ができるようにしたいと考えています。成果はひとまず「みちしるべ」に投下するつもりです。
2024.05.10 みはる
