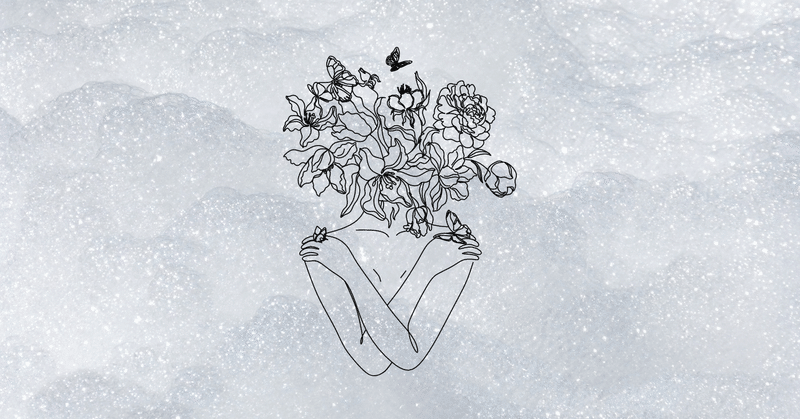
Movie 9 美しさの大きすぎる代償『世界で一番美しい少年(The Most Beautiful Boy in the World)』
なんとも重苦しい、心に何かがつっかえるような映画だった。
『世界で一番美しい少年』(2021年)。
前宣伝を観て「これは絶対観る!」と思っていたが、映画館に観に行けなかったので配信を心待ちにしていた。が、いつの間にかすでに配信されていた。気づかなかった。
先日やっと観ることができた。
ふとこの映画のことを思い出したのは、エブエブを観て同じA24の映画『ミッドサマー』を思い出したから。
『ミッドサマー』についてはkoedananafusiさんが、ドキドキする感想を書いていらっしゃる。
『ミッドサマー』には、北欧のあるコミュニティ(架空)が登場する。
そのコミュニティでは75歳になると自ら崖から飛び降りて人生の幕を閉じるという風習があり、身を投げる老人役で出演していたのが、映画『ベニスに死す』で「世界で一番美しい美しい少年」と言われたビョルン・アンドレセンだった。

さて、『世界で一番美しい少年』、観てよかった。
配信はユーネクストで6月まで。危ない危ない。もう少しで見逃すところだった。
(いつものようにネタバレだらけになります。これ以上のネタバレをご希望でない方は、ここまでで)。
映像も創りも純然たるドキュメンタリーなのに、不思議なほど現実感がなく、奇妙な浮遊感がある映画だった。アンドレセンはただ日常を暮らしているのに、まるで演技された映画のように見えることが多かった。本当の彼は、どこにいるんだろう、と思った。まるで他人の人生を生きているような風情なのだ。
15歳で当時巨匠と呼ばれたルキノ・ヴィスコンティ監督に見いだされ、映画『ベニスに死す』に出演したことがきっかけで、「美少年」として名を馳せたアンドレセン。
ヴィスコンティはゲイとしても知られ、この映画に出たことでアイドルという肩書だけではなく、ゲイ・コミュニティのアイコン的存在になってしまったアンドレセンは、結婚するも破綻し、その後音楽家として身を立てながら世捨て人のような暮らしを送ることになる。
映画はアンドレセンが暗く長い廊下を歩いていく場面から始まる。
次のシーンは、信じられないほどきったない汚部屋で、彼が賃貸の部屋を退去させられそうになる場面だ。法的にどうすればいいかわからないから、助けてほしいと役所(か弁護士)に電話している。現在、彼はストックホルムに住んでいるようだが、スウェーデンではそういった福祉が充実しているらしい。
退去勧告の理由は「コンロのつけっぱなし」や「不潔で衛生上問題がある」など。
常にコンロをつけっぱなしにしているらしい。危ないからというのが大家の言い分だ。大家さんの言うことは、至極当たり前のことに思える。わざとコンロをつけっぱなしで寝たり、出かけたりと言うのは結構正気の沙汰ではない。
で、次のシーンは、部屋を片付けに来た「恋人」だ。このあたりはどうも解せなかった。恋人がいたのに、家に一歩も入れたことがないのだろうか。
彼女は元の色がわからないような寝具や、持ったら崩れ落ちるマットに「汚すぎて吐きそう」といいながら10日間もかかって片付けと掃除をして、部屋を綺麗にした。そのうえで、自分がついているから賃貸契約を継続してくれと大家に掛け合う。アンドレセン自身はコンロつけっぱなしも認めているし、それには理由があるということをブツブツつぶやくが、恋人は不利にならないように必死にフォロー。賃貸契約は守られ、その後も恋人のおかげか撮影のおかげか汚部屋に戻ることはなく、ドキュメンタリーは進む。
推察に過ぎないが、恋人を部屋に入れたのは、おそらくはこのドキュメンタリーを撮ることになったのがきっかけなのではないかと思う。ひょっとしたら、ドキュメンタリーを撮ることになって知り合った人と付き合い始めたのではないかとすら思う。真実はわからないが、それ以前何年も部屋には誰も訪ねてこなかったと後で本人が述懐している。恋人とは後に、彼の秘密主義が原因で別れ話になっている。他人に心を開けないのだ(恋人は彼がオートロックの暗証番号を教えてくれないというので彼を口汚く罵っていた)。
そもそも、このドキュメンタリーを撮ることになるまでも、監督やプロデューサーなどが3年ほどかかって説得したらしい。姿をくらまし、死亡説まで流れていたようだ。
ついにドキュメンタリーへの出演を決断した彼は、部屋をきれいにし、これまで縁のあった土地(日本・フランス・イタリア)を旅したり、10年も会っていなかった娘を部屋に呼んだりしている。その過程で、これまで目を背けてきた母の消息を追い、残酷な真実を知ることになる。
この映画が公開される前、いくつかのブログやネットニュースで「周囲の大人たちに性的に搾取されていたことが映画によって明らかになった」ということが話題になっていた。
そんな前知識はあったのだが、実際に映画を観て、彼が「消費」され「玩具」にされ「食い物」にされてしまうより前に、実の母親のことで苦しんでいた姿が浮き彫りになり、そのことに胸が痛んだ。そのうえ、結婚してからの子供にまつわる悲劇にも、愕然とした。
彼は健やかに成長し大人になりきることができなかった。本人がそう述懐していた。幼少期から長い間、たくさんの身近な人々に傷つけられ、傷つきすぎたのだと思う。
私は、彼が『ベニスに死す』の狂乱のさなかにいた時期を知らない。そのころは幼児だった。大人になってから、トーマス・マンの原作を読み、映画も有名な作品だということで『ベニスに死す』を観た。
正直、本も映画も微妙に居心地が悪かった。
ギリシャ古典をこれでもかと引用した文章もすっきりとは入ってこなかったし、老作家(といっても50がらみのオッサン。モデルのひとりが作者の友人でもあったマーラーらしいので映画では作家から音楽家に変更されていて、マーラーの「アダージェット」が印象的に使われている)の少年への執着が薄気味悪いと感じてしまったのだ。しかもこのオッサンはほぼストーカーになったあげく、自分の恋心のために疫病(コレラ)の情報を少年の家族に知らせない決心なんかをしている。ヤバい。そして彼は疫病で死ぬ。うっとり少年を見ながら死ぬ。世界は巨匠の死に畏敬の念を抱いたというラストシーンだが、実際はオッサンは自分の欲望のために他人を犠牲にしようとしたんである。ひどい。トニオ・クレーゲルのほうがよっぽど面白い、と当時は思った。
この物語の「美少年」を演じたアンドレセンは確かに非日常的な美しさで、カリスマがあり、見る人を虜にしてしまう魅力を持っている。
しかし彼の身に起きたことは、その代償としてはあまりにも大きすぎるのではないか、と思った。それは映画の成功によって華々しいスポットライトを浴び、頂点からの転落人生といったような単純な代償ではなく、彼の出生から今までの人生全般に付きまとう「裏切りと絶望」という代償だ。
1971年に来日したのは、『ベニスに死す』公開後の日本で彼の人気が過熱していたからだ。16歳になったときに「少年の美しさは消えた。もう価値がない」とヴィスコンティにこき下ろされ、映画界ではなくゲイコミュニティーに送り込まれたアンドレセンは、ステージババの祖母とエージェントによって荒稼ぎをすべく日本に送り込まれた。
日本滞在のときの思い出を語るインタビューでは、当時の日本でのマネージャーだった人と酒井政利さん、漫画家の池田理代子さんなどが出演していたが、皆一様に「当時から、きれいなだけではない魅力、影を背負った魅力に気づいていた」と主張していた。それを聞く彼の眼は虚ろで静かだった。
アンドレセンは、CM撮り、日本語での歌謡曲の発売など、本人の承諾はおろか、ほとんどろくな説明もなく連日ハードスケジュールを強要されていたらしい。追っかけのファンがハサミを持っていて髪を切ろうとしたなどは序の口で、なんと薬まで飲まされていたという。昔、『フィンガーファイブ』のアキラさんが声変わりしないようにマネージャーに女性ホルモンを打たれそうになったというエピソードを聞いたことがあるが、さもありなんという話だ。
アンドレセンはでも、日本が好きだったようだ。貴族の末裔でゲイのヴィスコンティにされたルッキズムと差別に裏打ちされた仕打ちより、自分をギリシャの神のように崇めてくる平らな顔族は、よっぽどましだったのかもしれない。
映画を観ていると、彼があまりにも自己主張をしないことに驚く。嫌だと言わない。嫌だと言えないのではないかと思った。ヴィスコンティのオーディションを受けたのも「自分は興味がなかったのに祖母が熱望したから」と言い、人生のあらゆる場面で「誰かの望み」に応えることにあまりにもなじみ過ぎた姿が浮かび上がる。
冒頭、『ベニスに死す』のオーディションのシーンが出てくるが、ヴィスコンティは彼にいきなり「服を脱げ」と言う。最初は「半裸」を要求し、結局は下着一枚にさせた。しかもそれを映像に残している。現代では考えられないし、そういうオーディションなら事前に本人と保護者の同意があってしかるべきだが、なんの予告もなくいきなり「脱げ」とは、当時であったとしても常識的ではない。貴族出身の巨匠はそれだけ傲慢だったのだろう。その後も、言葉がわからないアンドレセンになんら気を遣うこともなく、道具やアクセサリーのように扱う振る舞いが随所にみられた。
あらゆる場面で、アンドレセンはいつも静かにたたずんでいることが多く、多くを語らない。当時の無知な自分に、今の自分ならアドバイスできることは沢山あるとアンドレセンは言う。でも未成年の少年を守ってあげるべきは周囲の大人だ。彼はあまりに家庭や家族、周囲に恵まれなかった。彼は嫌でも嫌だということもできず、そうしていいのだということも知らず、訳が分からぬまま唯々諾々と従ってしまったのだろうが、映画を観てそのベースは幼少期の家庭の中にすでにあったのだとわかった。無知だけではない、精神的なものが見え隠れしている。
彼は娘が生まれたとき「世界一醜い娘」とアルバムに記した。
彼にとって「美しさ」はあまりにも逆説的な価値となってしまった。「美しい」ということを、どれほど憎んだのだろう。世を捨てたように引きこもっていた、誰も訪ねてこない壮絶に汚い部屋は、彼の価値観そのものを象徴していたのかもしれない。
映画を観終わった時はため息が出た。萩尾望都の『残酷な神が支配する』を思い出した。成長期にあまりにアンビバレントな価値を植え付けられることは、その人の健やかさを蝕む。
それでも、彼がどれほど「醜く」なろうとしても、ガリガリに痩せた身体や、皺だらけの皮膚や、髪や髭を伸ばし放題の姿を人前にさらしても、チェーンスモーカーでも、コンロをつけっぱなしにしても、害虫が湧き出るような部屋に住んでいても、その立ち姿に、煙草を吸う手の美しさにハッと目を奪われてしまう。
現在の仙人然とした姿に「ひどい、幻滅した」というコメントも見かけたが、私はかつての「美少年」だけでなく、今の彼が美しいと思ってしまった。傷ついた心のままいびつに成長してしまい、美しさへの執着がないことそのものが、なぜか彼の美しさを引き立てる。皮肉なことに、タナトスと退廃に結びつく美しさは、なお、増すばかりなのだ。
そこを見抜ききったヴィスコンティは、やはり映画監督として、いけすかないが貴族の末裔として、鋭い慧眼と美意識があったのかもしれないと思う。
草の上に寝転んで宇宙を見ているつもりが
実のところ
下界を観察していると想像したことは?
畏怖すべき感覚だ。
星を見上げるときどの方向を見ているのか
外側を見ているのか内側か
上を見ているのか下か
彼には常に現実と乖離した
浮遊感がある気がする
人生にはあまり期待しない
うまく表現できないが多くを失い過ぎると――
不思議なことにむしろ
生きるのが楽になることがある
”あれもこれも失ったが別にいいさ”
”ほかにも失ってる”と
彼の母親は詩人だった。自由を愛する奔放な性格で、アンドレセンを未婚のまま出産した。父親のことは語らずに亡くなったため、誰かはいまだに誰もわからない。当時の8ミリカメラで撮った母の映像がいくつも残っている。アンドレセンはそれを大切にしている。
彼の母は亡くなる時、一編の詩を残した。
ラストシーンに重なるその詩が、何とも言えない余韻を残す。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

