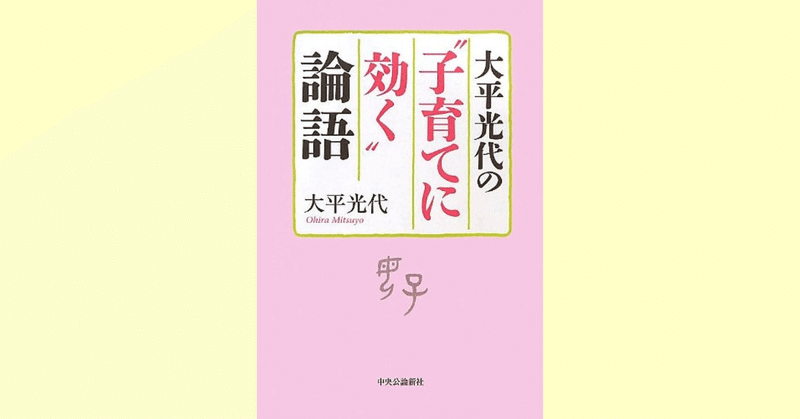
本「”子育てに効く”論語」
読んだきっかけ
僕は、論語という本は元々読んだことがありました。読んだきっかけは、よりよい人生を生きる方法を学ぼうと思ったからです。論語は、自分軸がぶれたときに、自分はどうしたいのか・どう生きていきたいのかを思い出させてくれます。
そんな僕にとっての論語ですが、親・子育ての視点から見ることで、新しい発見があると考えました。僕は、パパにはなっていませんが、これから子に関わる際に、大いに役立つと思います。
この本を読むオススメの人
論語に興味がある
論語を別な視点で読みたい
子育てに自信がない
自分の子育てに不安がある
気づいたこと
「うちの子私が言う事聞かないの」の解決策
例えば、宿題をしない・静かにしてくれない・ご飯を食べてくれないという悩みがあると思います。しかし、なぜできないのでしょうか。
著者曰く、「子は教えられていないことはできない」と書かれています。また、論語にはこうあります。
教えずして殺す、これを虐という。
そんなの知っている。なぜなら、大人より子は経験が少ないから、教えられていないことはできないなんて当たり前、と思われる方がいるでしょう。しかし、真にその意味を僕たちは理解できているのでしょうか。つまり、教えられたことはできているということだと僕は考えます。
上記の場合であれば、
「宿題しなさい!」▶子)宿題をやらされて苦痛だ▶やりたくない
「静かにしなさい!」▶子)パパママも大きな声を出している▶大きな声を出していいんだよね
「ご飯を食べなさい!」▶子)なぜ食べなきゃいけないか分からない▶食べない
親が言うように子が動けば、苦労なんかありません。そして、親子とはいえ、一心同体ではないので、親が言うことの背景が伝わることはありません。親の立場が子に対してできることは、親が言う事の背景を子が分かりやすいように伝えることだと気が付きました。
例えば、勉強嫌いの子がいたら、子が興味あることをとことん調べられるよう環境を整えて、学ぶことは面白いと感じさせてみる。静かにしてほしいなら、自分が大きな声を出していないか内省してみて、子に対する伝え方を工夫してみる。ご飯を食べてくれないなら、憧れの人の食事方法や・ご飯を食べることでどんな効果があるのかを、一緒に調べてみることができると思います。そうやって、近くにいる親から得た知恵が活きて、言わなくても自分でできるようになる子に成長するのだろうと、気付かされました。
「自分で決められる子に育ってほしい」の解決策
先日テレビを見ていた時、小学3〜4年生の子とパパがインタビューを受けている場面を見ました。すると、そのパパは子に対して向けられたマイクに、全部代弁して答えていたのです。
僕が、本を読んで気づいたことは、「親が子の声に耳を傾け、親も声を伝える」ことが大切だということです。なぜなら、親主導ばかりで決めると、周囲の意見に流される子・誰かが決めたことだから自分は関係ないと無責任な子になってしまう可能性があるからです。
論語にはこうあります。
和して同ぜず。
(仲良くしても、簡単に同調しない)
親子であっても、考え方は別です。小さい子でも、子なりに感じていることはあります。なので、子の声を聞き続けることは、自分の気持ちが受け入れられたということになるので、自分の軸ができあがるきっかけになります。また、自分の気持ちを伝えることは、エネルギーを使うことなので、安易なことを言えないことから、責任感が生まれるきっかけにもなると考えます。なので、自分で決められる子に育ってほしいなら、子自身の気持ちを外に出すということが大事だと気付きました。
「間違いを認められる子になってほしい」の解決策
これについては、親が自身が”内省”について、子に教えることが大事と気づきました。論語では、こうあります。
己の知ることなきをうれえず、知られべきことを為すを求む。
(自分を理解されなくても落ち込まず、自分が知るべきことを知る)
例えば、子が友達と喧嘩して、仲が悪くなったとします。そして、多くの子は「自分は悪くない」と言います。これは、自己評価が高い状態です。僕はこのことについては、人間らしい考え方だと思います。なぜなら、自分を守るための自然な反応だからと考えているからです。しかし、仲が悪くなったのは、本当に自分は悪くないのでしょうか?なぜなら、相手が言うことを気にない・受け流す・事前に仲が悪くならないよう手を打つことをすれば、仲が悪くなることはなかったはずです。だから、内省が大事なのです。
親ができることは、もし自分が悪いとしたら、どんなことをしてしまったのかを考えさせる。なぜなら、仲が悪くなったのは〜だからじゃないの?〜じゃないの?と問い詰めると、「その場にいないのに何がわかるんだ」と思われがちだからです。きっかけを与えれば、自分で答えを出します。なので、信じるということも親ができることだと考えます。このような訓練を重ねることで、自分の間違いを認めることができるようになると気が付きました。

僕ならこうする
子の傍で本を読む
僕も、勉強しなさいと言われつづけていました。チャレンジ◯年生という学習教材を、付録だけ楽しんで他は捨てていた1人です。今思い出すと、学生時代家で勉強することは嫌でした。なぜなら、親が勉強していないのに勉強することを強制させられることが嫌だったことと、勉強してもその姿を見てくれなかったからです。その結果、ひねくれ少年が出来上がってしまったのですね。
著者は、子が勉強嫌いになる理由についてこう述べています。
強要される
勉強して分からないことが解消されない
なので、僕が親になったら、子の傍で本を読みます。自分が学ぶ姿勢を見せることで、家でも学習する環境を整わせます。
子の心の声に耳を傾ける
僕が中学1年生の時の誕生日の思い出です。僕は、誕生日プレゼントを買ってもらうために、お婆ちゃんとイオンにきていました。僕が欲しいのは、プレイステーション3。高いので簡単に欲しいとは言い出せません。でも、やっぱり欲しいので、ゲームだけじゃなくDVDも見れる、友達を家に呼んで遊べる等、自分の欲しい思いが詰まったプレゼンをしました。すると、お婆ちゃんは「じゃあ買ってあげるわ」と、プレイステーション3を買ってくれたのです。
あの時、僕はプレイステーション3を買ってもらったことより、自分に正直になれたことが嬉しかったことをよく覚えています。具体的には、欲しいって言えた。魅力を伝えられた。なんとなくではなく、欲しい理由を説明できた。そして、少し厳しいお婆ちゃんに話を聞いてもらえた。僕はそんな思い出の詰まったプレイステーション3で未だに遊んでいます。そして、それが最初で最後のお婆ちゃんからのプレゼントだったのです。
デパートやアーケードを歩くと、「ダメ、行きません、買いません、置いていくよ」と端的なやり取りの親子の会話が耳に入ります。僕が親になったら、良いことでも・今はできないことでも必ず子の話に耳を傾け、僕の気持ちも伝えていきたいです。
内省のきっかけを与える
僕は、親が口出ししないほうが良いときがあると考えます。勿論、子が壁を乗り越えられないときに、手助けをしたりアドバイスをすることは、正しいと思います。しかし、度を過ぎればおせっかいになり、その場にいないのに何がわかるっていうんだ!と思われてしまうかもしれません。
僕が親になったら、内省をさせるきっかけを与える存在になりたいです。例えば喧嘩を解決したいと、子が願う場合のこと。あえて「仲直りの方法を知っているから、知りたくなったらおいで」と伝える。そうすれば、最初は怒りで相手の嫌なところしか見えなくても、怒りが冷めて、この状況をどうにかしたいと思った時に、親が手助けできる。つまり、子が能動的に解決したい姿勢になった時に、タイミングよく親が登場できるのです。1つ種を落として、目を出した時に水を与えるということが、理想であると考えました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
