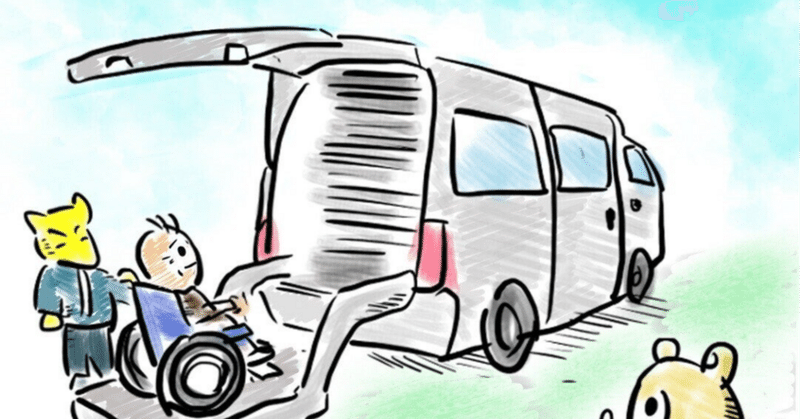
ケアは無償の愛の労働ではない
狭義のケアというと、介護を思い浮かべるかもしれないけど、家事労働も、子育てもケアだとおもう。そしてケアは一方通行のように思われるけど、実のところは、みな誰かに依存して生きているのだから、相互関係にあると考えた方が良い。
この家族内ケア労働には、通常対価が支払われない。おそらく、ケアとは無償の愛、見返りを求めない「愛の労働」によって行われていることが期待されているからだ。
このような家庭内ケア労働は、通常、女性によって行われることが期待されている。しかしこれは歴史的には産業革命以降、労働の場と、家事の場が別けられていこうの習慣で、それ以前は、男女で分担して行われていた。
結果的に分離したのは、道徳に対する価値観が男女で違い、女性はケアの倫理を意識して、責任感から自ら受け入れないと行けないと思ってしまうからでもある。(男性はそれに甘んじてる。くいぶちを持ってくることだけが自分の責任と捉えてるのかもしれない)。
考えられる理由として、それは子育て(本来なら出産でないのだから男性でもできる)が出産との連続で女性がやるものと男女とも決めつけているからでもある。
このような無償労働を有償化が進みつつあり、農林水産省は「家族経営協定」の締結を推進している。実際ボローニャ市では、主婦にたいして賃金が支払われていた時期があるらしい。同時に、家庭内ケア労働における傷害に、なんらかの社会保険が支払われる仕組みも重要だ。
もう一方は、無償労働の社会化だ、家族内ケア労働を社会全体で負担していこうという仕組みだ。介護ヘルパーさんや、介護士さん、保育士さんのケア労働には対価が支払われる。障害介護や、介護保険による居宅介護、施設介護は、社会の支え合いと本人の蓄積によって、対価が払われている。しかし、その費用は低く、保育士や介護士さんの定着率の低さは問題視されていて、改善が必要だ。
毎週通ってきてくれる介護ヘルパーさんは、拡大家族のひとりのようなもので、本当にケアが必要な人達には助かる存在である。
問題は、これらを解決したところで、ケア労働の対価が男性の給与水準と同等にするには、相当の社会保険料の負担が必要で、100%社会化されたケア労働の社会保障で充当するのは、難しい。やはりある程度の家庭内ケア労働も必要であろう。高齢者や障害者介護については制度ができているが、たとえば学童保育を超えた後の子どもの家庭内ケアなど、共働きの場合、空白になる可能性がある。
そのためには、やはり男性の家庭内ケア労働への積極的な参加が必要だ。しかし男性の現在の感覚は、女性が「愛の労働」として「すすんで」請け負っていると考えており、そのために男性の賃金を「愛情深く」提供していると考えている人が多い
女性がそのことに異論をのべた瞬間、男性は「愛の契約」が打ち切られたと考え、愛に報いないと暴力を振るう。男性は「働かない」から暴力を振るうのではなく、「彼を十分に愛してないから」と言う理由で暴力を振るうのだ。
この男女の傾斜は、所得格差にあることに理由があるのが明確だ。女性にしかるべく収入を与えるには、責任のある立場まで上がっていく必要がある。そのことで夫婦の収入格差がなくなる。しかし家庭内ケア労働の時間は、どちらもなくなる。
企業は、管理職であっても男女とも家庭内ケア労働に従事する時間を応分にあたえると同時に、ケア労働を積極的に社会化(アウトソーシング)することだ。ケア労働を他人にまかせることを恥と思う、差別する空気をけすべきだ。
そもそもこの考察には、家庭内と言う言葉を使う以上、そもそも家族とはなんなのかの考察が必要だとおもう。この論考はまた別の機会にしたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
