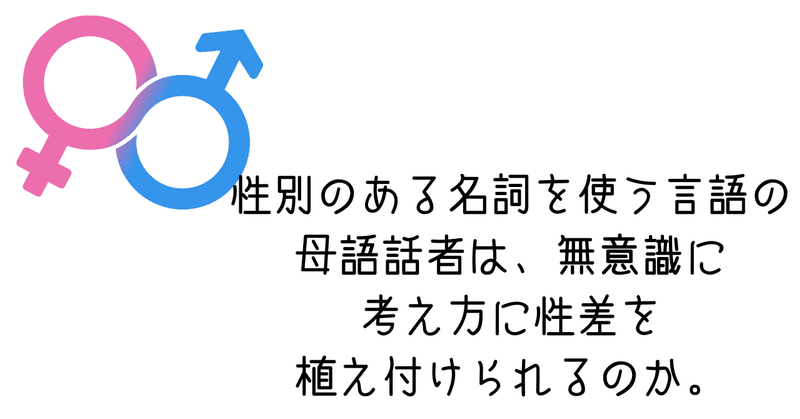
性別のある名詞を使う言語の母語話者は、無意識に考え方に性差を植え付けられるのか。
以前のわたしのイタリア語の先生との授業で、教科書の章が男女の社会的権利が同等でない問題を扱っていたから、「イタリア語は単語に男性女性がある言葉だが、そのシステムが言語使用者の意識に男女差別について影響するか?」ってなことを先生から聞かれたことがある。
これ、はっきり言って、わたしにはわかりません。イタリア語が母語じゃないし。母語の人の脳内で男性名詞女性名詞に関する概念がどうなってるか、同じ立場で考えられない。
かなり昔の話だが、アメリカでは、職業での女性差別を避けるため、たとえば、わたしが昔学校でならった、Fireman(消防士)、Policeman(警察官)などの単語は、MANで終わるから、これ、男基準でしょ💢ってことで、Fireman→Firefighter Policeman→Police officerと呼ぶようになった。極端な例ではhistoryという単語は、His storyということで、歴史を作ったのは男だけかい!と怒ったフェミニストたちがherstoryという言葉を作ったとか・・・それは行き過ぎって気はするが(笑)。
とにかく。
日本でも、昔は「看護婦」と呼んでいたがそれが「看護士」に、そして「スチュワーデス」が「フライトアテンダント」なんかに変わっている。日本の場合は名詞にそもそも性差はないが、「看護婦」といえば女性だとわかるし。まあ、「看護婦」という単語の場合は、なんとなく「医者」は男性で、そのアシストをする「看護婦」は女性、という構図が描かれていた時代にできた言葉なんだな、というのは、わかる。
しかし、イタリア語に関していえば、単語の性差が、「それ、いかにも男だわ」「たしかに女性っぽいよね」みたいなルールはまかり通らない気がする。
たしかに、「女性」を意味する donnaという単語は女性名詞だし、「男性」を意味するuomoは男性名詞だ。しかし、「海」のmareは男性名詞。でも海の概念って女性が多い気がする。ナイフは男性、フォークは女性、スプーンは男性、本は男性、鉛筆は女性。
だから、こういった性差が意識の深いところに根付くかといえば、って気がする。
それよりは日本語の看護婦的に、「市長」「弁護士」なんかの肩書のある名詞がそもそも男性名詞だったり、「看護士」が女性名詞だったりする方が意識に影響与えるんでは?と思う。
男性名詞女性名詞って話ではないけれど、現在わたしが日本語教師になるべく受けているコースで、先日教育実習をしたとき。わたしは「います」「あります」という、人、動物、物の存在を言えるようになる、という課題の授業だったのだが、日本人なので意識してなかったが、これ、たぶん外国人の日本語学習者にはちょっとめんどいとこなのかも。
人→います
動物→います
物→あります
ということろは、まあ、いい。生きてるものは「います」だし、物は「あります」。
しかし、曲者なのが、これが疑問文で「何が」「誰が」を使う場合だ。
人→誰がいますか
動物→何がいますか
物→何がありますか
お。ここで動物が微妙。人も動物も「います」を使うのだが、人は「誰」。しかし、動物と物は「何」なのだ!動物は、人と物の間に位置するのかな・・・こういった使い方は、動物は人よりも下だ、という概念植え付ける原因にならないのかな・・・とぼんやり思った。
言葉とは、本当に奥が深いもんだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
