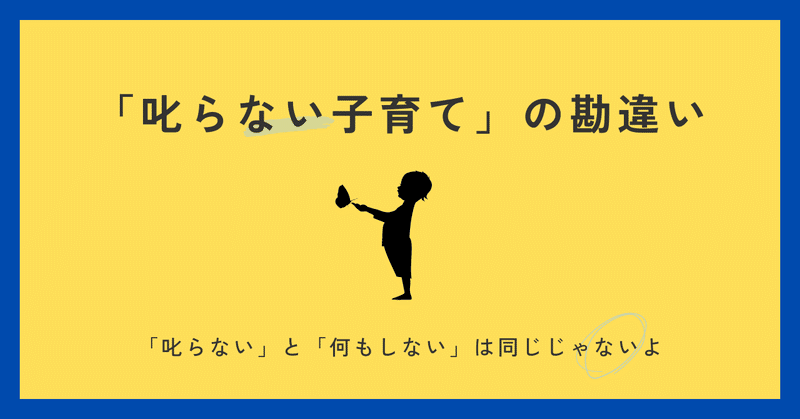
「叱らない子育て」の勘違い【子育てナッジ】
「叱らない子育て」という流行

「叱らない子育て」という言葉が数年前に流行しました。メディアの浅い情報が垂れ流されたことで、迷える親御さんたちは額面通り「叱らない方が良い」という事象のみを切り取ってしまいました。そしていつしか「叱らない子育て」から「何も伝えられない子育て」へと変わってしまいました。
「叱らない子育て」とは?
①不適切な行動ではなく、適切な行動に着目する
②叱るのではなく、共感しながら伝える
③子供の未来を心から願う
①不適切な行動ではなく、適切な行動に着目する

教員であれ親であれ、私たち大人はどうしても子供の「良くない行動」に注目してしまいがちです。反対に「良い行動」は、できるようになると徐々に当たり前となり、声をかけられなくなってしまいます。「できて当然」という評価が下されるからです。結果、普段の生活の中で「叱りの言葉が8割、承認の言葉が2割」という事態に陥ってしまいます。
学級崩壊が起こるクラスも、この現象が起きていることが多いです。良い行いをしている子供たちが置き去りになり、悪い行いをする子供の一挙手一投足に注意を促します。不適切な行動をとるほうが、注目されるクラスの出来上がりです。
「叱らない子育て」は、
「承認が8割、譲れない部分は真剣に想いを伝えるが2割」になります。
②叱るのではなく、共感しながら伝える

先ほど述べた「譲れない部分は真剣に想いを伝える」の部分になります。
叱るよりも伝える というニュアンスが近いと考えています。
「叱る」とは、
相手の非を指摘、説明し、きびしく注意を与える行為と言われています。
私の考える「真剣に想いを伝える」は、
心から相手の幸せを想い、伝えるべきことを伝える行為を指します。
感情任せに言うわけでもなく、厳しく非難するわけでもなく、まっすぐな目で、まっすぐな言葉で真摯に伝えます。
「そうか。◯◯な気持ちだったんだね」
→共感
「もし、あなたに天使と悪魔がいたとして、天使のあなたならどうしてた?」
→例え
「うんうん、そっか。本当は◯◯した方がよかったと思っているんだね。
私もそう思う。いつかその天使が出せたらいいね」
→真剣に伝える
③子供の未来を心から願う

基本的に教師も親も「なるべくガミガミ言わず、誉めたい」と思っています。しかし、心に余裕が無くなったり、疲れていたりすると、そう上手くはいかなくなるものです。そんな時「子供の未来を心から願う」ことができているか否かで、大人の言動は大きく変化します。いわゆる「最上位の目標」を常に意識できているかが鍵となります。目の前の子供の言動に一喜一憂するのではなく、子供の未来を長い目で見ることができると、声かけの言葉や姿勢をブレずに保ちやすくなります。
「叱らない子育て」は可能
自身の感情や気分を常に安定させ続けることは至難の業です。だからこそ、世には体系化された「子育て技術」があります。
「迷った時は◯◯する!」と、対応を決め打ちしておくことも「叱らない子育て」のポイントになります。
後日、叱らない子育てのメリットやデメリットも記事にしていきたいと思います。
「叱らない子育て」は
感情や感覚、知識だけに頼らないことが重要
お読みいただき、ありがとうございました。
そうじナッジ↓(これで掃除指導の悩みから救われました)
あいさつナッジ↓(ナッジの中で一番簡単かつ楽しいです)
サポートナッジ↓(課題のある子が自ら変わる、画期的なナッジです)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
