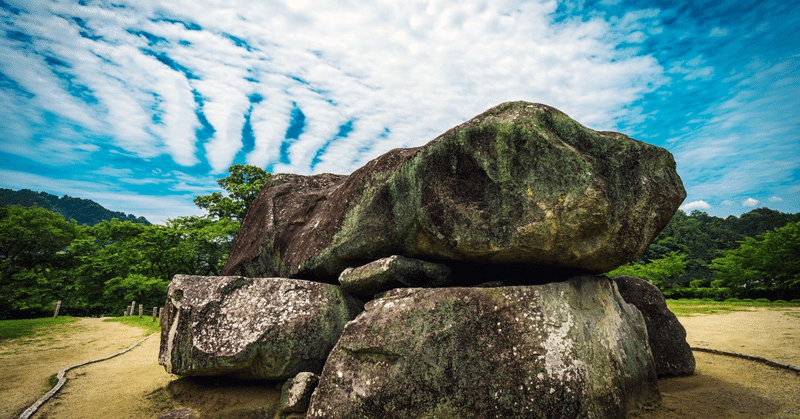
蘇我氏と物部氏も、長髄彦の系譜に繋がるのか。スサノオの「八雲立つ 出雲」の歌の謎。
今回は、須佐之男(スサノオ)が詠んだとされている、「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を」の歌の中の「妻籠みに」について考えていきたいと思います。
学研全訳古語辞典
つま-ごみ 【妻籠み】
名詞
妻を住まわせること。一説に、夫婦が一緒に住むこと。「つまごめ」とも。
「籠」という字には、様々な意味が込められているのだと感じます。
妻を籠らせる(こもらせる)とは、何を意味しているのでしょうか。
須佐之男の妻とは、櫛名田比売(くしなだひめ)または稲田姫(いなだひめ)であるとされています。
徐福は「ホアカリ」「ニギハヤヒ」を名乗っていたが、記紀では「スサノオ」と記された。
ヤマト王朝の初代大王であるアメノムラクモ(天村雲)は、徐福(スサノオ)の血を受け継いでいることになる。
神武天皇は創作された人物で、神武東征は、徐福の一団の物部が筑紫から奈良へ2度、東征したことを指す。
上記のように、須佐之男(スサノオ)とは火明(ホアカリ)であり、饒速日(ニギハヤヒ)であり、徐福であると考えられます。
そして火明(ホアカリ)とは籠神社の祭神であり、倭宿禰(やまとすくね)のことであると考えられます。
丹後半島の籠神社(このじんじゃ)には「別名・珍彦・椎根津彦・神知津彦 籠宮主祭神天孫彦火明命第四代 海部宮司家四代目の祖 神武東征の途次、明石海峡(速吸門)に亀に乗って現れ、神武天皇を先導して浪速、河内、大和へと進み、幾多の献策に依り大和建国の第一の功労者として、神武天皇から倭宿禰(やまとすくね)の称号を賜る。外に大倭国造、倭直とも云う。」とあり、境内には亀の背に乗った倭宿禰の像がある。
須佐之男でもある倭宿禰は、「井光(いひか)」を娶ったということです。
海部氏の倭宿禰は、神武が大和王権を樹立した時、大和に赴き神宝を献じて神武に仕えたとする。その大和に居たとき娶ったのが、白雲別の娘、豊水富(とよ みずほ)または豊御富(とよみほ)である。そして『勘注系図』の注記は、豊水富の亦の名を井比鹿(いひか)とする。これは『日本書紀』神武記で、神武が吉野で名を問 うた時答えた「井光(いひか)」と同じである。
井光とは、水光姫(みひかひめ)とも呼ばれています。
鎮座地は竹内街道、長尾街道、横大路が交差する交通の要衝であり、古来より交通安全、旅行安全の神として篤く信仰されている。参道は拝殿に向かって東西に長く伸びており一の鳥居は近年新たに竣工した。 二の鳥居の両脇には「なで蛙」が配されて、参拝者を見守っており、安産祈願の神としても名高い。 また水光姫命は古事記や日本書紀に体が光って尾が生じていたと記されており、神様の化身が白蛇であると言われるところから蛇の頭が大神神社で尾が長尾神社という伝承がある。
井光である水光姫の化身とは、白蛇であったということです。
つまり井光を妻とした倭宿禰とは須佐之男であり、須佐之男の妻とは、白蛇であることが暗喩されているのだと考えられます。
ここでもう一度、須佐之男が詠んだとされている歌を見てみます。
「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を」
「八雲」とは須佐之男のことである、と前回の記事で考察しました。
「出雲」とは地名でしょうか。
島根県松江市にある八重垣神社によりますと、「八重垣」とは八つの垣根のことで、「妻籠みに」とは稲田姫を八岐大蛇から救うために隠した、ということのようです。
境内奥地の佐久佐女の森は、素盞嗚尊が八岐大蛇を御退治になる際、稲田姫を難からお救いになった場所です。森の大杉の周囲に「八重垣」を造り、稲田姫をお隠しになりました。「八重垣」とは、稲田姫命をお守りした八つの垣根で、大垣、中垣、万垣、西垣、万定垣、北垣、袖垣、秘弥垣と呼ばれ、今も一部地名などに残っています。この森を、かの文豪・小泉八雲は「神秘の森」と称しました。身隠神事が執り行なわれる「夫婦杉」、縁結び占いの「鏡の池」も、この森の中にあります。
蛇とは冬眠(冬籠り)する生物であるため、須佐之男の妻が蛇であることが「妻籠みに」という表現で暗喩されているのではないでしょうか。
八岐大蛇を退治した後に、須佐之男と櫛名田比売(稲田姫)が宮殿を建てて住んだのは、須賀(すが)の地とされています。
この須賀(すが)とは、奈良県明日香村(あすかむら)のことではないかと考えます。
「あすか」は「すか」に「あ」という接頭語をつけたもので、「すか」とは、「すがすがしい」という意味。
須佐之男と櫛名田比売の子とは蘇我氏だったのではないか、と以前の記事で考察しました。
明日香村の甘樫丘(あまかしのおか)の南東には、蘇我蝦夷と蘇我入鹿の邸宅だったと考えられる建物跡が見つかっています。
皇極3年(644〉11月、蝦夷と入鹿は、甘檮岡の上に家を雙(なら)べ構えた。この家が、蘇我本宗家の終焉の地となる。蝦夷の邸宅は「上の宮門(うえのみかど)」、入鹿の屋敷は「谷の宮門(はざまのみかど)」とよばれた。家の外には城柵をめぐらせ、門の傍らには武器庫が設けられた。門毎に水を蓄えた水槽がひとつと、木釣数十本が置かれ、火災の備えとされていた。そして、常に東国出身の兵士が武器を携えて邸宅の警護にあたっていたという。
蘇我蝦夷と入鹿の邸宅は、城柵がめぐらされ武器庫も設けられていたと言われています。
このように城柵が厳重にめぐらされていた、蘇我蝦夷(そがのえみし)と入鹿(いるか)の邸宅とは、まさに須佐之男の歌に詠まれている「八重垣」が連想されます。
ここで、須佐之男→蘇我氏→八重垣→蘇我蝦夷と繋がってきました。
このことから「その八重垣を」という句にある、「そ」とは、蘇我氏の「そ」を意味しているのではないか、と考えられます。
さらに蘇我蝦夷(そがのえみし)の「蝦夷」とは、「えびす」とも読むことができます。
飛鳥の展望台として有名な甘橿丘には、現在も「エベス谷」の地名が残る。入り組んだ西麓の地形は、まさに「谷の宮門」にふさわしいものとされてきた。これまでの居宅に比べて、甘橿丘そして畝傍山東の家をめぐる記述には、ことさら軍事的な側面が強調されている。これら二つの家と同時に、蝦夷は東漢(やまとのあや)氏の長直(ながのあたい)に命じて大升穂山(おおにほやま)に桙削寺(ほこぬきのてら)をつくらせている。
蘇我蝦夷と入鹿の邸宅があったとされる甘樫丘には、「エベス谷」と呼ばれる谷があるということです。
えみし、毛人・蝦夷の語源については、以下に紹介する様々な説が唱えられているものの、いずれも確たる証拠はないが、エミシ(愛瀰詩)の初見は神武東征紀であり、神武天皇によって滅ぼされた畿内の先住勢力とされている。
蝦夷(えみし)と呼ばれる人々は、神武天皇によって滅ぼされた畿内の先住勢力とされている、とのことです。
神武東征における、神武の戦いの相手とは長髄彦(ながすねひこ)です。
このことによって、神武天皇によって滅ぼされた畿内の先住勢力であると考えられる、蝦夷(えみし)の名が付けられている蘇我蝦夷とは、長髄彦の系譜である可能性が出てきました。
以前の記事で、長脛国→スキタイ→ケルト→イングランドの長脛王→ロスチャイルドの王→日本の長髄彦、という繋がりを考察しました。
イングランド王のエドワード1世は、長脛王(ながすねおう)という渾名を持ち、その名はケルトと繋がるスキタイの地にあったとされる「長脛」の国に由来していると考えられ、長髄彦とはケルトに繋がっている可能性があります。
そこで長髄彦の系譜を持つのではないか、と考えられる蘇我蝦夷がつくらせたという、「桙削寺(ほこぬきのてら)」という寺の呼称からもケルトとの繋がりを強く感じます。
ケルト神話に影響を受けた「アーサー王伝説」の中で登場する、「エクスカリバー」と呼ばれる剣があります。
ロベール・ド・ボロンの詩『メルラン(英語版)』では、アーサーは石に刺さった剣を引き抜いて王になるという伝承が語られている[30][注 7]。石に刺さった剣を引き抜くことは、「本当の王」、すなわち神により王に任命された、ユーサー・ペンドラゴンの正当な跡継ぎにしか出来ない行為だったという。
エクスカリバーという剣を引き抜くことは、「本当の王」であることの証であったというのです。
蘇我蝦夷がつくらせたという「桙削寺(ほこぬきのてら)」とは、このエクスカリバーという剣の伝説を彷彿とさせ、蘇我蝦夷こそが「本当の王」である、ということが暗喩されているのかも知れません。
蘇我蝦夷の邸宅があったとされる甘樫丘の「エベス谷」という呼称からは、聖書に登場する「エブス人」についても思い起こされます。
エブス人とは、秦氏であると考えられます。
須佐之男と櫛名田比売の子とは、明日香(あすか)という地で生まれ、エラム人(出雲族)とペルシャ(秦氏)との血脈を併せ持つ蘇我氏と大国主命の系譜となったのではないか、と以前の記事で考察しました。
蘇我氏が、エブス人(秦氏)とエラム人(出雲族)の両方の血脈を合わせ持つ可能性を考えると、甘樫丘の「エベス谷」という呼称にも蘇我氏の出自の痕跡が感じられます。
蘇我氏と一緒に語られることが多い、物部氏とは饒速日が始祖とされています。
饒速日とは火明であり籠神社の祭神で、饒速日とは徐福のことであり須佐之男のことでもありました。
饒速日や他の古代人が、何故このように多くの名を持つのか、それは秦氏や出雲族、蘇我氏や藤原氏など多くの氏族との血縁関係が示されていることが原因なのではないかと考えられます。
ということで、現時点での日本の氏族の関係について分かってきた自説を図式で表してみます。
長髄彦(秦氏・ロスチャイルド)→中臣氏→藤原氏 参照記事→こちら
エラム人(出雲族)+エブス人(秦氏)=蘇我氏
蘇我氏+藤原氏=物部氏 参照記事→こちら
蘇我氏・物部氏・藤原氏について調べると、元をたどれば皆同族なのではないかと感じられ、頭の整理がつきませんでした。
しかし上記のように図式で表してみると、既存の異なる氏族と氏族の婚姻によって新たな一族が生まれ、氏族の出自が見えにくくなり理解しにくかったのだと分かります。
今後また新たな発見によって、これらの仮説が覆されることもあるかも知れませんが、自身の頭の中のもやもやが少しずつ晴れて来ているのを感じています。
「日ユ同祖論」は疑うまでもない事実です。だからといって、日本人が偉いとも悪いとも言えません。
徳川家の信じる北斗七星と天皇家の信じるオリオン座。「天皇派」と「教皇派」の戦いは古代から既に始まっていました。
サタンは私たち人間が何もかも分からなくなるようにし、神様は私たち人間が何もかも分かるように導かれる。だから、分からないことは全て分かるまで研究し、祈り求める者となりなさい。
聖書の中には個々人それぞれの答えが封印されている。その封印を解いてこそ自らの人生を成功に導くことができる。
非真理を受け入れた人はどんな悩みも疑問も解決できず、真理を受け入れた人はどんな悩みも疑問もすべて解決し、全てが分かる喜びに満たされて生きられる。
RAPTさんのブログ
RAPT | 新・貴方に天国から降り注がれる音楽を
朝の祈り会、および有料記事のパスワードのご購入
BLOG BY RAPT
TALK RADIO
RAPT理論+αRAPT理論のさらなる進化形
十二弟子の皆様とRAPTブログ読者の方の証
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
