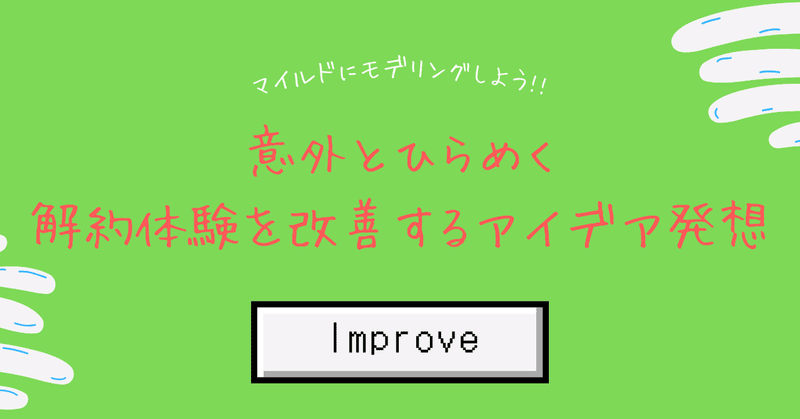
解約体験はどうやって改善できるか
以前に「解約体験にこそ企業姿勢が現れる」という記事で、なぜ解約体験が悪い企業がいるのかについて、その理由をモデリングによって考察してきました。しかし気になるのは「どう改善できるか?」ではないでしょうか。
これについてはこのnoteと連動しているPodcastでモデリング結果を元にして改善策を考えるブレストをしています。Podcastの台本として、解約体験の状況をモデリングしたところまでだったので、解決策はぶっつけ本番で喋っています。
これは事前準備を怠ったわけではなく、最初からフリートークで考えていたのですが「準備なしで会話が成立するだろうか?」と正直不安に思いながらの収録でした。
しかし実際には話は盛り上がりまして、録り直しもありませんでした。これもモデリングの効果だなと思います。(会話という空気感や雑談がコンテンツになるPodcastという音声メディアの特徴の影響も大いにあります)
この改善策についての記事は、Podcast収録後に書いておりますが、記事のベースとなっている議論も聞いて頂けると嬉しいです。
解約体験を改善する考え方
前回のモデリングによって解約体験を分析してきました。解決策を考えるといってもサービサーではないため解決策を生み出すことは難しいですが、モデリング結果を元にした分析から改善アプローチを考えることは可能です。
この改善アプローチ自体は、問題が変わっても適用可能なため多くの場面で活用できます。
それでは前回のモデリングでTOCクラウドによる解約体験の対立構造をどのように改善していけるかについて説明します。
どうすれば対立構造は解消するか?
まず前回の記事でも説明したTOCクラウドを見ていきましょう。

いくつかのテキストボックスが矢印で繋がっています。今回は改善策を考えるため、この対立構造をどうやったら解消できるかを考えます。
これは見方を変えると対立した構造を可視化したモデリング図です。つまりハコと矢印の関係が成立しているからこそ対立構造が発生していると考えることができます。
ならば、このつながりを切れば対立関係が解消できることが可能です。
構造のリンクを切れ!
この図でリンクしている箇所は全部で5つあります。どこかのリンクを切れば問題が解決します。
現状の対立構造を生み出しているそもそもの前提や結果を変えることが出来れば、このリンクを切ることが可能です

どこのリンクが切りやすい?
リンクを1つでも切れば良いとなると、考えるべきは「どこが切りやすいか?」です。実は切りやすさは箇所によって異なります。改めて整理するとリンクは3種類です。
共通目的 ← 要望:2つのリンク
行動 ⇔ 行動:1つのリンク
要望 ← 行動:2つのリンク
まずは「共通目的 ← 要望」はリンクを切るのが難しい個所となります。なぜなら共通目的に設定してある内容は、今の行動の根本理由や最終目的になっているからです。今回の例でも「お客様を大事にする」ことと「利益を大事にする」ことを変えるのは簡単ではありません。
次に「行動⇔行動」もリンクを切るのが難しい個所です。そもそも対立する行動が顕在化してしまっているので、リンクを切ることが難しい個所となります。
そのため「要望←行動」が、その他と比べてリンクが切りやすい箇所となります。対立行動を生み出している要望を見直すことができないか、その要望を実現する行動としてはより適切な行動が取れないか。既存の観点を抜け出して対立構造を考え直していくと、新たな選択肢を見つけることが可能です。

解約体験の改善策を考えてみる
この考え方をベースに、今回のTOCクラウドの対立構造解消のアイデアを考えてみます。狙い目は「要望 ← 行動」のリンクのため「お客様を大事にする」か「利益を大事にする」の前提や行動を変えることです。Podcastで話してみたときにはこんなアイデアが出ました。
・サービスを利用してくれそうな別の顧客紹介の施策に注力する
・ターゲット顧客以外にはスマートな体験を提供しない
・クーポンの効果が薄れない状態まで、案内回数を減らす
サービサーではないため、このアイデアの実現性や効果がどれくらいあるのかはわかりません。ただし出てきたアイデアの観点としては「顧客を引き留めない」「簡単に契約させない」といった既存の観点からは考えづらいものが出てきています。
解約体験を良くするだけでなく、それと連動して契約体験を見直す。こういった考えの幅をモデリングしたことで検討できるようになりました。
自分の解約体験に照らし合わせると、契約体験がスマートであったからこそ、契約後に自分が本当の顧客でなかった事がわかったので、そもそも契約をしなければ解約の不満も感じませんでした。また、サービサーとしてもターゲット外の顧客を契約させるのはネガティヴキャンペーンの危険性を減らせると思います。
問題解決にはモデリングが役に立つ
先ほどの解決策はサービサーからしたら、すでに検討したことかもしれません。しかし、サービスのことがわからない立場の人でもこれくらいの改善策を考えつくことが可能です。このように多くのアイデアを出しながら改善施策として磨き上げていくことになります。
当事者のサービサーでなくても、解決策を見出せるのはモデリングという「技術」を使っているからです。もし、ただ集まって「解決策を考えよう!」と会話しても、こういった議論をするのは簡単ではありません。
では、モデリングの価値はどこにあるでしょうか。それは解決アイデアを考える状態を作り出している前提条件を考えていくと見えてきます。この解決策を考える前提条件とは問題構造の可視化です。
つまり解決策を考える時には、まず問題を明らかにしなければなりません。逆に問題の構造を可視化できれば、解決の可能性はグッと高まります。
では可視化の前提条件は何でしょうか。それは現状とゴールの状態と、現状とゴールに存在するギャップを把握することです。
今回の例で言えば「企業として存在する」ゴールを達成するために、現状は「お客様を大事にする」と「利益を大事にする」ことを優先させるUXが対立している現状になっていて、その状態の差がギャップとして発生しています。
この現状をモデリングによって構造化し、そのギャップを1つの図解としてまとめて表示したことで問題を可視化しているのです。これがTOCクラウドによるモデリングの効果となります。
そしてモデリングによるメリットで重要なのが「シンプル」であることです。要素というオブジェクトの箱をリンクとして矢印で繋いで行き全体構造を描くことで図解できます。それがモデル図となります。このシンプルな図だからこそ、共有や認識合わせを素早く実施できるのです。
さきほどTOCのモデリングした図解によって、問題解決のアイデアを考え出すことが出来ました。実はそこに到達するまでのプロセス自体も、モデリングされています。
これは「問題解決のステップ」で検索すれば、すぐに結果が出てきますが、問題解決のステップは大まかな流れはこのようになります。

つまり、問題解決の進め方をメソッドとして適用できるのがモデリングの良いところです。このように問題解決の考え方の指針がわかっているからこそ、どんな問題が来ても取り組むことが出来ます。
モデリングという道具を使って山の登り方がわかっていれば、登れるかどうかは別として登ること自体の挑戦が可能です。これは山だけを眺めて、どうしていいかわからない状態よりも圧倒的に登頂確率が高くなります。
今回のようにサービサーではない2人が、解決策の議論ができるのはモデリングによる解決のステップを踏んでいるからです。冒頭では「フリートークで収録に不安がある」と書きましたが、実は「多分、うまくいくだろう」という勝算を持って話をしているのです。
この勝算の根拠はたった1枚のモデリング図です。議論のために必要なアウトプットはこれだけです。そう考えると、たった1枚の資料の有無が議論の結果に大きな影響を与えていることになります。それだけモデリングが強力な武器になっているということです。
ここまで読んで頂き、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
