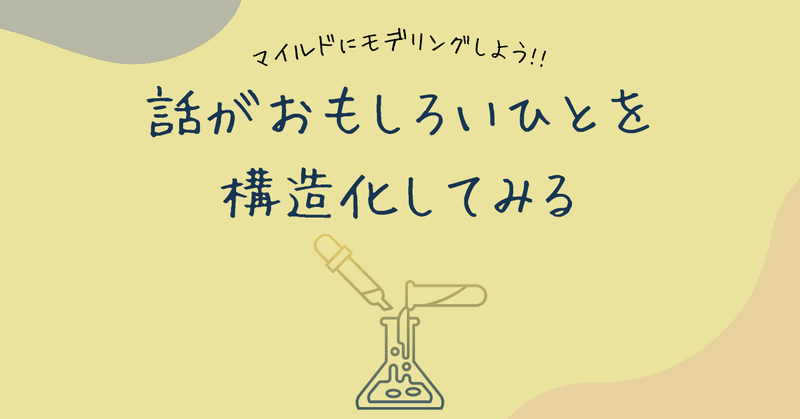
「あの人の雑談はなぜおもしろいのか? 」を話の構造から分析してみた
このあいだTwitterでアップルさんが整理したビジネス雑談のおもしろい人とつまらない人の分類がおもしろかったので引用リツイートを投稿しました。
これ解像度を高くするための行動をした人の話す内容が、結果として面白くなるのであって「話が面白い人になろう」が目標になってない。つまり「面白い話をする人になりたい」と思う人の話は面白くない。という構造が見えるのが面白いです。 https://t.co/2YlDPZOc3p
— Hori|CS Harmony カスタマーサクセス (@mttk_hr) March 20, 2023
自分がリツイートしたくなった理由は、もともと自分が「話がおもしろい人」のイメージについて新たな示唆を得たからです。
話がおもしろいの要素は「1次情報✗視座・視野」で整理できるのか!
確かに自分の体験と照らし合わせても、豊富な1次情報を持っていて自分よりも高い視座や広い視野からの切り口がある話は惹き込まれる事が多い。
一方で示唆から「1次情報と視座・視野はどういった構成要素から作られるのだろう?」と興味が湧いたので、今回はこれをモデリング(もやもやした内容を構造化すること)してみようと思います。
話がおもしろい人についてPodcastで話してみました。
今回のモデリング結果について話してみたPodcastです。
まずは「おもしろい」の定義から
ではお決まりの定義から定めていきます。今回のモデリングの目的は「話(ビジネス雑談)が面白くなる要素を構造化する」ことなのでゴールである「話がおもしろい」を想定して定義をこのようにしてみました。
定義 :「話がおもしろい」とは聞き手がおもしろいと評価する話
ゴール:おもしろい話をできるようになる
以降の記事で紹介するプロセス図のモデリング記法やツールの詳細についてはこちらの記事で説明しています。
おもしろい話を構造化した結果
まずは説明が長くなるので結論から入ると、話のおもしろさの構成要素を構造化した結果がこれです。

この矢印の関係から、おもしろいビジネス雑談には「数多くの経験」が絶対に必要であることがわかりました。この結果に至る分析過程については以降で説明していきます。
おもしろい話を構造化してみる
上記まとめに至った構造化分析について、まずは話のおもしろさを構造化したモデリング内容です。

図解したこのプロセスは、フローチャートと同じく左から右に流れていきます。話し手のプロセスから始まって聞き手のプロセスに引き継がれていく形ですね。
一応断っておくと、この構成要素については現時点での私の仮説です。構成要素としては色々考えられると思いますが重要要素を選別しています。
プロセスの会話部分の構造を確認する
二人の会話は赤線でマーカーしたプロセスで再帰的に繰り返されていきます。実際の会話では話し手が聞き手に変わり、また話し手に戻るといった形で繰り返されていきます。
本当の会話なら、話の区切りや時間や誰かからの割り込みなどといた「会話の終了条件」が存在しており、それもプロセス図に記載されるべきですがマイルドモデリングなので割愛しています。

またこの赤線マーカーで引いた以外は会話のプロセスでなく、会話として発信する内容を作る構成要素です。今回の構造化では、赤線が引かれていない矢印の部分が「おもしろいを作る構成要素」となります。
プロセスの構造を分析する
モデリングしたプロセスを分析する手順はこの2つです。
1.矢印が集まる重要な構成要素を探す
2.重要な構成要素から左に遡っていき根本原因を把握する
まず手順1の注目する構成要素を探すことになります。今回は矢印が集まる要素に圧倒的に差がありませんが、赤線マーカーが通らないプロセスで見ると「知識」です。また見づらいですが「新規獲得」と状態説明がされています。つまり「新規獲得した知識」を作る構成要素が、おもしろい話には必要となります。

次に手順2のプロセスを左に遡ってみると、根本原因が見えてきます。今回は話し手の知識(これまでの既存知識)と、外部の知識、経験値が因子となります。つまり、新たな知識は、既存と外部の知識、そして話し手自身の経験した内容から得た経験値を元に形成されるということになります。
つまり、話し手がビジネス雑談としておもしろい話をするためには知識と経験が必須であるとこの構造化分析からは読み解けます。

おもしろい話を作る決定的な因子
ここまで知識と経験値が大事だと伝えてきました。中でも経験値が構成要素として一番大事になります。なぜならこの経験値はおもしろい話をするために必要な一次情報と視座・視野の両方を構成する要素になっているためです。

改めて図をみていくと「一次情報」の要素に集まる矢印は「二次情報」と「経験値」です。また「視座・視野」の要素に集まる矢印は「知識(新規獲得)」と「一次情報」になります。
「一次情報」と「視座・視野」の両方を左に辿ると両者に影響を与えている因子が「経験値」です。このことから「経験値」がとてつもなく重要な構成要素とわかります。つまり経験値がないとおもしろい話ができないのです。
「よく学びよく遊べ」はまさにこれを体現しており、幅広い経験と知識を取り入れる行動をしていくと、その結果おもしろい話ができる人になっていきます。
おもしろい話と評価されるために何が必要か?
ここまで話し手のプロセスについて説明してきました。しかし話がおもしろいかどうかを判定するのは聞き手側です。聞き手がどのように判定しているかについては利き手側のプロセスから確認できます。

ここは前述した赤線マーカーで引かれた会話のプロセスに含まれる要素ですが、話し手の「会話内容」と聞き手の「知識」を元に「認識」をします。
この認識の条件分岐として「驚きがある」ことがおもしろい会話と判定する要素となります。
聞き手が既存知識と照らし合わせて未知の情報に出会った時に驚きがあるはずです。一方で驚きがない場合は既知の内容にとどまっているため「おもしろい」まで到達しません。
これは最初に聞いたニュース内容には驚くことはあるけれど、2回目以降に驚かないのと同じで、未知の情報が既存知識に取り込まれるためです。だからこそ、自分しか持っていない一次情報は相手に驚きを与えることが可能になります。なお、相手の興味がない話題は未知の情報でも驚きません。
ただし既知の情報でも、視座が高く視野が広いと情報の解釈として新鮮さが未知の情報として得られるため驚きがあります。
整理すると受け手が驚くポイントは2つあります。
情報の内容としての驚き
情報の解釈としての驚き
どちらか1つでも満たすと「おもしろい」になるのですが、2つとも満たせれば「おもしろい!!」になる感じですね。
おもしろい話の進み方
今回は「おもしろい話の構造」を可視化しました。それではおもしろい話はどのように展開されていくのでしょうか?
これはお互いの共通関心テーマにおける驚きを相互に提供しあうことで進んでいくと思います。その時に驚きの数が多いほど「おもしろかった!!!」となるのです。
構造を分析してみた結果から、自分なりのイメージはこんな形ではないかと考えています。

同じ関心のあるテーマでも持っている知識と経験はそれぞれ別ものだから、仮にAさんの知識・経験がBさんとしては未知の情報なら驚きを得ることになります。またBさんの知識・経験がAさんとして未知の情報なら同様に驚きがあります。このように共通領域でも驚きは提供できるので、会話が弾んでいくことになります。
ただしAさんとBさんが同じ環境にいると、知識・経験が似通っていき驚く機会が減っていきますので、同じ業界にいる別企業の人と会話するほうが驚きを得やすい可能性が高くなるのです。
話のおもしろい人は目指せるのか?
おもしろい話の構造がわかったら、誰でも同様におもしろい話をできるようになるのでしょうか?
これについては「半分Yesであり半分Noである」と考えられます。
なぜなら今回分析したプロセスの構成要素は全て点線です。点線の要素はノウハウといった暗黙知であり属人性が高いものになります。そのため構造が理解できても品質担保が人によって異なり、経験値や視座・視野の品質が人によってピンからキリまでバラけてしまうのです。
おもしろい話をしているかどうかはその人の獲得した知識と経験値に依存するので、同じ知識と経験値を元にした会話でも人によって内容が全く異なることになります。
そのため話し手によって「おもしろい」と認識する受け手の数は大きく変わることになりますが、受け手も属人的な知識を元に判定するため「おもしろい」と思ってくれる受け手が全くいない状況は考えづらいでしょう。
話がおもしろい人になるためのジレンマ
今回の分析から話を面白くする要素は明らかになったので、その要素獲得に意識を持てば戦略的にビジネス雑談がおもしろい人になれるはずです。
しかし皮肉なことですが、戦略的に「話がおもしろい人」になることを狙うには多くの学びと経験が必要になります。これを積み上げていくためには、おもしろい話をしようという動機が原動力にすると達成が難しいものです。
つまり、おもしろい人になりたいをゴールにすると、到達するのがとても難しいという葛藤を抱えることになるのがわかります。
このジレンマに対応するには、それよりも様々なことに好奇心を持ってよく学び、たくさん体験することのほうが重要になりますね。
ここまで読んで頂きありがとうございました。励みになるので、よければこのnoteのシェアやスキをお願いします!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
