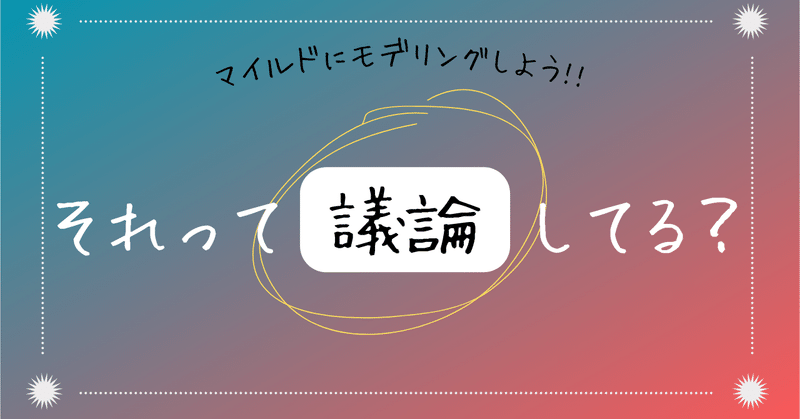
それ、議論じゃなくね?
日常の中で「議論しよう」と言われる機会は結構あると思いますが、実際に議論が正しく行われていることが少ないように感じます。多くの場合は、議論でなく質問や確認、もしくは主張を押し通すための説得の場になっていることもあります。
これは本当に議論なんでしょうか?
議論とは、お互いの意見をぶつけ合いながら、より良い結論を導き出すためのものです。議論を通じて、どこに合意でき、どこに合意できないか、なぜ合意できないのか、そういったことを話し合いながら、議題に対する認識を深めたり、議論相手との相互理解を高めることが大切なはずです。
しかし、多くの場合は、そうした議論ができないのは、議論をするための構成要素が足りないからかもしれません。

今回はそんな「議論」ついて、モデリングして考えてみたいと思います。
議論の定義
まずは「議論」の定義について調べてみます。
互いに、自己の意見を述べ、論じ合うこと。
この説明だけだとピンとこないので、議論という言葉の解像度を高めるために、議論と似た言葉も含めて整理してみます。
議論の類義語には、このような言葉があります。
討論:
互いに議論を戦わせること。意見を出して論じ合うこと。是非を詳しく論じ合うこと。対話:
直接に向かい合って互いに話をすること。相手を尊重しながら行われることが特徴。談話:
話をすること。ある事柄に関して、非公式にまたは形式ばらずに意見を述べること。
討論と似たものにディベートもありますが、大きくはこの分類をしてみました。
議論はこれらと比べると「議題について最良と思われる結論を導くこと」が目的となっていると考えられます。そのため自分の主張を通したり、相手を深く理解するのではなく結論を導くことが議論を行う重要なプロセスとなります。議論では他人の意見をもとに、自分の意見を変えることありです。
つまり議論とは、特定のテーマや問題について、意見を交換しながら結論を探求する共同作業を行うプロセスとなるのです。そう考えると、ビジネスシーンで「議論」という言葉がよく使われるのも納得しますね。
議論の構成要素
ここからモデリングをしていくために、議論を成立させる構成要素にどんなものがあるかについて整理してみます。
問う(質問する):
議論の情報を求めたり、議題に対する理解を深めるための行為。提示する(論証する):
主張や意見を支持するための理由や根拠を示す行為。推論する:
与えられた情報や証拠から論理的に結論を導き出す行為。支持する(証拠を提供する):
主張や論点を裏付けるための事実やデータ、証言を提供する行為。反論する:
対立する意見や論点に対して論理的な反証を行う行為。説得する:
相手を自分の意見や立場に同意させるための論理的かつ感情的な行為。合意する:
議論の結果として、共通の結論や解決策を導き出す行為。聴く(リスニングする):
相手の意見や立場を注意深く理解するために聴く行為。分析する:
議論の中で提出された情報や論点を詳細に検討し、理解を深める行為。統合する:
議論の中で生じた異なる意見や情報をまとめ上げ、全体としての理解や結論に導く行為。
10個もキーワードが出てくると少し数が多いので、もう少し分類して整理して構成要素を構造化するとこんな感じになります。

効果的な議論では、これらの要素が適切に実行され、バランス良く組み合わされることで、正しく行われることになります。
議論の「前提を作る」ために必要な行為
聴く議論を「構築する」ために必要な行為
問う(質問する)
提示する(論証する)
支持する(証拠を提供する)議論を「深める」ために必要な行為
推論する
分析する
反論する議論を「結論に導く」ために必要な行為
統合する
説得する
合意する
つまり、議論とは議論の前提の土台がある状態で、議論を構築し、深めて、結論を導く、という一連の流れの行為であると考えられます。
「議論しよう」が引き起こす問題
議論のプロセスを構造化してみて気づくことは、本来の議論ができない多くの場合が、議論に必要なプロセスの構成要素すべてを満たせないからだと考えられます。
例えば、議論の場で質問だけで終わるなら、議論の構築しか実行してないことになります。また説得するだけなら、議論の経過に関係なく結論を導くことしか実行できないことになります。どちらも片手落ちな感じになってしまいますね。

どうして議論に必要なプロセスを満たせないかというと、議論の参加者が正しい議論を実施できない理由があるからだと考えられます。
「じゃあ、その理由ってなに?」ということですが、ここについては議論に参加する人々の関係性が重要になると考えています。
議論とは結論を導く共同作業なので、共同作業ができる関係性になっていることが正しい議論を実施するためには非常に重要です。しかし現実はこの関係性が築けてない状態で議論をすることが多いのではないでしょうか。だから議論としてやるべきプロセスが不十分になる。
特によくあるのが上司部下の関係です。このような権力の不均衡があると、議論のプロセスに大きく影響します。関係性がなければ部下は上司に対して自分の意見をためらう可能性があります。そういった状態だと議論は一方的なものとなり、多様な視点やより良い結論が見過ごされる可能性があります。

そのため関係性の不均衡を防ぐことが、良い議論には必要です。こういった条件が満たされていなければ、良い議論をするのが難しくなってしまいます。
対等な関係か?
効果的な議論には、参加者間の対等な関係が必要不可欠です。これを実現するためには、全員が意見を自由に表現できる安全な環境の提供が重要となります。上司が部下の意見を尊重し、すべての意見が公平に評価される雰囲気が必要です。透明性が確保されているか?
議論の透明性は、プロセスと結果の双方において重要です。意思決定プロセスが透明であれば、参加者は自分の意見がどのように取り扱われ、考慮されたかを理解しやすくなります。これにより議論に参加しやすくなります。建設的なフィードバックが得られるか?
議論の質を高め、参加者の成長を促すにはフィードバックがとても重要です。フィードバックによって、議論のプロセスは健全に進み、結論を導くための参加者の協力や共同が可能になります。
これらの要素が揃って初めて、議論は本来のプロセスを実施することが可能です。
無用な「議論」を避けるには?
ここまでの話を整理すると、正しい議論を実施するには、参加者の関係性と議論プロセスの進行という前提が成立している必要があります。
もし、この前提が担保できないならば議論すること自体が非生産的になる可能性が高くなるので、議論そのものを避けたほうが賢明かもしれません。そういったときは議論をするのではなく、対話などから相手を理解することに切り替えたほうが良いことになります。

対話で相手の理解を深めることで、結果として意味のある議論ができる可能性が高くなります。その時に効果的な議論をするためには下記の観点を意識すると成功確率が上がります。
まずはリスペクト
議論の基本は相手へのリスペクトです。意見の違いを尊重し、全ての参加者が価値を感じられるようにします。明確なゴールの設定
議論の目的を明確にすることを意識する。ゴールが事前に明確であれば、最良かどうかはさておき結論を出すという、議論としての生産性は上がります。全体進行をコントロールする
議論を進行する立場に立つと全体をコントロールしやすくなります。有意義な議論をするには、スキルを磨く必要はありますが、ファシリテーションが有効です。ファシリテーションスキルを磨くこと、無用な議論を避けられる可能性は高くなります。
健全な議論ができる文化を作れたほうが絶対によい。そうなったら誰がそれを牽引するかという問題になります。議論を適切に進行できる能力はどこでも通用するポータブルスキルなので、スキルを磨くチャンスとして、自らが議論を仕掛けたほうが実は手っ取り早いかもしれません。
そんな議論することについて、あれこれとPodcastで話しています。
ここまで読んで頂き、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
