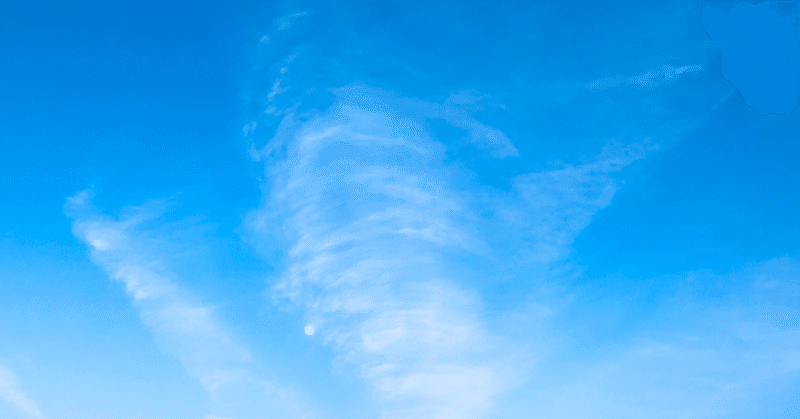
相続法ばかりが詳しくなっていく司法書士受験生 #10
ご縁があって、相続の手続きに関する記事を継続的に執筆する機会を頂いている
相続は、人生の一大イベントと言っても過言ではないが、家族が亡くなった時に発生するという性質もあり、あまり経験したくないことかもしれない
でも、いずれはやってくる
私も、一度経験しているが、なかなか塩辛くてしんどい経験だった
相続に関連する手続きはたくさんあり、家族が亡くなった後の悲しみにくれる間もなく容赦なく突きつけられていく
相続放棄をしたい場合(包括遺贈による遺贈の放棄も同様)は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内
相続税の申告は、被相続人が死亡したこと(相続が開始されたこと)を知った日の翌日から10か月以内
法定相続分で分ける場合、遺産分割協議をする場合、遺言が見つかった場合…
人それぞれにいろいろなパターン(人生ドラマ)があるので、相続の勉強は訳がわからなくなることも多いが、私の場合は、いろいろなパターンがあることに逆に勉強のやりがいを感じてどんどん覚えていく
相続の各種手続きを始める前には、必要な書類をかき集める
相続人を特定するために、被相続人が亡くなった時から生まれた時まで遡った戸籍謄本または除籍謄本を取り寄せる(講義では、生殖能力のある13歳まで遡ると言ってた)
共同相続で、相続人全員の署名と実印、印鑑証明書が必要な場合に、全員分が揃うまで大変な時がある(共同相続メンバーが遠方や外国に住んでいる場合とか)
遺言があったので開封してみたら驚きの事実が......!(いわゆる隠し子の存在とか)※自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要(ただし、法務局保管の自筆証書遺言は検認不要)
遺言による指定相続分があった場合は、残りを他の法定相続人で法定相続割
遺言による指定相続分が、法定相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分侵害額請求(最近ようやく、遺留分減殺請求からこの新しい名称に脳みそが書き換えられた)できる
兄弟姉妹が相続人の場合に、兄弟姉妹が複数人いる場合、父母の片方のみが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の両方ともが同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1
相続に関する記事を執筆していると、おのずと、相続法に詳しくなっていく
そして、相続登記のことを執筆すれば、不動産登記法も多少詳しくなってくるのが嬉しかったりする
そしておまけに(追記:いやおまけではなくかなり)、相続税法(相続税、贈与税)にも詳しくなっていく
これから社労士になるのだから、税法についてはあまり詳しくなくてもよい、という考え方ではないので、税法の知識も、もりもりと蓄えたい
勉強する時間がなかなかとれない場合は、こういった形で、仕事を通じて勉強するのも一つの方法かと思う
相続法ばかりが詳しくなっていくので、多少バランスが悪いが、相続の専門家になりたいという気持ちもあるので、これを機に詳しくなっておこうと思っている
私が執筆した記事を師匠にみせると、法解釈の話に花が咲く(花が咲くというか、師匠が民法に対してアツくなっている)
私は、人生の中で親族法に関する問題に直面する機会も多いので、親族法についても多少詳しかったりする
生きていると、自然と法律知識が身についてしまってることも多い
普通なら弁護士に依頼するようなことも経験してみた
机上の知識だけではなく、リアルな経験は、仕事に活かすことができるのではないかと思っている
人生がドラマティックだと、法律に詳しくなる
私が法律家を目指しているのは、自分の人生に必要不可欠だからかもしれない
※ヘッダー画像は、みんなのフォトギャラリーより、dondonikouze様の「Dear」という作品です
最後まで読んで下さりありがとうございます
皆様よいお年をお迎え下さい
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
