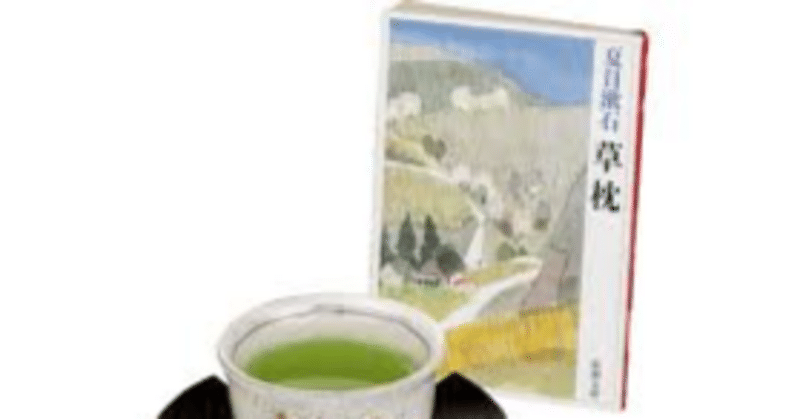
夏目漱石の名作に登場するお茶・紅茶への思い 4
Ⅰ 漱石とお茶 4
❹『坊っちゃん』
『坊っちゃん』は親譲りの無鉄砲で江戸っ子気質な主人公が、四国の地方に赴任して、中学校の教師になるお話。何度もメディア化され、国語の教科書にも採用された作品だけに、知っている方も多いのではないでしょうか。
漱石の小説では、登場人物たちがよくお茶を飲んでいますが、そのお茶は味が薄いことが多く、ときには粗茶(そちゃ)であることも。漱石が日常を描くお茶は薄味なのです。ところが、『坊っちゃん』(三)の地方で出てきたのは、苦い濃い茶。お茶の味わいから、東京との違和感を表現しています。
「(略)
それからうちへ帰ってくると、宿の亭主がお茶を入れましょうと云ってやって来る。お茶を入れると云うからご馳走をするのかと思うと、おれの茶を遠慮なく入れて自分が飲むのだ。この様子では留守中も勝手にお茶を入れましょうを一人で履行しているかも知れない。亭主が云うには手前は書画骨董がすきで、とうとうこんな商買を内々で始めるようになりました。あなたもお見受け申すところ大分ご風流でいらっしゃるらしい。ちと道楽にお始めなすってはいかがですと、飛んでもない勧誘をやる。 (中略)
おれはそんな呑気な隠居のやるような事は嫌いだと云ったら、亭主はへへへへと笑いながら、いえ始めから好きなものは、どなたもございませんが、いったんこの道にはいるとなかなか出られませんと一人で茶を注いで妙な手付(てつき)をして飲んでいる。実はゆうべ茶を買ってくれと頼(たの)んでおいたのだが、こんな苦い濃(こ)い茶はいやだ。一(いっ)杯(ぱい)飲むと胃に答えるような気がする。今度からもっと苦くないのを買ってくれと云ったら、かしこまりましたとまた一杯しぼって飲んだ。人の茶だと思って無暗(むやみ)に飲む奴(やつ)だ。主人が引き下がってから、明日の下読(したよみ)をしてすぐ寝(ね)てしまった。」(『坊っちゃん』三)
解説
東京育ちの主人公は、引っ越し当初、とにかく地方では気に入らないことばかり。古い慣習から、学校の派閥争い、はてはお茶にまでケチをつけます。『坊っちゃん』では、四国に赴任した主人公が、関東の薄いお茶に比べて、ここのお茶は苦そうだと懸念を述べ、四国に感じる東京との異質感を表しています。 (つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
