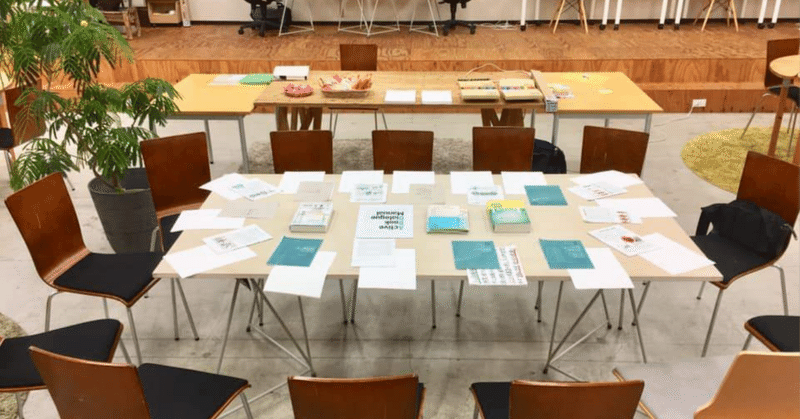
ネガティブ・ケイパビリティを巡る脳内会談
こちらの記事では、書籍「ネガティヴ・ケイパビリティで生きる ―答えを急がず立ち止まる力」を通じて得た気づきについて、脳内の仮想キャラを通じて伝えるという新しい取り組みを実践しています。ネガティブ・ケイパビリティという、答えが安易に出ない問題に対し、わからなさを受容する態度は、現代を生きる私たちにとっては対話能力と同じくらい重要な能力です。個性あふれる3人の会話をお楽しみください。
こんにちは、おがくずにゃんこです。
わからないことは、わからないままにしていい。
そんな世界になれば、優しい世界に近づくのではないかと思い手に取った一冊があります。
こちらの本について「わかりやすい」感想を伝えるのはなんか違うのではないか、ということで、突如脳内で巻き起こった3人の対話を通して内容を伝えてみたいと思います。登場人物は以下の3人です。
マサル:仕切りたがりだが、持論を話し始めると止まらない。基本的に真面目だが、真面目じゃない人間を嫌悪してしまう一面もある。
ハナ:傾聴を心掛けているが、自分の意見ははっきり言ってしまう。10-14歳をアメリカで過ごしたが、本人は帰国子女と言われることを嫌う。
ユウ:会話に苦手意識があるが、考えをまとめるのは得意。男なのに女性っぽい名前がコンプレックス。
3人のネガティブ・ケイパビリティを巡る対話をお楽しみください――
マサル:というわけで、今日はネガティブ・ケイパビリティとは何なのかについて話していきたいと思う。取っ掛かりとして、SNSに支配される社会というのはどうだろう。今の20代、30代では、X(Twitter)、Instagram、FacebookといったSNSを持っていない人のほうが少数派だと思う。そんな僕たちは、誰かの意見がバズったり炎上したりするのを見るわけだけど、そういった投稿というのは、得てして極端な意見であることが多い。そんな言説に振り回されることに僕は最近疲れてきていて、適切な距離感が分からなくなってきているんだよね。
ハナ:疲れるって感覚は共感できるね。スマホを使い始めたころは、見様見真似でおしゃれなカフェの写真をアップする体験自体が楽しかったけど、付き合うコミュニティが固定されてからは、どんな体験をシェアすれば「当たり障りがないのか」ということをすごく気にするようになった。インフルエンサーの投稿と仲間内で共有する想定の投稿は性質が違うかもしれないけど、義務感を感じたり、現実世界で求められるような「空気を読む」能力を求められる感じは、はっきり言って疲れるよね。私はそういうの煩わしいから最近は見るだけにしてる。
マサル:確かに最近は「見る専」という人も多いよね。一方で僕はいわゆる「ツイ廃」になってた時期があって、あの頃は何すればバズるんだろうってことを四六時中考えちゃってた。もうみんな覚えてないかもしれないけど、寿司チェーン店で醬油をペロペロしちゃった少年の気持ちも僕は痛いほど分かっちゃうんだよね。何物でもない僕らのような小市民が目立つためには何か尖ったことが必要で、社会的な善悪という軸よりも「目立つ・目立たない」という軸のほうが優先されるというか、目立たなきゃいけないという変な強迫観念や焦燥感がある。なんでそんな悪目立ちすることをやってしまうんだ、ネットリテラシーがなってない、っていう見解もあるけどそれは全然違うと思っていて、すべてはSNSが承認欲求という化け物を生み出してしまったことが悪いと思うんだよね。目立つことが評価されるという時代においては、多少悪いことでも目立てば勝ちというところがある。仲間内でだけ盛り上がれればいいんだけど、SNSというのはインターネットによって世界中に拡散されて「炎上」という取り返しのつかない事態に発展してしまうということもある。これはネットリテラシーがどうこうというよりも、まずその「いいね!」稼ぎなんかしなくても承認欲求が満たされることが重要だし、何より承認欲求という化け物を生み出す今のSNSの構造そのものに問題があると思う。僕自身ツイ廃ではなくなったけど、承認欲求は常に満たされないなと思っているところがある。これは「何物にもなれない」大多数の人々の間でそんなに特殊な感情でもないと思っているし、こういう感情に対して「なんでそんなにバズりたいの」と一線を置いて、理解を拒むのも違うんじゃないかと思う。ごめん、長くなったのでこの辺で!
ユウ:なんだか現代特有の病っていう感じになってるけど、承認欲求自体は昔からある感情だよね。古来より戦では「名を上げる」ことが重要なことだったわけで。最近はそういう感情を、GAFAといったテック企業が「ハック」して、自分たちのマーケットで良いように人々を操ってるんだよね。俺たちが作ったプラットフォーム上で、人々よ面白いコンテンツを作って競え!と(笑)
ハナ:大きな話になっちゃうけど、今の新自由主義的な社会って、何でもかんでも競わせるよね。現代社会って何だかんだ何かしらのコミュニティに所属しなければ生きていけないから、そうすると否応なくその中での競争を強いられるというか。そういった競争の象徴がGAFAで、そういった企業のサービスなんだから、それらが競争を後押しするのは必然だよね、っていう。そうじゃなくて、自分が満足ならそれでいいや、って現状維持でずっと甘えられる場所があるといいのかな。
ユウ:自己満足って言葉がネガティブなニュアンスを含んでるのも競争を前提にした見方があるよね。競争から降りるのって本当に難しくて、どこか別の場所に移ったとしても、そこでは別の序列が機能していてまた一番下からスタート、みたいなことが世の中平気である。そこで、ちょっとマサルの「バズりたいという感情を理解しようとしない」って話に戻るけど、誰もが違う感覚を持ってるって、忘れがちなことだと思うけど重要だと思う。それこそSNSとかって、「いいね!」数という目に見えた序列があるけれど、そうじゃなくて、身の回りの人だけでも、いろんな言葉を「並列に」評価して、「フラットに」全員を評価できると良いなって思った。特にFacebookって、友達が多くていいね!も多い人=すごい!ってなりがちだけど、別に友達少なくても良いじゃないというか。等しくみんな自分の友達だろ!って感覚(笑)
マサル:そうそう、フラットという感覚が本当に忘れがち。バズりたい!って承認欲求はかなり競争を意識した序列のある感覚ってことを巧妙に隠してるよね。内発的動機だから新自由主義的に良いこと!って気がするけど、意識するしないに関わらず、目立つということは他の誰かよりも何かしら優れていることを示すことになる。いいね!数なんて単なる数字で突き詰めれば空しいんだけど、みんながそこに価値を見出している限りは貨幣のようにその価値は衰えないし、序列があることも変わらない。そういった序列関係と、フラットな友人みたいな関係ってそもそも軸が全然違うんだよね。そうか、友達と思える人とだけつるむっていうのはある意味真っ当な精神状態なんだなぁ。
ハナ:めちゃくちゃ納得してるけど、それが当然ということを忘れさせるSNSってやっぱり病的な側面があるね。一方でSNSを通して、専門的な意見を気軽に知ることもできるし、自分の本来の生活圏では知りえないような情報を手にすることもできるから、それは良い側面だよね。ということを考えると、「いいね!」数や「フォロワー数」を一切見えなくするのは有りなのかなと思った。たぶんそれだと成立しないんだろうけど。
マサル:確かにそれは流行らなさそうだな…ただまあ、自分の中で割り切って使うというのは必要だと思った。承認欲求はいったん脇に置いておいて、どういう目的で使っているのかを意識するというか。バズりたい!って思いながら使い続けるのは、逆に道具に使わされてる感じがする。
ユウ:このテーマは無限に話せそうだけど、そろそろまとめるか。SNSは個人の承認欲求を増長させて繁栄してきたけど、その結果として現代人は時に過剰な競争に明け暮れ、疲れてしまうことがある。それは新自由主義的な競争原理に根差していて、本質的に人々の関係に序列を生み出している。ただ、本来人々の繋がりというのは「タテ」じゃなくて「ヨコ」の場合の方が多いわけだから、そっちにもっと目を向けることが重要、という感じかな。最後にちょっと、このテーマは教育も重要な気がする。SNSに振り回されないようにするにはネットリテラシー教育だけでは不十分で、フラットな人間関係の構築や、個人を真の意味で尊重するとはどういうことか、ということについて考えさせることが重要だと思う。従来それは友達同士の遊びを通して学ぶものだったんだろうけど、最近は公園で遊ぶこともできなくなったし、友人関係そのものが希薄になってきている。オンラインを通してでも、もっと情緒的な面を学べるような仕組みがもっと必要なんだろうね。
マサル:まとめをありがとう。僕はまだ自分の承認欲求から逃れられないけど、本当は仕事であったり、リアルな関係の中で成果を出し、認められるように日々奮闘するのが大事だっていうことは薄々気づいているよ。ただそれでも現在のSNSをなんとか活用できないか、ということをどうしても模索してしまう。だって世の中どんどん生きづらくなってきてるわけで…おっとこれは長く長すぎるので、また次のトークで話そう。ハナからも何かあるかな?
ハナ:うーん、バズりたいという承認欲求についてもっと理解しようと思ったけど、所詮バズったところで一時的な快楽に過ぎないんじゃないかって思うんだよね。それはやっぱり空しいだけだから、みんなもっと充実できることを探しな!
マサル:それは手厳し…締めにふさわしい言葉をありがとう。それでは今回はこの辺で。もしこのノリが好きだったら冒頭の書籍も合ってると思うので、ぜひ手に取ってみてくださいねー!それではまた!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
