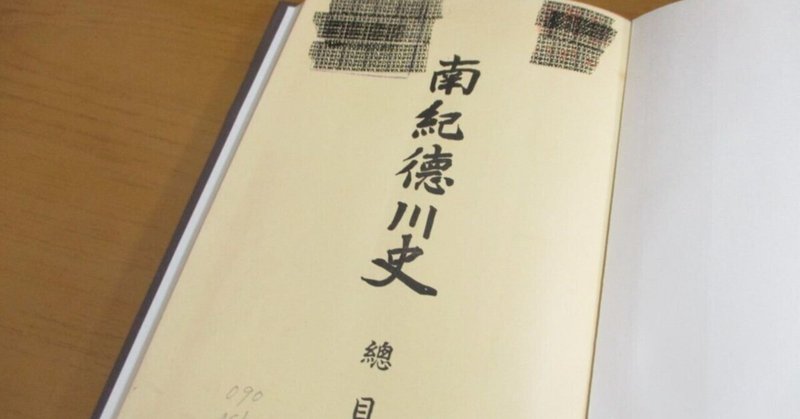
熊野結縁#02/紀州徳川家への疑問
【徳川家康の十男である徳川頼宣が紀州藩主に封じられたのは元和5年(1619)だった。それまでは駿府藩主を務めていた。家康が死んだのは元和2年(1916)だったから、徳川秀忠のときだ。家康は慶長10年(1605)将軍席を秀忠に譲っている。家康が駿府城に移ったのは、この2年後である。その時の藩主が十男・頼宣である。頼宣は5歳だった。母は万。勝浦城主・正木頼忠の娘である。
徳川頼宣は紀州に赴いたのは17歳の時である。・・なぜ直系を紀州に置いたのか? 水軍と水利を説く人は多い。しかしもう一つ腑に落ちない。どう考えても、当時は今以上に山深く、産業が成立しにくい地域だったからだ。だと云って防衛の拠点とすべき要素はなにもない地区である。確かに南北朝時代、伊勢は大きな意味を持っていた。しかし、いまでもそうだが当時は伊勢と紀州は隔絶していた。伊勢は名古屋からいくもの。紀州は大阪から行くものだったのである。
なぜそこに、直系のそれも末子(おそらく家康が、日々顔を合わせ溺愛したであろう)を置いたのか?
たしかに水利は既に房総との間に開かれていた。なので房総と紀伊は同名の町が多いが・・堀内信による「南紀徳川史」をみても、いまひとつ痒いところに届かない。
https://webarchives.tnm.jp/.../3057;jsessionid...
たしか和歌山城がある紀の川河口は、水運によって栄えた地であることは間違いない。大阪にも近く紀伊半島奥地から運ばれる様々な産物を、中央に商う地として極めて有利な地である。しかしだがね、紀伊半島奥地から流れ出る川が作る河口の平地が。紀州には幾つあるのか?それも陸地は難所続きで、それぞれの河口はは飛び地状態である。伊勢との間はあまりにも山深く、隔絶状態にある。
何故その地を束ねて愛息のものとしたのか・・家康の心の軌跡が辿れないのである。あれほど、深淵に考え抜く人物である。何か、おおきな理由がある。僕はそう思うのだ。木材は豊富に伐採出来るが、金山があるわけではない。
家康死後、御三家の一つとなる紀州徳川については、とても悩ましい思いを持っているのです。
ちなみに第5代藩主・吉宗が第8代将軍・徳川吉宗となり、第13代藩主・慶福が第14代将軍・徳川家茂になっている。実は、御三家のうちで将軍を出した唯一の徳川家である。
そのうえ、維新政府による徳川資産の簒奪から逃れている。最後の藩主である茂承が華族となったが、その資産は華族の中でもダントツに多かった。しかし本家徳川の鏨が緩んだことで、浪費家が頻出し戦後・頼貞の代でほぼ没落している。「平成新修旧華族家系大成」を見ても紀州徳川家の当主の名は空白になっている。
無くてもいいような話ばかりなんですが・・知ってると少しはタメになるようなことを綴ってみました
