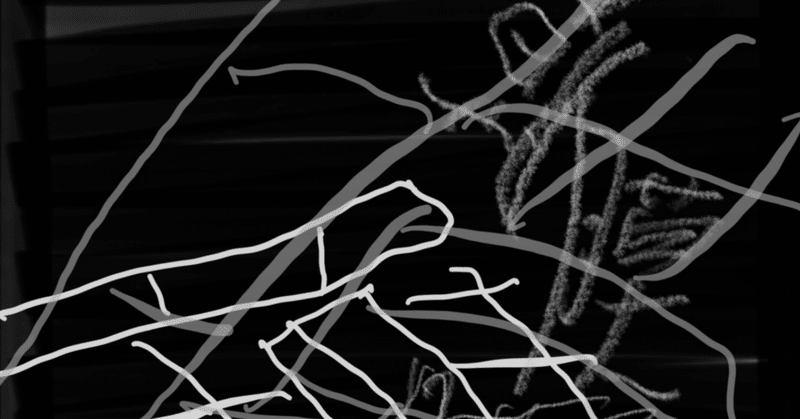
「滝沢汀の漢字書de現代アート」
漢字って面白い
今、私は「漢字」をモチーフに現代アート作品を創作しています。
なぜ漢字なのか。
漢字は古代に生きた人間の感性や思想・哲学がその中に練り込まれていてる、とても魅力的な文字であると同時に、書の起源と歴史に深く関わる文字でもあります。
幼い頃より書に携わり、日本人としての文字教育を受けてきた私にとって、漢字は自身のものの捉え方や考え方、発想などに深く影響を及ぼしているであろう、どうしても切り離すことのできない関係にある文字だと思うからなのです。
そして元来書とは、文字を記し伝え残すことから始まったもので、書家である私が何かを書いて表現しようとした時、漢字を書いて想いを表現することは自然な成り行きだったようにも思うのです。
もちろん、漢字だけでなくカタカナやひらがな、数字、そして今や日本の社会に普通に溶け込んでいるアルファベット、馴染みの深い記号たちを記すことも書であると思っているので、今後そういった作品を創っていく可能性はおおいにあるだろうと思います。
(実際、既にアルファベットやカタカナの作品もあります。)
ただ、今は漢字なのです。
一つの文字が複数の意味や読み方を持つ漢字は、自然界にあるものの形を象(かたど)り、それを簡略化して作られた象形文字、抽象的、形而上的なことを表現している指示文字、それらを複数組み合わせた会意文字など、その多様さ、奥深さは計り知れません。
日常生活を送っていると、ふと浮かんだり目や耳に残る言葉が、漢字となって私の脳裏に映し出される時があります。
それは、その漢字が意味し象徴しているものと、私が日々考える現代社会やそこに生きる人々のあり様とがシンクロする瞬間なのだと思います。
字しか書いていないのに絵に見えると言われる件
そんな私のここ数年の作品を見て下さった方たちから、「字しか書いていないのに絵に見えるね」と感想をいただいたり、
「この中には字が書いてあるの?」と聞かれ、
「・・・っていうか、字しか書いていなくて絵は一つも書いていないんです・・・」
というような会話のやり取りをすることもしょっちゅう。
なぜ字しか書いていないのにそう見えるのか、その自己分析は少し後にして、その前に、絵のように見える書で思い出すひとつの日本の伝統的な書体・技法があります。
それは「葦手書き」。
「葦手書き」とは
「葦手(あしで)書き」とは、平安時代にはじまった書体の一つで、
水辺などの光景を描いた絵に、植物の葦(アシ)や鳥、石などの文字を絵に溶け込ますかのように書き込む技法のことを言います。
料紙の下絵や、蒔絵(まきえ)などの技法で作られた工芸調度品などにそれを見ることができます。
たとえばこんなのです。

源雅実の歌
「なほ照らせ代々に変はらず男山仰ぐ峯より出づる月影」を主題とした硯箱

重要文化財

※「平家納経」平安時代に平家一門が
その繁栄を願って厳島神社に奉納した一品経

国宝 雲仙院千代姫所用
江戸時代
最後の写真は、徳川三代将軍・家光公の長女として生まれた千代姫が2歳6カ月で尾張徳川家に嫁いだ時の婚礼道具のひとつで、硯(すずり)箱です。
「初音の調度」と呼ばれ、歴史的・芸術的に高い価値を持つことから国宝に指定されています。
左の写真では判別しにくいのですが、よく見ると右側の写真で赤く見える部分が、「年月」「人」などの字が絵に紛れるように書き込まれています。
このように葦手書きはしっかりと日本の伝統文化の中に溶け込み、世の中に認知されている書法でもありました。
「絵の中の文字」と「文字ばかりで脳内風景」
絵と文字が一つの画面に書き込まれて成立しているものとしては、山水画や禅画もありますが、それらは画と讃(絵画に書き込んだ詩文)として、書き込まれる場所の区分わけがされています。
しかし、絵と文字が一体化している「葦手書き」は、それらとは違った独特の技法といえるのではないでしょうか。
一つの文字の中に、それが持つ意味や元々の象形を、切り離すことなく捉えている日本人独特の感性が生んだ書体なのではないかと思います。
文字だけで心象風景や脳内イメージをそのまま表現している私にもそういったDNAが引き継がれているのかもしれません。
ただ私は絵は全く書いておらず、文字しか書いていないのですが・・・
そして、もう一つ、文字を絵のように書く」というので思い浮かぶのが、もっと時代は降っての「コンクリートポエトリー」。
コンクリートポエトリーという詩
コンクリートポエトリーとは、ポエム、そう詩のことです。
直訳すると「具体詩」。
いったいどんなものなのかというと、元来、文字とはある対象を表す3つの要素「形象」「音」「意味」を抽象化したものだと捉え、そのうちの「意味」を排除し、形象、形式にこだわって作られた詩のことです。(ここで「音」という要素は紙の上に表現されているということで関係なくなっているとみなしているようです。)
要するに文字(活字が主です)が用いられてはいるけれど、読む、というより視覚的に感じる詩、といったところでしょうか。
綴られた詩の内容がその文字の配置や形式によってより増幅され、右脳と左脳で感じることができる詩なのかな、という印象です。
そのコンクリートポエトリーの歴史は古くて、17世紀前半にはイングランドのジョージ・ハーバートという人の天使の翼を表現している〝天使の翼”というのがあります。

確かに、翼のように見えないでもないです。
あと19世紀前半の、画家のマリー・ローランサンの恋人だった詩人ギヨーム・アポリネールの「カリグラム」というのがあります。
これは手書きの文字ですね。

そしてこれもアポリネール。エッフェル塔のように見えます。

『カリグラム』所収 1918年
これらオランダ、ドイツなどの西洋の作家たちや、ほぼ時期を同じくしてブラジルで結成されたノイガンドレスという前衛詩のグループなどが、コンクリート・ポエトリーの基礎を作ったようですが、日本でも1950年代にこのコンクリート・ポエトリーの運動がありました。
厳密には、西欧やブラジルで起こっていたこの運動とは別に独自の進化をしコンクリート・ポエトリーの手法に到達していたようなのです。(詳しくはまた別の機会に)
その中で有名なのが北園克衛(きたぞのかつえ)。

詩集『白のアルバム』1929年

「雨のランデ・ブー」から「M e Voici」
黒田維理詩集サムシング・クールより
そして、もう一人が新国誠一(にいくにせいいち)。
新国は60年代には独自に「視覚詩」を創作し、次のような作品を発表しています。

「川または州」1966年
川と州の微妙な文字の形の違いが、色で塗り分けられたかのようになっていて、尚且つその文字の意味の違い通りのような景色に見えて面白いなぁ、って思いました。

「触る」1972年
様々な触感、いや触角を思わせるような「る」の配置に魅入ってしまいます。
観て感じて考える書
このように「葦手書き」や「コンクリート・ポエトリー」の作品を見ていると、文字を扱っているという点では左脳で解釈するけれど、それと同時に右脳で感じて観る、そんな芸術なのではないか、と思います。
そういった観点からすれば、私の漢字書の作品もその流れの中にあると言えるかもしれません。
しかし、これらの葦手書きやコンクリートポエトリーと自作品では大きく違う点があると考えます。
それは自作品では、あえて文字を使って絵のよう書こうとしたり、ある形を意識して配置やデザインをしようとしていないという点です。
私個人の考えとしては、「書」とは、その時その時の想いの発露であり一過性のものだと捉えており、毎回紙を前にその心持ちで筆を運んでいます。(ペンだったり、パステルだったりもしますが)
ただ、コンクリートポエトリーの作家の中でも、日本の新国誠一という作家には二つの点で親近感を抱いています。
まず、新国はデザイナーからスタートしていますが、文字をデザインのように配置して絵のように書くことを否定していた点です。(中にはそのような作品もあるようですが)
私も、漢字を使って絵のように書くことを避けたいと思っています。
しかし、結果的に絵のように見えてしまうと言われるのは、手前味噌ながら「観る書」として制作している観点からすれば成功しているのではないかとも考えます。
そしてもう一点、新国は文字の持つ意味を排除して創作された西洋のコンクリートポエトリーと一線を画し、いくら削ぎ落としても「意味」が残ってしまう「漢字」という文字をあえて用い、意味を感じながら「観る詩」を作ろうとしたところです。
まさしく私も、一つの漢字が意味し、象徴するもので、現代社会やそこに生きる私たち人間の精神世界を表現できたならばと、文章でもなく詩でもなく、ひたすら文字だけを書して作品をつくっているからです。
古代に生きた人間の概念や感覚が見事に抽象化された漢字という記号を、私の脳の中で今一度スライムのように解凍し、現代社会やそこに生きる私たちの精神世界の中に滑り込ませ、そのスライムが纏わりつき浮かび上がってきた形や線を、その脳内のイメージが消えないうちに外の世界(紙の上)に書き留めているのです。
文学でもなく絵画でもない「書」としての表現方法、それが私の作品なのです。
絵のように見える滝沢汀作品たち
ここで、いくつかの私の漢字のみで書いた作品をあげてみたいと思います。

「記憶の化石」は「扉」という字を、大きめの超長鋒(穂先が軸の直径に比してとても長い筆のこと)を持ち紙の上に立ち、ぐるぐる回転するように歩きながら書いた、145cm四方大のかなり大きめ作品です。
昔から化石のアンモナイトに魅力を感じではいたのですが、アンモナイトは殻の中で成長するたびに外に向かって移動し、それまでいた部屋に扉を閉め、前の部屋は空洞となり浮力となるのだそうです。
それを繰り返された跡があの化石の断面なのだと知った時、人の人生と重なり、私の頭の中でこのように「扉」が螺旋になって連なって出てきたのを書き止めたものです。
それも、あたかも人生の歩みを凝縮するかのように、実際、紙の上を一歩一歩、歩きながら扉の字を書いています。
しかし、こうして改めて見てみると、この作品はアンモナイトの形状を模しているようにも見え、ある意味絵のように書いていることになるかもしれませんね。
偉そうに文字を絵のように書くことを避けている、と言いながら失礼致しました(≧∇≦)
そして次も超長鋒を用いて書いた大作です。

これは漢字の「夢」と「現」という二つの漢字を交互に重ねて書いた作品です。
小学2年生まで夢を見たことがなかった(と思い込んでいた)私は、ある朝「私は夢を見た!」と意識した日がありました。
その日から、覚醒している現(うつつ)と現の間には、抜け落ちることなく必ず「夢」が挟まるようになりました。
どちらかというと夢の中で生きている時間が長いのではないかと思われる私の人生を、夢と現の漢字をただひたすらバームクーヘンのように重ねて書きあげた作品です。(コレも紙の上に立って動きながら書いています)


上の2作品は、「象」の字のみを書いています。
アルモノ(それぞれの作品の中にあるぼやんやりとした墨の塊、これもよく見ると象という字になっています)を見た時の、その見え方、捉え方、カタドリ方の、人によって様々に違う状態を、文字通り「象(カタドル)」という文字の書き方の違いで表現したものです。
我ながら絵に見えてきます(笑)

コレは、現代社会に生きる私たちは、目に見えるものから見えないもの、あらゆる恐怖に取り囲まれているという状態を、元々はぐるぐると取り巻く形からできた「回」という漢字をいくつか重ねて表現した作品です。
取り囲んでいるのは、わかりやすい恐怖だけでなく、保護し守るという建前で、厳重に監視の目かも・・・
そんな意味での「We are surrounded」です。

あまたの影像に取り囲まれ、その中に埋没し、何が現実で何が影像(虚)なのか判別しにくくなっている今、またこの現実も何者かに投影された3D影像かもしれない、と思いながら、影の字をいくつも書いた作品。
そして、最後に現時点での最新作は次の作品です。

私たちは膜の存在無しには生きてはゆけない。
生物学的な膜はもちろん、目に見えない膜(バリア)によって心身を守り外とのバランスをとりながら生きている。
時折り、この地球上のあらゆるものを覆い護ってくれている大いなる膜の存在を想像する。
そして、その外側に想いを馳せる時、なぜかいつも身震いしてしまう。
(今や、私たちが生きている時間を含めてのこの空間を四次元空間とするならば、それ自体が一つの膜の中にあるとする「膜宇宙論」という最新の学説もあるのだとか!!)
と、こんな感じで文字(漢字)しか書いていないのに絵に見える作品、「観て感じて考える書」を、今後もしばらくは続けていきたいと思います。
長い記事になりましたが、最後まで読んでいただきありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
