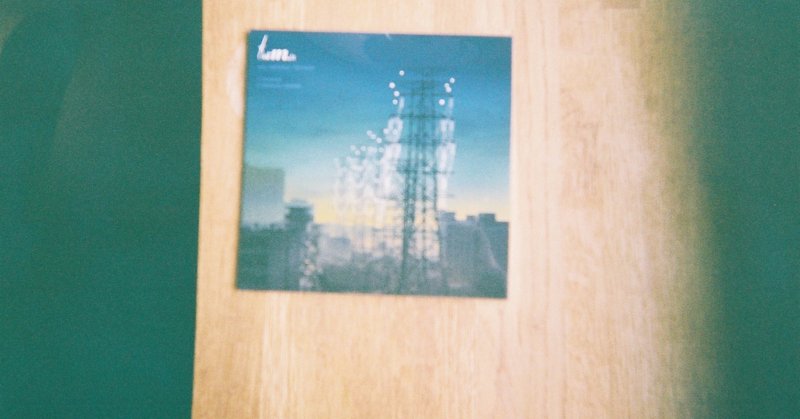
純粋なリスニング体験、2020年の空気、など。石原 洋「formula」レビュー
図らずも2020年を切り取った作品、ある一つの観点として私は捉えられた。
amazonのレビューに非常に興味深い投稿があった。「もともと普通の楽曲として録音していたが、それを喧騒と合わせて長尺のトラックにしたのでは」という指摘だ。まったく異論なし、そんな感じがすると思った。
実際のところは少し違い、石原氏のインタビューでは2年前から本作の構想があり、リスニング体験における「遠さ」をテーマとしてこの曲を作り上げたという。解釈と妄想は紙一重ではあるが、つらつらと書いていきたい。
本作を未聴の方にはなんのこっちゃお前、と言われそうなので軽い説明。ゆらゆら帝国やOGRE YOU ASSHOLEのサウンドプロデューサーを務め、プレイヤーとしてはWHITE HEAVENの活動等、長い視点で見れば日本音楽のキーパーソンとなる人物の23年ぶりの怪作であり、フィールドレコーディングによる街の音が流れ続けながら、バンドサウンドが虚ろに並走する。
2曲42分。雑踏、声、生活の営みが猥雑に流れる後ろで、サイケでメロウな曲が遠く流れる。「後ろ」というのがキモであり、アンビエントに括るにはあまりにぶっきらぼうなミックスだ。都市のノイズと曲がイーブン、いやむしろノイズの方が前面にくるような、時に曲を阻害するような音も問答無用に挟み込まれるほど、かつてないような位置関係を強いている。この街のどこかで甘い曲が流れているが、それがどこから聞こえているのか、私たちは知ることができない。
①純粋なリスニング
twitterで誰かが仰っていたことを思い出した。「ストリーミングで音楽を聴く以上、どんあジャンルであろうとそれは常にアンビエントである」といった旨の内容だ。うーん。分からないようで分かる気がする。
ストリーミングサービスの発達により、24時間前後左右なく、あらゆる最新・古来の音楽にアクセスできてしまう。それは、電車の中でもどこであろうと場所を選ばずに私たちに音楽を届けてくれる。一方で、音楽のBGM化を同時に加速させる(少なくとも私にとっては)。
最近、音楽を聴くのが非常に難しくなった。1枚のアルバムに集中して「音楽のことを考えて聴く」というのが困難な時代になったなあ、と感じる。例えば、アナログレコードのブームもそこから端を発しているのではないだろうか。レコードを買い、プレイヤーにセットして、針を落とし、ひっくり返す。あまりにも情報量が多すぎるこの時代に、私たちは儀式なしには音楽に向き合えなくなってきたのかもしれない。遥か昔(録音技術のない時代)はライブしか音楽を聴く媒体がなかった訳であり、そこにかける集中力は、現代とは自然と異なってくることはと想像に難くない。1枚のアルバムに向きあうには、あまりにも多くて速い時代だ。
前置きが長くなってしまったが、私だって買ったばかりのairpodsを耳にセットして、iphoneの画面に指を落とす。ノイズキャンセリングなんて気の利いたものはないので、電車や車の音など容赦なくガンガン流れ込んでくるわけだが、本作はその感覚に非常に近い。
いよいよ熱を帯びるストリーミングの時代に、アンビエント化してしまったリスニング体験を最初から楽曲に落とし込む、という構造だ。私たちは今、本当に音楽を聞いているのだろうかという問いをそこに感じる。そもそも、完全な無音状態を作って音楽を聴くことは、基本的に無理ではなかろうか。ジョンケージのエピソードに、無音室においても心臓脈打つ肉体が発する「音」から逃れられなかったという旨の出来事があった気がする。この文章を書いている最中も、窓の外で残暑を叫ぶセミの声をバックに聞いているわけで、そもそも純粋なリスニング体験ってなに?と頭を巡らす。
②「遠さ」
冒頭に書いた石原氏における楽曲の「遠さ」とは、例えばブートレグ音源の録音の悪さや、それによって観客の声の方が聞こえてしまうような状態を指すという。自己表現の音楽とはむしろ対極であり、その点で言えばアンビエント的だが、バンド(肉体的)としてのサウンドを一回経由して、そこにたどり着こうとするところが面白い。シンセサイザーで「フワ〜」とした音を流すのではなく、一度迂回する方法論は一種の幽体離脱、幽霊的な感覚と言い換えることができるだろうか。都市の雑音からバンドが浮かび上がり消えていく。遠く昔にあった情念、その残滓だけが残ってしまったような。そこにはかつてのエゴがあったかもしれないが、現代を生きる私たちにその目線は向けられていないことが気持ち悪くて快楽的だ。坂本慎太郎の2ndアルバム「ナマで踊ろう」における「人類滅亡後の音楽」というテーマとも通ずる。
なんにでもvaporwaveに結びつけることに、自分でも食傷気味なのだけれどやはり避けて通れない。あれも幽霊的な音楽だ。かつてある時代に放出された意思のエネルギーが、そのまま現代に取り残されてしまったことによる物悲しさ、郷愁。
vaporwaveとの関連についてはyoutuberの「みのミュージック」が既に指摘しており、ここで面白い関連が出てくる。彼は「ABBAが隣の部屋から聞こえてくるmixや、無人のショッピングモールでTOTOがかかっているmixがyoutubeであがっており、それに近い感覚がある」と述べている。
私個人の話になるが、深夜に隣の部屋からテレビの音が薄っすら聞こえてくるのが好きだった。今でもラジオを最小音量にして眠りにつくことがある。会話のアタック音だけが聞こえて、なにやら話をしている、という情報量に留まっている感じが、不思議な恍惚と結びついていた。これもまた石原氏の言う「遠さ」なのだろうか。彼の思想と、vaporwaveの流れ、私の感覚がリンクした。そして、同じようにニッチな魅力にとりつかれている人は思いの外たくさんいるらしい。確かに「遠い音楽」は幽霊的な魅力がある。
③思わぬ副産物
上述にもあるように、この曲は2年前から構想されており、「遠さ」へのアプローチについてはそれ以前からあった作品だ。しかし、本作の都市のノイズは思わぬ副産物となった。
コロナ禍を経由した後に聞くそのノイズは、今そこにあるノイズとは違う。せわしなく人が行き交い、言葉を酌み交わし、なによりそれらにの行為に気負いなく生活が営まれている情景がパッケージされている、図らずもだ。
vaporwaveが80~90年代の幽霊的な残滓であれば、この作品は2020年以前の空気の残り香だ。それは手厳しくも、私たちに現実を見ることを強いる。vaporwaveの資本主義を懐古する逃避的・享楽的な懐かしさではない。懐かしむほど昔ではないが「時代が変わってしまった」という事実を突きつけて、逃がしてはくれない。
現代のリスニング体験が強いるアンビエントの証左。幽霊化したロックミュージックのエゴ。逃避を許さぬ、もはや過去のものとなった都市の営み。あらゆる角度から2020年と言う時代を切り取っている。
あなたはどう感じましたか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
