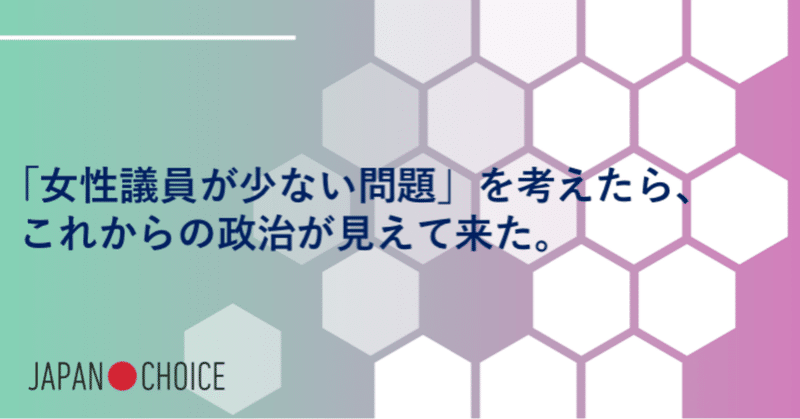
「女性議員が少ない問題」を考えたら、これからの政治が見えて来た。
1. 女性議員が圧倒的に少ないという現状
世界経済フォーラムが発表するジェンダーギャップ指数2018で、日本の順位は149カ国中110位。分野別では政治分野で125位と特に低く、女性議員が少ないことが、日本のジェンダー平等の足を引っ張ってしまっています。

日本では、2018年5月に「候補者男女均等法」が成立し、あくまで各政党の努力義務ではあるものの、候補者を男女均等にすることが求められることになりました。今回の参院選は施行後初めての国政選挙になります。注目度の高さから、各党の女性候補者擁立の様子についてもメディアで報じられているのをみなさんもご覧になったのではないでしょうか。実際に、今回の参院選の女性候補者の割合は男女均等ではないものの28.1%と過去最高を更新しました。
一方で、候補者の男女均等だけでは女性議員の比率は改善できないのではないかという意見があります。この背景には、過去の選挙において,候補者段階での女性の割合と,選挙によって当選した者に占める女性の割合では、後者の方が著しく低い事実があります。女性候補者を増やすだけで果たして十分なのか、十分でないならば何をしていくべきなのかという問いが検討されるべきではないでしょうか。
そこで、この記事では、女性候補者が議員になるのにどういったハードルがあるのか、また女性議員は本当に必要なのか、ということをジェンダーの観点から整理してみました。
2. 女性は政治家としての素質がないのか?
日本で女性の政治家が少ないという議論になると、必ず聞くのが「差別ではない、女性に実力がないだけだ」という意見です。
本当に「実力がないだけ」なのでしょうか。そもそも、政治家として「実力がある」とは何を意味するのでしょうか。その際、ジェンダーという要素はどのように作用しうるのでしょうか。
2.1 「ジェンダーステレオタイプ」
ジェンダーステレオタイプとは、社会的性「ジェンダー」に基づいた固定観念です。
例えば「女性は家事育児が得意」、「男性が泣くなんて男らしくない」などという言葉を聞いたことはありませんか。いずれも生物学的な根拠なしに、社会的に構築された言葉です。
ジェンダーステレオタイプはしばしば二項対立で表現されます。よく挙げられるものを表に整理してみました。

では次に、「政治家に必要な素質」として思いつくものを挙げてみましょう。
例えば、『職業としての政治家』において、マックス・ヴェーバーは、政治家の素質として「情熱・責任感・判断力」を挙げています。多くの人もこのようなイメージを持っているのではないでしょうか。
しかし、このいずれの素質もどちらかというと「男性らしさ」に結びつきがちです。情熱を持っているということは、「強い」意思を持っているということであり、責任感があるというのは「自立」した「リーダー」であるということ、判断力というのは「理性的に」決断できるということ、とそれぞれ男性に当てはまるステレオタイプと関係が深いからです。
対して、「女性らしさ」に挙げられる要素はむしろその素質とは正反対のように私には思えます。
つまり、ジェンダーステレオタイプから描かれる女性像と,政治家とはかくあるべきとされる理想像が非常にマッチしにくく、したがって女性は政治の世界に参画しづらいと考えることができます。
例えば、女性候補者が「強いリーダー」ではない場合、政治家の素質を満たさないと言われますが、逆に女性候補者が「強いリーダー」であった場合は、彼女は「女性らしさ」の特徴と一致しないために、「攻撃的すぎる」とみなされ批判される、といった具合に。女性候補者は「政治家として強くあるべきだが、女性なので強すぎてもいけない、ほどほどに」というダブル・バインドに苦しめられていると分析できます。
2.2. ジェンダーステレオタイプと政策の関係
次に、ジェンダーステレオタイプと政策の関係を見てみましょう。政策にも「男性らしい」と思われている政策と「女性らしい」と思われている政策があります。(1)先ほど考えた特徴をもとに、分野を分類してみましょう。
例えば、「女性は母親として子供を育てる」という性別役割分業観や、「優しい、同情的」といったジェンダーステレオタイプがあると、保育や福祉といった分野と親和性が高いように思えるのではないでしょうか。また、「男は強くあるべき」、「男が女性・子どもを守る」といったステレオタイプを持っていると、安全保障は「男性らしい」分野であると思えるでしょう。

現代の政治において、「男性らしい」政策と「女性らしい」政策はどちらが大きな争点になりやすいでしょうか?その答えは、個人の価値観によりますが、状況次第で、候補者のジェンダーは、国民からその候補者への注目度に影響することがあるはずです。
加えて、女性候補者が「男性らしい」政策を主張した時には、それはジェンダーステレオタイプに合致しないと批判されることがあります。例えば、2016年アメリカ大統領選挙に出馬したヒラリー・クリントン氏は外交、安全保障に造詣が深く、実際の選挙活動でもこういった政策について自信あふれる主張をしていたので、こういった点が「女性らしさ」に一致せず、彼女が落選した理由の一つになったという考え方もできます。
とはいえ、何かを決断する時に、ステレオタイプは確かに便利です。候補者の情報をショートカットする手段として、無意識のうちにジェンダーに基づいたステレオタイプを用いて判断してしまうのは、ある意味で仕方がないと思います。
だからこそ、有権者がそういった**ジェンダーステレオタイプに決定を委ねることを避けるために、メディアが性別に関わらず候補者の情報を量・質共にフェアに報道することが求められています。
3. マスメディアが女性候補者の当選を妨げている?
しかし、現状ではメディアが女性候補者を余計に見えにくくしています。ある調査では,女性と男性の候補者に対する報道の量を比較すると、女性候補者の報道量の方が圧倒的に少ないというデータがあります。(2)
なぜでしょうか?

一つの理由として、メディアとしてはより有利な候補者を多く報道したいからという背景が伺えます(3)。 有利な候補者の筆頭として,現職の候補者が挙げられます。そうなると現状女性の議員は数少ないことから、女性候補者が報道されにくいということになってしまいます。
*なお、報道量を現職の女性候補と男性候補者で比較すればほとんど違いはないことが報告されています(3)。
そして、候補者がメディアで報道されればされるほど、当選確率も高くなるという研究もあります(4)。メディアでの報道量が少ない女性候補者は、当然、当選確率も落ちます。この一連のメカニズムが女性候補者を不利にしているのです。
また、報道の量だけでなく内容を見ても、女性候補者は男性候補者と比較して容姿や家族(〇〇の妻)といった特徴について報道されることが多いと感じます。「美人候補者」などといった報道の仕方は、「候補者」としてではなく「消費されるもの」として客体化しているという点で、フェアな報道とは言えないと私は思います。
有利な現職候補者のみを報道すること、性別によって違った報道の仕方をすることがメディアの役割ではありません。「メディアには民主主義においてすべての社会集団を正確に代表する責任がある」(5)ということを念頭に置いて、ステレオタイプから解放され、多様な社会集団(女性、LGBTなど)を報道するべきです。
4. 女性議員は必要なのか?
ここまで、ジェンダーステレオタイプやメディアの構造が女性候補者を不利にしているということを述べました。
最後に、結局のところ女性議員はなぜ必要なのかという問いについて考えたいと思います。
「男性の政治家だけでは良い子育て政策ができない」という声があります。しかし、この言説には、「子育ては女性がするもの」という偏見が隠れているようにも思えます。
当然ながら、女性といっても人それぞれ違った人生を生きています。子育てをしている女性もいれば、していない女性もいます。よって、女性が政治に進出する意味を、「女性の視点」と単純に一括りにするのは危険です。それは、少数の女性議員が社会の女性全員の意見を代表するということは不可能だということを意味します。(7)
これまで、「女性の視点での政治」は、「女性活躍」や「女性の子育てとキャリア両立」といった文脈で語られることがほとんどでした。しかし、昨今では、企業のハラスメントへの対策を義務化するハラスメント規制法の成立、強制性交等罪の脅迫・暴行要件についての国会での議論、緊急避妊薬のオンライン処方容認など、女性のセクシャルヘルス・ライツについても政治の役割が多く指摘され、法制度を整える動きも多くなってきました。
このような現代において、社会全体にとって重要な課題を見逃さずに、世の中の多くの女性の意見を代表した政治が行われることは非常に重要だと考えます。女性議員の数が増えることを通して、一括りにされがちな「女性の視点」の多様性が担保され、様々な論点や政策が国会で議論されるべきです。それは、女性のためだけでなく、政治が広く社会を捉えるために役に立つはずです(6)。
5. 最後に:女性議員が増えていく重要性
この記事では、無意識なジェンダーステレオタイプ、そしてメディアの構造により、女性候補者が不利になっている現状、そして女性議員が必要な理由を整理しました。
ぱっとテレビをつけた時に、国会中継が流れ、その中で男性が圧倒的マジョリティだった場合、それを見た子供たちはどういった印象を受けるでしょうか。「政治とは男のもの」こういった刷り込みを与えられてしまい、女児は政治から遠ざかってしまうのではないでしょうか。
ニュースを読む、政治について議論するといった日常的な行動の男女差が、やがて政治に対する関心度の違い、知識量の差となり、それが政治における男女の力の不均衡の原因になるのです。(8)
女性議員が一定数いることは、これからの社会に不可欠だと思いませんか?
女性に限らず、国会がより多様な価値観を代表する場になることを願います。

高島菜芭の個人Twitterはこちら:https://twitter.com/nxxx61
GenesisのTwitterはこちら: https://twitter.com/Genesis_for_All
★この記事はJAPAN CHOICEとの連動して選挙と政治を多方面から分析したシリーズです。ぜひ他のサービスもご利用ください。
★本サービスの開発・運用はクラウドファンディングで支えられています。下の画像より支援ページにとぶことができます。応援してくださると幸いです。
*参考文献 (1)Herrnson et al. 2003, Women Running “as Women”: Candidate Gender, Campaign Issues, and Voter-Targeting Strategies(2)Kittilson, Miki C., and Kim Fridkin. 2008. “Gender, Candidate Portrayals and Election Campaigns: A Comparative Perspective.” Politics & Gender 4 (3): 371–98.(3)Lühiste, M. & Banducci, S. (2016) Invisible Women? Comparing Candidates’ News Coverage in Europe. Politics & Gender. 12 (02), 223–253.(4)Goldenberg, Edie N., and Michael W. Traugott. 1987. “Mass Media Effects on Recognizing and Rating Candidates in U.S. Senate Elections.” In Campaigns in the News: Mass Media and Congressional Elections, ed. Jan Pons Vermeer. New York: Greenwood Press, 109–33.(5)Scammell and Semetko, 2000 Media, Journalism and Democracy. Aldershot: Ashgate.(6)Burns, Nancy, Kay Lehman Schlozman, and Sidney Verba. 2001. The Private Roots of Public Action: Gender, Equality, and Political Participation. Cambridge: Harvard University Press.(7)Phillips 1995, 1998 The Politics of Presence. New York: Oxford University Press.(8)Wolbrecht and Campbell, 2007 See Jane Run: Women Politicians as Role Models for Adolescents
<ハラスメント規制法の成立、強制性交等罪の脅迫・暴行要件についての国会での議論、緊急避妊薬のオンライン処方容認などについて取り扱った参考記事>・列国議会同盟https://ipu.org/resources/publications/infographics/2019-03/women-in-politics-2019
・東京新聞 https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201905/CK2019052902000271.html
・毎日新聞 https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20190611/pol/00m/010/009000c ・毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20190610/k00/00m/040/263000c
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?


