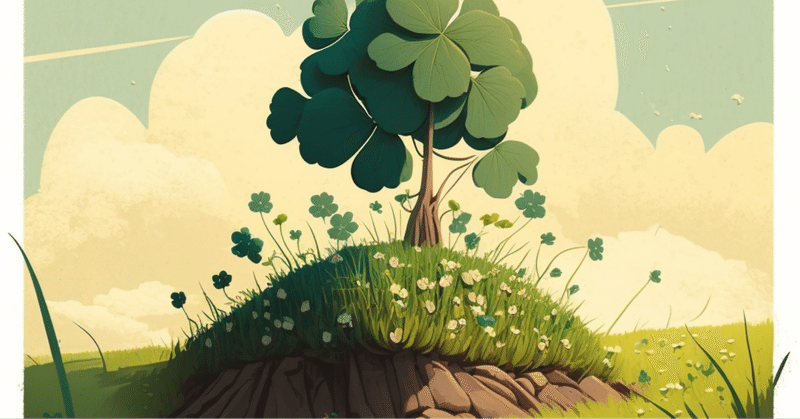
樹を植えるように生きていく
私は約20年前に横浜から千葉県の南房総にある小さな田舎町に新規就農を目指して移住した。正直、自分でもうまくいくとは思っていなかったけど後悔してもやり直せる年齢のうちに一度挑戦してみたかったのだ。
しかし当時、都会から田舎に移住するなんて考えは大変クレイジーなことのように思われていた。
「便利な都会を出て不便な田舎に住みたいなんて思う人間はいない」
そういう時代だった。何度もはっきりといろいろな人に言われた。
当然移住先の人たちからの信用なんてものはないので好奇と不審の混じった視線を受ける毎日に自分の決断の甘さを後悔してやっぱり実家に帰ろうと涙したことも少なくない。
ぶっちゃけてしまえば田舎は小さな異国だ
まず最初、方言が強すぎて地元の人が何を話しているかわからなかった。
次にその土地のルールも以前住んでいた場所とまったく違うことに気づかなかった。
同じ日本人なのにどうしてわかってくれないんだと悔しく思っていたけれど
もしこれが外国で暮らすことに当てはめて考えてみたら成程と納得できる
外国で日本の常識が通じるかと言われれば正直それは難しいし、その土地のことをよく知ったうえで時間をかけて現地の人とコミュニケーションを取ろうと試行錯誤するだろう。
例え同じ国に住んでいたとしても、どんなところで生きていても人はお互いを少しずつ少しずつしか理解できない。
移住とはまるで植樹のようだと思った。
何年、何十年先にどうなっているのかまったくわからないけれど
それでも時間をかけてここで生きていくのだと私は覚悟という小さな苗木を自分の心に植えたのだ。
その後あまりにも頼りないのになんとかなるだろうと楽観的な私を見ていて不安に思ったり、心配して徐々に声をかけてくれる人が少しずつ現れて
その紹介で知り合った役場や農業関係の諸先輩方にいろいろ教えて貰いながら私はこの小さな田舎町に少しずつ順応していった。
昨今の物騒な世の中で知らない人を受け入れるのは勇気がいる行為だと思う。
また理解できずにぶつかり合って口も聞きたくないほど関係が拗れることもあるだろう。
私はそれでもいいと思う。
すべての人と仲良くなんてできない。
だけど誰か一人でも受け入れてくれたことで、知らない土地でホッと息がしやすくなる。生きやすくなる。
それだけで幸せによく眠れる日もあるのだ。
2019年に南房総は台風によって甚大な被害を受けた。
私の住む地域でも大きな被害を受け、電気や携帯電話も一切使えなくなったときにまず最初に自分や家族の身の安全を確保してから町内・区内の人達が集まって道路が通れるように倒れた木や飛んできた瓦礫をできる範囲で自分たちで撤去した。
「道路が通れなければもし誰かが具合が悪くなっても救急車を呼べない、病院にも連れていけない。物資も届かないし、電気の復旧作業の車も入ってこれない。だから自分の家よりも優先して行わなければいけないんだよ」と教わった。
お互いを心配しあいながらもみんなできることを必死にやって自分たちの町を守ろうとしていた。
とても大変な時だったけど「ここで生きてきてよかった」と私はしみじみと思っていた。
私が思っていたよりも私が植えた木は大きく育っていたようだ。
今はインターネットの普及によってどこに住んでもそれほど困らない。2014年に国から地方創生が打ち出され、移住による企業や就業支援が行われるようになり、自治体からも移住相談や支援など積極的に行われ、コロナ禍以降は二拠点・多拠点生活をする人たちも増えてきた。
「不便な田舎にあえて住みたい」当たり前にそういえる時代になった。
どこでも住める時代になってきているのだ。
新しい場所で生きていくのは簡単なことではない。
合わなくて別の場所にいくことももちろんあっていい。
でも#どこでも住める からこそ「ここで暮らせてよかった」と思える場所に焦らず時間をかけて育ててほしい、と私はそう思っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
