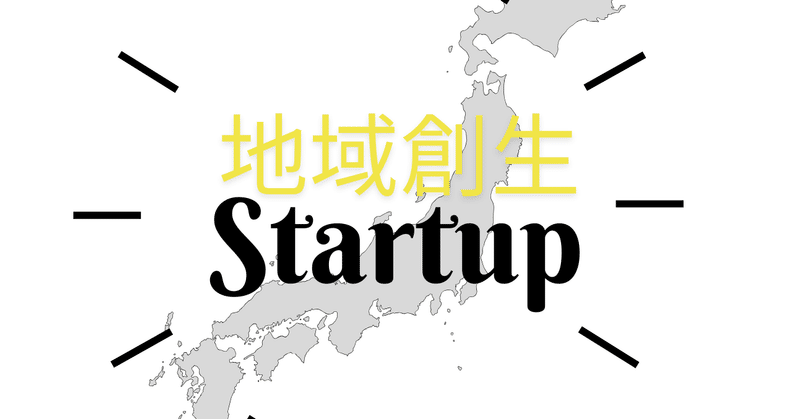
地域創生の型No.1スタートアップによる地域創生モデル
2005年にシンクタンクに入社して以来、スタートアップ支援施策に携わり全国のスタートアップ支援を見てきて地域創生に向けた処方箋を簡単ではありますがまとめました。
地域創生を目指す地域の皆さま、目先の税収を増やす施策はもちろん重要ですが、長い目で見れば、魅力的な仕事があることこそ若者を惹きつけまちの賑わいを取り戻す事につながると思いませんか。そのためにも、その地域の新産業たりうるスタートアップを創出し育て地域と共に発展してもらうことが重要だと思いませんか。
今取るべき策は「スタートアップしかない」と言っても過言ではない。魅力的な地域を次世代に繋ぐために、今その視座を上げ、本気で取り組んでみませんか。
スタートアップ支援のノウハウを蓄積せよ~各地で広がる車輪の再発明~
スタートアップエコシステム拠点やスタートアップ5カ年計画など政府方針が打ち出され全国各地で新たなスタートアップ支援の取り組みが始まっています。既に行われてきた地域にはベースとなる知識・ノウハウや経験したことによる学びがあるわけですが、それらは他の地域に共有されることなく、またゼロから発明されることになります。この車輪の再発明に際し所謂コンサルが介在するわけですが、スタートアップの背景を理解しないコンサルが表面的な調査で綺麗にまとめてくるだけなので、本質をとらえたものにならない。新たに取り組む地域や担当者に向けて、これまで得られた知識や経験して得たことが蓄積され学び合える場が必要です。

このような思想のもと、起業家やVC・CVCの皆さんと共に国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)さんのもとでICTメンタープラットフォームを2011年に立ち上げ、全国のスタートアップエコシステムと連携を図り続けています。
先ずは、先人から学び、最低限の知識をもって、その地域に合った最善の策を打って頂きたい。車輪の再発明に貴重な時間とコストを掛けることなく、成果の最大化を図っていただきたいと思っています。
地域発スタートアップ創出に向け「新産業創出力」を高めよ
次に、各地で車輪の再発明が行われないためにも、これまでの経験から得られた最低限の処方箋(フレームワーク)を示す必要があると思っています。それが地域からスタートアップが生まれるための4つの視点「新産業創出力」です。
大きくは、地域から起業家が「生まれるために必要な要素」と地域に起業家が「根付くために必要な要素」から構成されます。
①起業家の源泉
地域から起業家が生まれるためには、①起業家の源泉となる大学・高専などの教育機関の存在が重要です。こうした源泉の存在を把握できているか?ネットワークを構築し、源泉から常に沸き上がる状況が確立されているのか?確認する必要があります。
②目線の向上
次に、②目線の向上です。①の源泉があり、常に湧き出していたとしても、彼ら彼女らが社会課題の解決やよりよい社会に向け自ら主体的に動こうとするきっかけがあることも重要です。よく、起業家の親は事業家であることが多かったり、周りに起業家が多いと「自分にもできる」と思って起業したという話があるように、ロールモデルを提示することで起業家が生まれる環境ができると思います。
ここまでは、地域から起業家が生まれるために必要な2つの視点になります。ひと昔前は「この地域には起業したい人なんていない」というのが課題だったので、この2つの要素は重要でした。

③シードの資金調達手段
地域から起業する方々が出てくるにつれ聞かれるようになったのが「起業家が東京に出て行ってしまう問題」でした。そこで大事になるのが地域に起業家が根付くために必要な要素です。なぜ、スタートアップは東京に行かなくてはならないのか?その理由の1つは③シードの資金調達手段が無く、シードラウンドでのリード投資家を探しに東京に行かなくてはならない、ということです。そのほかにも販路拡大のしやすさや人材獲得のしやすさなどの理由はあると思いますが、まだまだリード投資家を探すために東京に行く、という事が行われています。ないなら連れてくるか作る、という事です。
④わざわざそこにいる理由
最後に、④わざわざそこにいる理由です。(個人的にはそもそもここが一番重要だと思ってます)そもそも、ゴールは何でしょうか?

日本全国でシリコンバレーを目指しても無理なわけです。わざわざその地域に残る理由はなにか?まずは地域の強みを洗い出すことが必要です。こう言うと「うちは自然が豊かで山や川があります。」とおっしゃる地域が多いのですが、7、8割方そんな地域ばかりです。そういう事ではなくて、地場産業や地域中核企業は重要な地域の強みですので、彼らのDX推進やオープンイノベーション環境を整備し、彼らと協働するスタートアップを育成することも1つの手段だと思います。また、最近改めて知の拠点たる大学の存在は貴重だと思っています。米国のスタートアップコミュニティも背景に大学の存在があることが明らかです。彼らが持っている研究開発シーズを生かし、新たな産業の創出を目指すことが求められていると考えており、先述のNICT ICTメンタープラットフォームでもディープテック領域にフォーカスしていますし、当社では、各地域の強みや特徴を生かした産業クラスターを構築していきたいと考えています。
いずれにしても、こうしたフレームワークと4つの共通言語をベースに各地で切磋琢磨できる環境があり、知見が蓄積され、取組が向上していくことが重要です。
参考)海外のスタートアップ拠点
海外のスタートアップ施策についても触れておきます。J-STARTUPのお手本であるFRNCH TECHは2013年から推進されました。国内13都市を重点拠点「フレンチテック・シティ」に指定し、更に38のコミュニティを巻き込み地域分散型産業クラスタの形成を推進。重点分野として、HealthTech、IoT製造業、スポーツ、FinTech、小売り、FoodTech、EdTech、CleanTechモビリティ、セキュリティの9分野を指定しました。この地域は#●●Techといった特徴を出していました。10年が経過し、ユニコーン企業25社を輩出しているそうです。

少し話がずれるのでまたの機会に書きたいですが、地域創生に向けてドイツとの比較で書かれたこちらのコラムもとても参考になりましたので共有します。
参考)地域発スタートアップ事例
地域発スタートアップとしては、地域課題解決型や地域の魅力創出型、大学の研究開発シーズ型などありますが、分かりやすいものを3つ紹介します。
1.北海道 ZEROSPEC 自動発注配送管理システム「GoNOW」
野外用灯油タンクが当たり前の雪国では、これまではオイルの残量が分からないまま、従業員の経験と勘を頼りに巡回し、配送の無駄が発生していた。
ふた部分にIoTセンサーを設置することで残量が見え、配送頻度と配送ルートの自動提案により、配送回数を約1/2に効率化することが可能に。
雪国にしかない課題と着眼点により事業を拡大させている企業です。
2.富山県 笑農和株式会社 水稲農家向け水管理システム「Paditch」
水稲農家では高齢化や担い手不足が深刻な課題となっており、管理圃場規模の拡大により作業負荷やガソリンコストも増加しつつあった。水管理に伴う作業負荷80%軽減、最大で「16.4%」収量増量(10aあたり平均収量)を実現。
3.横須賀市 N-Sports tracking Lab 合同会社 次世代スポーツエンタメ「HAWAKCAST」
ヨットやサーフィンなどのマリンスポーツはリアルタイムでの観戦が難しく、スポーツの魅力がなかなか伝わらなかった。また、運営側もタイム測定等人を配置するコストや負荷がかかっていた。同社技術及びサービスによりマリンスポーツの魅力最大化され、海外含む国際大会での利用実績多数。
マリンスポーツが盛んな横須賀エリアならではの企業です。
さいごに
長い目で見れば、魅力的な仕事があることこそ若者を惹きつけまちの賑わいを取り戻す事につながります。そのためにも、その地域の新産業たりうるスタートアップを創出し育て地域と共に発展してもらうことが重要です。
我々はその実現に向け、地域のオープンイノベーションプログラム「クアトロヘリックスキャンプ」を開催しております。宜しければご覧ください。
また、社会課題解決型5方良しスタートアップと全国の熱い自治体職員の出会いの場「7minutes」も開催しております。登壇希望のスタートアップと自治体職員の皆さまも募集しております。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
