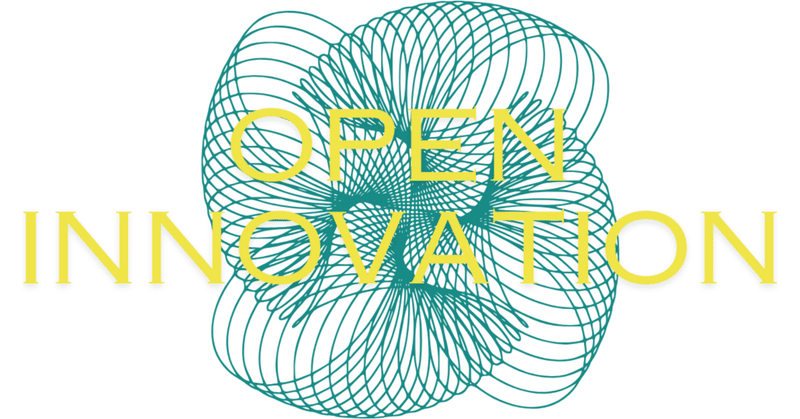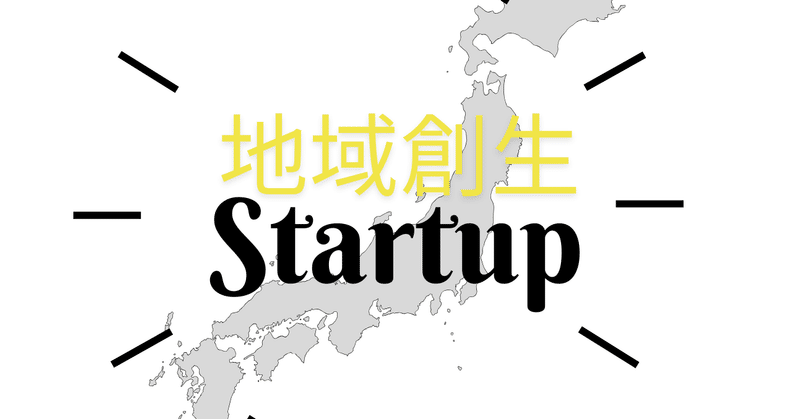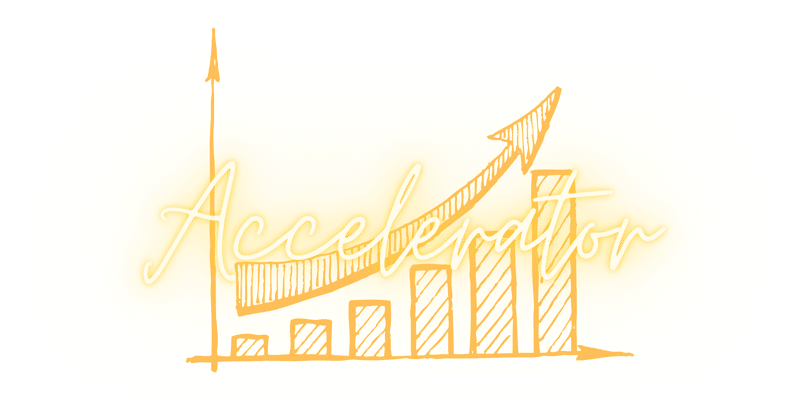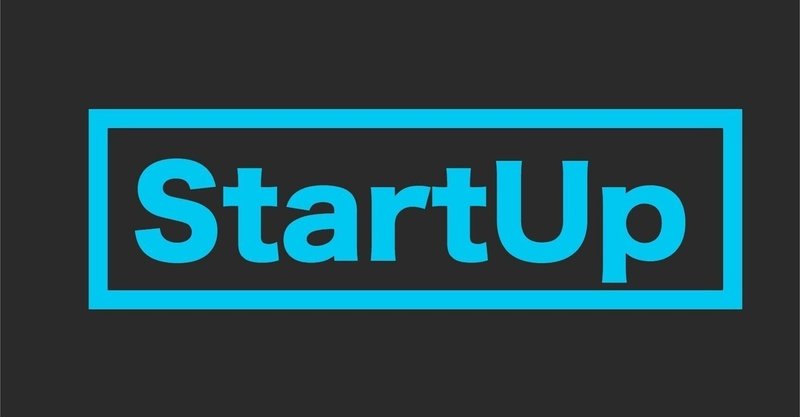記事一覧
地域創生の型No.2 地域のオープンイノベーション
2005年にシンクタンクに入社して以来、スタートアップ支援施策に携わり全国のスタートアップ支援を見てきて地域創生に向けた処方箋を簡単ではありますがまとめました。地域創生の型No.2は地域のオープンイノベーションです。
①地域からスタートアップが続々生まれ、②地域に根付いてもらうための型「新産業創出力」については、地域創生の型No.1スタートアップによる地方創生モデルに書かせていただきました。スタ
地域創生の型No.1スタートアップによる地域創生モデル
2005年にシンクタンクに入社して以来、スタートアップ支援施策に携わり全国のスタートアップ支援を見てきて地域創生に向けた処方箋を簡単ではありますがまとめました。
地域創生を目指す地域の皆さま、目先の税収を増やす施策はもちろん重要ですが、長い目で見れば、魅力的な仕事があることこそ若者を惹きつけまちの賑わいを取り戻す事につながると思いませんか。そのためにも、その地域の新産業たりうるスタートアップを創出
知っているようで知らないキーワード No.2「アクセラレータ」
最近では企業のアクセラレータブームも一段落し自治体など公的機関がアクセラレータを始める動きが活発になってきているように思います。そもそもアクセラレータとは何かを知らずにやっていらっしゃるのかな?と思うようなケースも出てきており、「アクセラ疲れ」「PoC疲れ」とも言われて久しいので今回はアクセラレータを簡単にご説明します。
本noteはスタートアップ支援やオープンイノベーションの担当になったばかりの
知っているようで知らないキーワードNo.1「スタートアップ」って何ですか?
先日、ピッチイベントで登壇企業から「スタートアップって何ですか?」とご質問を頂き、スタートアップの共通認識が無いことに気が付きました。
民間企業はもちろん国や自治体・大学もスタートアップ支援やオープンイノベーションに乗り出して随分経ちますので、充分理解している方も多いのですが、定義が曖昧なのでお互いの共通言語になっておらず、その結果、ちぐはぐなプログラムや支援策を展開しお互いに無駄な時間を過ごす結