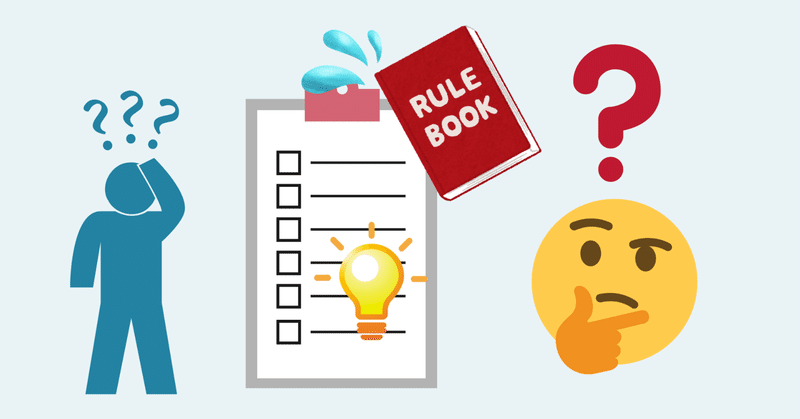
一括表示のルール
一括表示について何度か書いてきましたが、今回はその基本になる「一括表示のルール」について取り上げます。
ルールも人間が決めることですから、いろいろな判断によって次第に整えられていく事になります。新旧で表示の仕方、内容、追加や削除、その他が変化することも出てきます。ですが、多くの人が口にするものが対象になっていますので、違反した場合は罰則が科せられるのは仕方のないこと。現在の表示のルールは令和2年4月1日から施行されています。
①表示する文字の大きさが定められています。通常は8ポイント以上の文字が必要ですが、表示できる面積が小さい(150平方センチメートル以下)場合は5.5ポイント以上が必要です。
②表示責任者の氏名を記載します。製造者、加工者、輸入者、販売者などがこれに当たります。
③製造者は、営業者名を記載します。この場合、法人で許可を受けている場合は法人名、個人で許可を受けている場合は個人名の記載が必要です。屋号だけの記載は違反とみなされます。
④原材料については原材料と添加物を分けたうえで、重量が多い順に名称が並ぶことになっています。添加物については物質名を記載しますが、名称と用途の両方の記載が必要なものもあります。1、甘味料 2、着色料 3、保存料 4、増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料 5、酸化防止剤 6、発色剤 7、漂白剤 8、防かび剤又は防ばい剤例)の8種類が該当して、例えば「甘味料(スクラロース) 、保存料(ソルビン酸)」といった表示が必要です。
⑤添加物の場合は上記に加えて、原則として使用した全ての食品添加物を「物質名」で表示しなければなりません。ただし、簡略名や類別名を使用しても構わない例も存在します。
⑥添加物の場合、さらに「使用目的の一括名として表示できるもの」という例があります。また、表示しなくてよいといった例も存在します。とはいっても、着色料や甘味料といった五感に関するものには、そのような記載の省略は免除されていませんので、表示が必要です。
⑦期限については「消費期限」と「賞味期限」の2種類の期限がありますが、両者は明確に区別されています。消費期限は、腐敗などが起きて品質の劣化により安全でなくなる危険性が生じることがないと考えられる期限。賞味期限は、期待されるすべての品質が劣化せずに保持される可能な期限ということになります。大雑把にいうと、おいしく食べられるのが賞味期限、痛む前に食べましょうというのが消費期限、そんなところでしょう。
⑧保存方法は未開封の状態での保存の仕方が表示されます。開封後の保存方法については、一括表示の枠外に記載されます。
⑨これらの表示は、外食や出前の食品については省略してよいことになっています。量り売りやばら売りなどの場合も同様です。他にも、店頭販売のように顧客の目の前で食品の製造や加工を行なう屋台のような場合も、省略してよい項目があります。
こういった表示のルールを詳しく見ていくと、食品ごとに様々なルールが必要になってきます。これらを商品として扱う業者にとっては絶対に必要なことです。消費者にとっても、知っておくことでずいぶんと参考になる情報ではないでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
