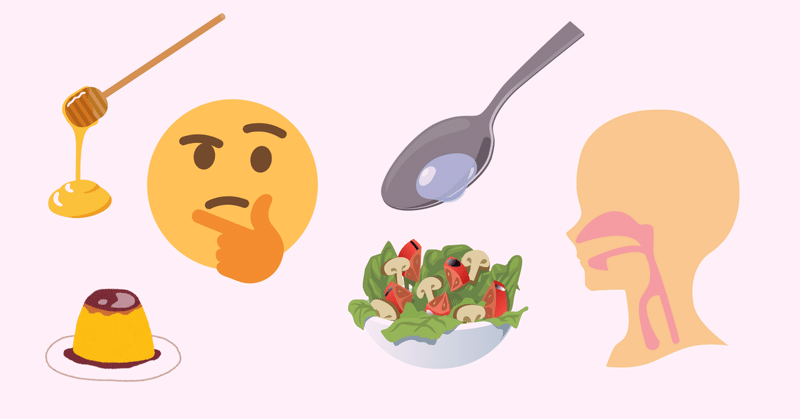
増粘多糖類について、もう少し・・・
今回は増粘多糖類について、もう少し詳しく見ていくことにします。
まず、増粘多糖類っていったいどんなものなのかですね。これは、多糖類ですから基本的に水溶性です。そして、水に溶けたときにゲル化したり粘性を示したりする性質を持つ、複数の糖からなる物質の総称です。
総称ですから、いくつかの種類があるという事ですね。そして、それぞれにその粘性の特徴や性質が違ってきます。食品を加工する時に添加する増粘多糖類の選択は、その食品の性状や増粘多糖類自身の性質などを考慮して行われます(この辺りは、最後の方でもう一度取り上げます)。
増粘多糖類の働きとしては、歯ざわりや舌ざわり、さらにはのどごしなどの食感を調節するするというものがありますが、なによりも”とろみ”をつけて食べやすくしたり、食品の形を安定化させたりする働きが重要です。したがって、その利用も広い範囲で行われていて、菓子類、惣菜類、介護関連の食事などに及びます。
では、その増粘多糖類の種類ですが、主だったものを挙げてみます。ペクチンやゼラチンといった名前はご存じでしょう。
まずはペクチンです。リンゴ、そしてミカンなどの柑橘類などの果皮から抽出されます。古くからジャムのゲル化に用いられてきましたが、最近では酸性乳飲料のたんぱく質の安定剤といった使用もされています。使用例としては、プリンのような菓子類、ヨーグルトなどの乳酸飲料などです。
続いてゼラチンです。牛や豚といった動物由来になります。骨や皮といったところに含まれるコラーゲンの繊維から得られるたんぱく質です。水分をしっかりと掴まえたうえでゲル化しますね。熱を加えると溶けて、冷めてくると固まってくるという、熱による可逆性のゲルを作ります。
次はキサンタンガムです。これは、私は初めての物質名でした。細菌の中にはキサントモナス属というグループがあるのですが、このグループの菌が発酵によって作る増粘多糖類物質です。冷水でも溶けるという性質があり、また優れた耐塩性、耐酸性をもっています。他の素材との組み合わせも含めて、ドレッシング類やタレ類など、多くの食品に用いられています。
カラギナン、これも初めて知りました。海藻類の中でも主に紅藻類から抽出された増粘多糖類になります。元になる紅藻類の種類や抽出の方法によって多少性質が変わるそうですが、ソース類の粘性であったり、ハムやゼリーなどの弾力性を加えたりするところで使用されています。
ガラクトマンナン類というものもありました。これは、さまざまなマメ科植物の種子に由来します。構造としてはマンノースとガラクトースという2種類の糖からできていて、両者の比率の違いによって、グァーガム、タラガム、ローストビーンガムなどの名前がついていて、それぞれが違った性質を示します。
この他にも多数の増粘多糖類がありますが、ガラクトマンナン類のようにグループで捉えるか、それとも種類として別々に捉えるかで変わってくる場合もあるようです。
では、これらの種類をどのようにして選ぶかですが、増粘多糖類としてどのような性質をとるか、使用する食品の性質はどうか、製造するときにうまく使えるかどうか、加えて経済的な理由などによって変わってくるそうです。
最近では、以上の内容に加えて増粘多糖類自身が持つ性質にもクローズアップされるようになりました。
たとえば、主に高齢者を対象にした嚥下が困難な人向けの食品としてとろみをつける働き、食物繊維としての便通改善効果や糖質・脂質の代謝にかかわる働きなども期待されるようになってきています。なかにはタマリンドシードガム(今回名前は出しませんでしたが)という増粘多糖類のように、強い免疫応答維持活性(アロエよりも強いと言われている)を持つことが分かってきたものも存在します。
過剰な摂取にならないように注意しながら、こういった新たな機能も利用していくことができれば、いいですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
