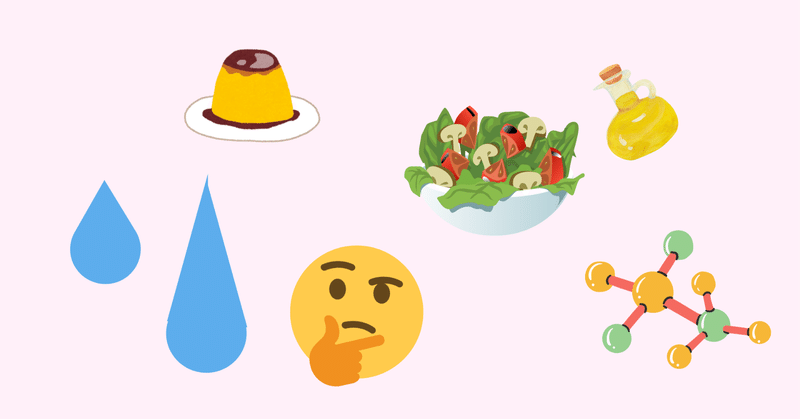
増粘剤と増粘多糖類
以前にこの場所で「増粘剤」について書いたことがありましたが、最近の食品一括表示を見ていると「増粘多糖類」といった表示名を見かけることがありました。これって、いったい何でしょう。前に書いた増粘剤と違うものなのでしょうか。
多糖類という名前がキーワードのようです。どうやら多糖類が用いられた場合には「安定剤」、「糊料」、「ゲル化剤」などの名称が使われているようです。これらは名前が違うのですから役割が違うのだろうという判断はできるのできそうです。しかし、さらに突っ込んで考えてみると、どのように違うのかが分かりません。今回はその辺りを考えてみる事にします。
一般に、食品に表示されている内容を消費者から見れば「物質名」であると考えることが多いと思います。しかし、食品表示法に則ってみれば「物質名」と「用途名」の2種類の表示があるそうなんです。そして、先に挙げた「安定剤」「糊料」「ゲル化剤」といった名称は用途名に該当するという事でした。
とは言っても、用途名だけだと実際には何が用いられているのかが分からないので、指定の用途で用いられたものについて「用途名+物質名」の記載をすることになっています。その「指定の用途」の対象は、甘味料、着色料、保存料、増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤又は防ばい剤なのだそうです。これらは食品表示法で規定されているという事でしたので、食品を買うときに見る一括表示などに書かれているんですね。そこまでよく見ていなかった・・・。
さて、指定の用途として挙がった内容を見てみると、この場所で以前に書いたものもあれば、取り上げていないものも出てきました。未だのものについては、いずれここでも取り上げることにします。
話を戻して、増粘剤と増粘多糖類との違いですが、これは食品表示の穴とでも言えばよいのでしょうか、ちょっと問題ありな気持ちになるようなルールがあるんですね。どういうことかというと、増粘剤や安定剤といった目的で使用した多糖類があったとき、複数の多糖類をそれらの目的で使用した場合は「増粘剤」「安定剤」とせずに、「増粘多糖類」と略した書き方にしてよいという決めごとがあるという事なんです。しかも、その場合は物質名を省略してよいとなっているんです。省略してよいという事ですから、消費する側としては書いてもらった方がよいと思います。
こんなルールがあるんですね。なんか逃げ道がいくらでも出てきそうな気になってしまいますが、ルールとしてある以上、仕方がありません。
なぜこのようなルールになっているかというと、これもまたヘンな理由がありました。かつては、一部の食品添加物に限って使用目的が表示されていたという経緯があるようです。その名残でしょうか、今でも用途名で記載されているんだそうですね。30年以上前の話になりますので、当時と現在とでは消費者の意識も社会情勢も違っていたでしょう。
そろそろ、また法的に改善をしていただけたらいいなと思うのですが、皆さんはどう思いますか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
