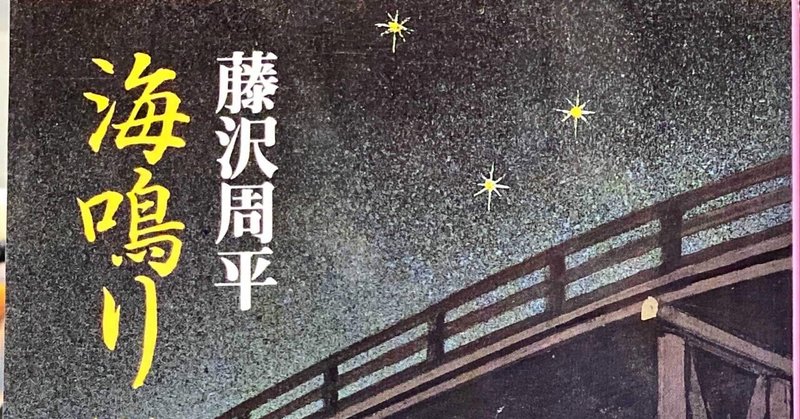
『海鳴り』ノート
藤沢周平
文春文庫(上・下)
藤沢周平の作品を取り上げるのは2冊目だ。1冊目は今年3月にnoteに書いた『静かな木』である。
藤沢周平の作品は、大まかに言うと、〝武士物〟〝捕物〟〝歴史物〟〝世話物〟と分かれると思うが、この作品は、世話物すなわち江戸時代の町人たちの人情と商売、日常生活を描いた作品の中でもやや異質な、大人の恋慕の情を描いている。
和紙の仲買から身を起こし、新参の紙問屋となった小野屋新兵衛は46歳になる。
自分の髪に白髪を見つけたのは40歳になる前で、その時は予期せぬものが落ちかかってきたと感じたのである。それは紛れもなく老いの徴候であった。見つけたのは1本の白髪であったが、その背後に見知らぬ世界が口をあけていると感じ、一瞬新兵衛を押しつぶしたのである。
そして40の坂を越えた辺りから、疲れも知らずに働いていた自分から想像もできないほど疲れが残り、身体の不調を自覚し始め、自分が老いの方に身を置いてしまったように感じ、老いとその先にある死を明瞭に感じられたのである。
ある夜、紙問屋の寄り合いがあった日の帰りに、道から見える鳥居の暗がりで男数人に囲まれてうずくまっている女を見つけた。かかわり合いにはなりたくないと思ったが、横を通り過ぎるとき、新兵衛は男たちを見た。その時、うずくまっている女の横顔が見え、同業の丸子屋のおかみのおこうであることが分かり、声をかけた。すると女の周りにいた風体の良くない男たちは、「この女の知り合いかい?」と声を掛けてきて、そうだと応える新兵衛に、「ぐあい悪そうなんでね。介抱していたところさ」といって、男たちはあっさりと離れて行った。
この時が、新兵衛とおこうの初めての出会いであった。
おこうは夫の代わりに出た寄り合いで酒を飲み過ぎたらしく、悪酔いをしており、とても一人で帰れる状態ではなく、寄り合いのあった店に連れて引き返すのも遠すぎた。駕籠も見えなかった。新兵衛は仕方なく、近くにあった飲み屋の二階を連れ込み客に貸す店があったことを思い出し、そこにおこうを抱え起こして連れて行った。そこで暫く休めば少しは楽になるだろうと新兵衛は考えたのである。この夜のことが、たちの悪い紙問屋の男に揺すられる因になり、あとあとこの物語の展開に影を落とす。
新兵衛とおこうのこの夜の出会いは、それぞれに決して幸せではない家の事情を抱える二人にとって情を交わす契機となるのだ。
物語の進展の中で描写される大人の交情の場面の描写は、お互いに交わす言葉とともに、人の心の機微に通じた藤沢周平の真骨頂である。
この時代、有夫の女と通じた男は引き回しの上獄門に懸けられ、相手の女も死罪になる時代であるから、駆け落ちをする二人は決して幸せな人生を送ることはないと思われるが、藤沢周平は物語の最後の場面をこのように書く。
「新兵衛さん。あたしのためにこんなことになって、済みませんでした」
「それはお互いさまだよ、おこうさん」
「でも、江戸のことは忘れてくださいね。お願いです」
二人は立ちどまって、顔を見合った。ついで固く手をにぎり合った。新兵衛は野を見た。日の下にひろがる冬枯れた野は、かつて心に描き見た老年の光景におどろくほど似ていたが、胸をしめつけて来るさびしさはなかった。むしろ野は、あるがままに満ちたりて見えた。振りむいて新兵衛はそのことをおこうに言おうとした。
この〝むしろ野は、あるがままに満ちたりて見えた〟という描写にこの新兵衛とおこうの行く末の幸せを藤沢周平は託したのである。
何で読んだか忘れたが、藤沢周平は渡辺淳一の『失楽園』のように心中で終わらせるつもりであったが、そうはしなかったということを知った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
