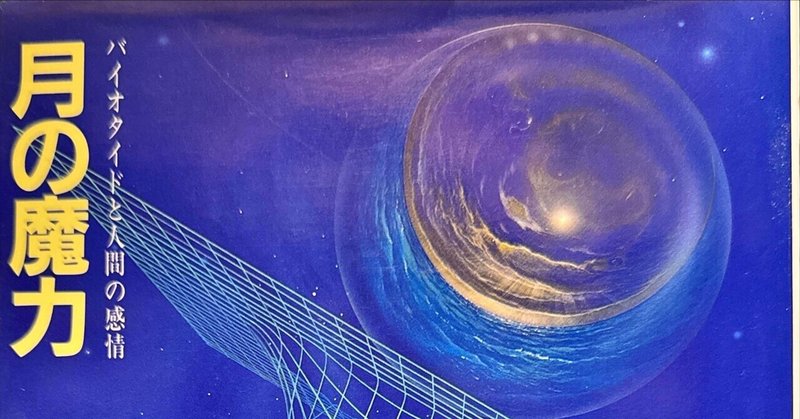
『月の魔力』ノート
A・L・リーバー著
藤原正彦・藤原美子訳
東京書籍刊
この〈note〉の存在を筆者に教えてくれた若い友人から、以前「満月の夜は眠れなくなる」という話を訊いたことがあり、その時は筆者も、月の動きと人間の体調は関係があるというどこかで仕入れた知識が頭の隅にあったので、「狼男伝説」や人間の生理などの例を伝えた。その後、随分前にそんなタイトルの本を読んだ記憶が甦り、本棚を探して再読した。
1984年の初版で、原題は『THE LUNAR EFFECT』で、もう40年近く前の本だ。今回初めて気づいた、あるいは忘れていたのか、訳者が数学者の藤原正彦夫妻だったのには驚いた。
藤原正彦の『若き数学者のアメリカ』や『遙かなるケンブリッジ』など、文章は軽妙で、人間味に溢れ、女性にもてたという話が必ず出てくるエッセイ集や硬派の『国家と教養』などほとんどの著作を読んでいる。今は『文藝春秋』の本文冒頭に置かれているエッセイのトップを飾っている人だ。余談だが、藤原正彦の両親は、ともに作家の新田次郎と藤原ていだ。以前にも書いたが、新田次郎の作品が好きでほとんど読んでいる。また、藤原ていの、『流れる星は生きている』という、戦後の満州からの引き揚げの悲惨な状況を綴った本も読み、講演会にも参加して著作にサインをもらったことがある。
さて、余談はこのくらいにして、この本のことを書く。
副題は『バイオタイドと人間の感情』とあり、帯には、「満月の夜は殺人、交通事故が増える!? 狼男・占星術・出産・精神病など、古来から現代にいたるさまざまな月の伝説・ミステリーを今、科学が解明する」とある。
著者のA・L・リーバーは、マイアミ在住の精神科医で、「満月の夜は殺人、交通事故が増える」という噂に興味を持ち、研究しはじめ、次々と新たな事例に遭遇し、月と人間の行動の関係を突きとめた記録をまとめたのがこの本だ。
月はその引力により、満潮・干潮を引き起こすのは知られているが、リーバーは、人間の体内水分は80%で、人間の身体でも潮汐作用が起きているのではないかという仮説を立てる。
この「生物学的な潮汐」こそ、人間の行動と感情に影響を及ぼし、そのリズムを通じて人間などの生命体はこの宇宙とむすびついているという「バイオタイド理論」を展開している。
「バイオタイド理論」に関してのリーバーのその後の研究の展開は寡聞にして知らないが、この宇宙で出現した地球上のあらゆる生命体を構成する元素も宇宙由来で、月を衛星として従えている地球の環境がその生命体の海からの出現、さらには進化の過程や体内的環境に影響を及ぼしているという仮説は決して荒唐無稽な話ではなく、肯えるものである。
本文の裏扉には、「月は人間行動に影響を与えている、と私は確信している」という宇宙学者のカール・セーガンの言葉を紹介している。
著者はこう書いている。
「何か身体が変だ? 月をごらんなさい、満月ではありませんか?」
「むしゃくしゃする? 月をごらんなさい、満月ではありませんか?」
「眠れない? 月をごらんなさい、満月ではありませんか?」
ニューヨークの著名な精神科医の話として、その医師が勤めている病院では、自分をはじめ職員が皆、患者の突然のおかしな行動は月が引き起こしたとしか説明できない、と思っており、満月時には電話の声まで荒っぽくなる傾向がある、とも証言している。
またフロリダ州立大学のある犯罪学者によると、彼の授業に出ている警官たちは、満月の時には犯罪発生率が上がると報告しているという。
ジョージア州のある地方判事は、4年ほど判事をしているが、満月時に夫婦間のもめごとがこじれる傾向があると言っている。
そういえば、ラテン語の月を意味するlunaを語源とする英語のlunatic(月の)という単語には「精神障害」という意味もある。月と人間の精神状態との関連を表しているのかもしれない。
古代ローマを起源とする変身伝説が元と思われる「狼男」の伝説の広まりは、人間の攻撃行動と月の周期に関連するある種の文化的背景であるとも書いている。
もう一つ例に挙げると、スティブンソンの『ジキル博士とハイド氏』のモデルとなったイングランドの職工であったハイド氏は、法廷で、月による間欠性精神病(ルーナシィ)のせいだとして、無罪を主張した。その主張は認められず有罪になったそうだが。
著者は、自分が務める病院の精神科病棟で、事件の起きる日時には独特なパターンがあることに気がつき、興味をそそられ、他のスタッフに取材すると、誰もが患者たちの動揺に説明の付かない周期があることや、満月の間は、落ち着きを失った、いっぷう変わった患者が治療を受けにくるということが分かった。
そして、これはもっと研究してみる価値があると思い、でたらめならでたらめであることを立証すればいいし、少しでも根拠があるのであれば確かめて、患者の健康管理に役立てようと詳細な研究を始めたのである。
その手法として、当時発達しつつあったコンピュータと天文学を使って、臨床心理学者の協力も得て、統計学的研究を始めた。
彼のチームは、殺人事件の記録が、発生時刻まで詳細に残されているアメリカのある地域の犯罪記録を詳細に調査して、満月と新月の時に殺人事件が有意的に増えることを発見する。
この本では、犯罪のことだけではなく、海の生物の産卵時期や、人間の身体の周期など、多くの例を挙げ、詳細な分析を試みている。
翻訳者の一人である藤原正彦は、バイオタイド理論に興味を持ち、自ら出産と月の関係について自身の数学的知見に基づき、統計的手法を用いた『出産における月のリズム』という研究報告をこの本の巻末に掲載している。
「バイオタイド理論」では、月の影響だけではなく、太陽と月と地球の相対的位置による引力(潮汐力)の変化にも触れており、小さいとはいえ太陽の様々な影響も折り込んでいる。
ちなみに、気象庁のホームページには、「月の満ち欠けと潮汐について」、海上保安庁のホームページには、「潮汐・海面水位の知識/潮汐の仕組み」という図解での分かりやすい解説が掲載されている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
