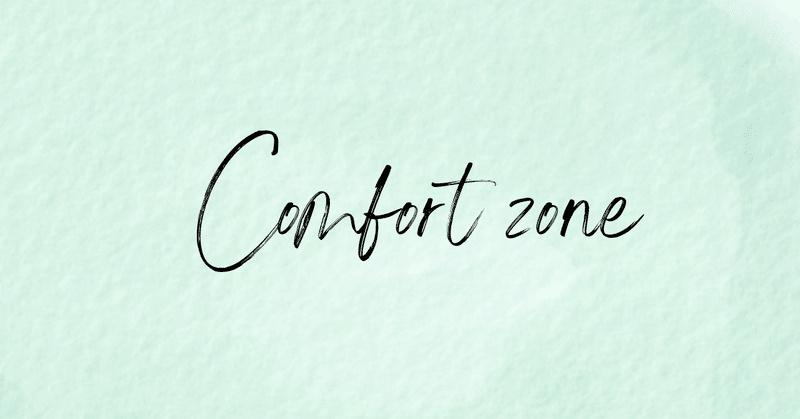
コンフォートゾーンの外側にいくことを一旦やめてみた
こんばんは、Miaです。
昨日はハッピーフライデーということで、お気に入りの韓国料理屋でチキンをテイクアウトして、家で作ったチゲ鍋と一緒に食べました😊
オーストラリアは外食が高いので、基本は自炊ですが、たまにテイクアウトで美味しいものを食べるのも楽しみのひとつです。
コンフォートゾーン
自分の居心地のいいところにとどまらない
さて、いきなりなんですが、ここ数年、私が手帳の表紙に書いてきた言葉があります。
“Life begins at the edge of your comfort zone.”
意味としては、コンフォートゾーンの外へ飛び出す時に人生が始まる、といったところでしょうか。
コンフォートゾーンとは、自分にとって居心地のいい範囲、環境、仲間などを指しています。
つまり、居心地の良い範囲にとどまることなく、挑戦し続けることで人生をより豊かに実りあるものにする、という教えだと理解しています。
上記の言葉を手帳に書き続けたのは、目標として掲げていたわけではなく、自分を鼓舞するためでした。
というのもここ数年、私にとって本当に激動の数年間だったからです。
新卒から勤めた会社の退職、
オーストラリアへの移住、
海外での就職、転職、
結婚、引っ越しなどなど。
コンフォートゾーンを飛び出していかねばならない、慣れない環境の連続だったともいえます。
英語しかり仕事しかり、何度も落ち込むことがありましたが、とにかく今は成長だ!と考えてひとつひとつこなすように心がけていました。
海外移住されている方はまさに今同じようにコンフォートゾーンから飛び出して、いろいろなことにチャレンジして頑張っている方も多いのではないでしょうか。
コンフォートゾーンとストレス
コンフォートゾーンの外側に挑戦していくことは、自分の成長につながります。
ただ、それと同時に大きく体力を消耗する考え方でもあります。
コンフォートゾーンの外側にいく負荷とストレスのバランスがうまく取れていないと、逆に負のスパイラルに陥ってしまいます。
・本当に嫌だけどこれも成長のため、と思って頑張るものの結果は出ず。
・自分の努力が足りない、情けない、なんで自分はこんなにダメなんだろう。
実際に私は移住してから英語に何度もつまづいて、一時期自己肯定感は爆下がり、布団に入るとツーと涙が流れてきて訳もなく悲しくなる状態になってしまいました。
それまで盲目的に、負荷こそ成長!と信じてきたのですが、過度にプレッシャーをかけたり、ストレッチしすぎることはかえって成長の妨げにもなりうるということに、ここでようやく気づきました。
コンフォートゾーンの内側に目を向けてみる
今までスポ根魂の如く、自分への負荷をかけ続けてきたのですが、これではメンタルのバランスが保てないと思い、思い切って今年からこの言葉を手帳に書くのをやめました。
そして、今年はもっとコンフォートゾーンの内側にフォーカスしてみようと思ったのです。
私は何が心地よくて、何に喜びを感じるのか。
何が好きで、どんな状態が幸せなのか。
自分の興味関心という感情に素直に従って、好きなこと、やりたいことに取り組んでみた結果、幸福度がめちゃくちゃ上がりました。
苦手なことややりたくないことに向き合うことがあまりに多くてなりすぎて、いつのまにか好きなことをするのが楽しいという感情すら忘れてしまっていたようです。
実際どんなことをやったのかはこちらの別記事で詳しくまとめていますので、ぜひ読んでみてください。
やりたいことだけやる、というと心の中のスポ根コーチがお尻を叩いてきそうになるのは分かります!
でも、コンフォートゾーンの外側にチャレンジする英気を養うには、コンフォートゾーンの内側の自分も充分に甘やかしてあげなければ、釣り合いが取れないんですよね。
もし同じように、日々成長のためにコンフォートゾーンの外側へ一生懸命に自分を押し出そうとしている人や、過度にストレッチした負荷を自分自身にかけてしまいがちな人がいたら、ぜひ思い切って一旦外側へ目を向けるのをやめてみることをおすすめします。
それはそれで勇気のいることですが、内側を見つめ、好奇心が湧くことやずっとやりたかったことに集中することは、結果としてリフレッシュにつながります。
最後に
なんだか横文字の多い回になってしまいましたが、私がお伝えしたかったことをまとめると、
・心地よい範囲を超えて挑戦することも大事
・ただし押し出しすぎに注意
・疲れてしまったら、自分が本当に好きなことに目を向けて、そこだけに一旦集中してみる
何事も無理しすぎず、心身ともにバランスをとりながらヘルシーな生き方を模索していきたいと思います。
今日も読んでいただきありがとうございます♪
Mia
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
