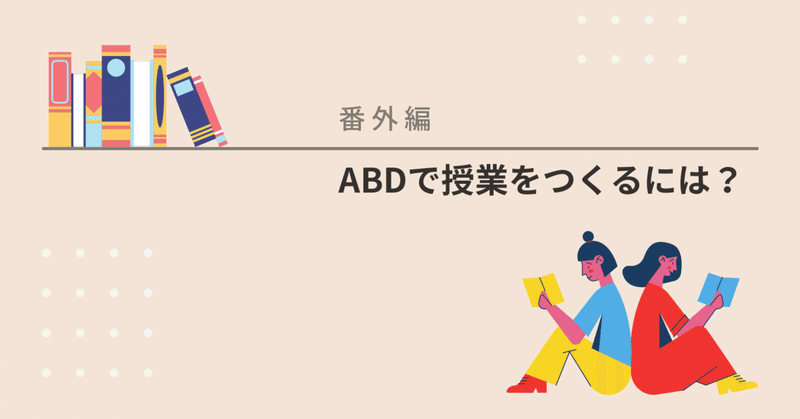
ABDで授業をつくるには?〜塩中ABD番外編
走りながら作ってきたABDの授業。全10回の授業のうち、いま5回を終えた時点で、ようやく全体像が見えてきました。私自身もファシリテーターとしてふるまう以上に、学びながら授業を作っています。
私もファシリテーターとしてはまだまだ駆け出しなので、今後も授業は改良の必要があります。
そこで今回は、自分自身の備忘録も兼ねて、ABDという読書会をどのように授業として組み立てていったか、構成の経緯をご紹介します。
何か新しい授業形式を模索されている方々の参考になれば幸いですし、こうすればいいよ!という改良のアドバイス、コメントもいただけると、とてもうれしいです。
最初にやったこと
以前の記事にて、この授業のテーマをメディア・リテラシーとして、「ググっても出ない自分の人生の歩みかたについて、考えるきっかけにしたい」というイメージで授業を作っているとご紹介しました。
講座を作るにあたってテーマから考えたのか~と思われるかもしれませんが、実はそうではありません。テーマは講座の準備をするにつれて表れていったものです。
一番最初は、全体の構成を考えること、つまり授業時間の整理からはじめました。至極ふつうですね。
全10回の中でしっかり時間を取れる回数が何回あるか、1回の授業時間は何分かなどを依頼の際、先生に伺った要件を整理して時間を配分していきます。
今回、授業の授業時間は110分で、しっかり時間をとれる授業の回数は7回。そこで、7回全部を私が選んだ本を読むので時間がもつかどうか?慣れるためのABDが3回ぐらい必要だとすれば、その後はどうするか?という考えに至ります。
ここで、ABDの強みを考えてみます。
ABDの面白さの一つは、同じ本でも人によって感想や考えが違うことを目の当たりにできることです。これは人の意見を聞いて初めて成立するのですが、実は「フリーな意見を聞くことって、学校生活では少ないのではないか?」という問いが私の中にありました。
学校生活は、テストなどを通して、正解がある生活に慣れることでもあります。そうすると、「何でもいいから意見を話して」と急に言われても、暗黙のうちに正解があるように思って、考えを出すのを不安に思うことがあります。思い返せば、私自身の学生時代にも、人と違うことをすると根拠もなく怒られた経験があります。
そうした私の妄想から浮かんだのが、上記の「ググっても出ないことについて考える」というテーマでした。
すると、あとは自動的に、生徒が自分で選書をする回や、それを元に自分たちでABDを実施するという構成で、講座を肉付けするイメージができあがります。
このような手順で大まかなスケジュールは講座の最初に決め、一方で1回1回の授業内容は、生徒の様子を見ながら直前に決める、というスタイルで運営してきました。
講座全体の折り返し地点にたった現時点から、改めてこの講座を見通すと、3つのステップに分類されるように思います。
Step1 自分を意識する(第1回~4回)
Step2 自分を表現する(第5回・6回)
Step3 協働する(第7回・8回)
ひとつひとつみていきます。
Step1 自分を意識する(第1回~4回)
初回の授業では、アイスブレイクとして「自分の好きなもの3つ」を挙げてもらいました。
その取り組み具合で、子どもたちが、どのくらい自分の好きなものについて意識しているか、それを抵抗なく人前で出すことができるかの調査も兼ねています。
予想していたとおり、子どもたち全体としては、自由に意見を出すのには慣れていない印象でした。食べ物やスポーツ、よく読む本のジャンルなどをいくつか挙げられる子がいる一方、何を書いたらいいかわからない、と筆が止まる子もいて、個人差はかなり大きく感じました。
しかし、いざ「好きなもの教えて!」といわれると、大人でもちょっと時間が必要かもしれません。
単に好きなもの一つとっても、考えをすぐ出すためには、
・普段から自分がどう考えているかを意識していて
・それを人前で表現する習慣がついている
ような練習をしないと、なかなか難しいものです。このステップでは、まさにこれらのポイントを意識する点にあります。
また、第2回~4回で実施した計3回のABDの中でも、ダイアローグの時間が自分への意識を促すきっかけになります。
ダイアローグを成立させるためには、黙っていては進まないので、毎回「メモに書いて、他の人に話す」を繰り返すことになります。この中で、少しずつ自分の考えに意識を向けたり、他人との違いを意識したり、自分なりの表現方法を身に着けたりする練習を重ねていくのが、第2回~4回でした。

Step2 自分を表現する(第5回・6回)
第5回の授業では図書館を貸し切って、子どもたちにABDで自分が読みたい本を選んでもらうことにしました。
しかし、残念ながらすべての本でABDをするには時間が足りないので、この中からいくつかの本を選ぶ必要があります。第6回の授業では子どもたちがプレゼンをして、2冊に絞ります。
他人とは関係なく、自分が読みたい本を選ぶ。そして、それを他人にプレゼンする。このとき、大切なのは本の内容ではありません。
なにせ、選んだだけでまだ読んでいないのですから。
最も大切なのは、なぜ読みたいと思ったか。
自分の気持ちを整理して、理論的に話す。または、相手にわかるようなストーリーをつくる。こうした練習は、前の授業でおこなった「書いて、話す」よりも一歩進んだ表現です。
次回、第6回を実施する現時点で私が注意していることは、子どもたちの「心理的安全性」です。
心理的安全性とは、組織やグループにおいて、人間関係の不安を感じることなく、それぞれが力を発揮するための土台作りとして、近年重要視されています。
自分自身を表現しようとするとき、それによって自分が不利益をこうむったり、チームの雰囲気が悪くなることを気にしたりしていると、なかなか率直に意見を出すことができません。
このため、次回のプレゼンの前には、グループごとに安心して本音を言えるような土台作りをする必要があります。
例えば、これまでのABDのダイアローグの前には、約束事としていくつかのルールを説明しました。
・人の話をよく聞く
・判断を保留する
・教室の外のこととは無関係
これらのルールで、授業でつくられる関係性をひとまず授業内に限定し、その他の学校生活と結びつけられないようにすることを狙っています。
心理的安全性の構築については、ルール作り以外にもまだできることがあると思いますが、私自身も資料などで勉強中です。興味のある方は調べてみてください。そして、わかったことがあればぜひ私にも共有してください!
Step3 協働する(第7回・8回)
終盤の授業は、生徒たち自身にABDを企画・実行してもらうことにしました。そのための準備が第7回、ABD本番が第8回です。
自分を意識し、表現ができれば、最後はそれを個人の思いとしてだけでなく、グループでの活動で活かすことで、さらに大きなことができるようになります。
毎回思うのですが、子どもたちは毎回私が予想した以上のスピードで、理解し、行動をしてくれます。ここではそんな子どもたちのポテンシャルを最大限に引き出すのが私の仕事と考えています。
ABDで必要な項目(ページ数の目安、時間配分の例など)を私が説明したら、後はグループごとに計画を立てていきます。きっかけになるのは、個人的な「読みたい」という思いです。スタート地点は個人の思いですが、そこからほかの人の思いも加わって、自分「たち」がABDを通して知りたいこと、やってみたいことを、うまく調整しながら決めるには、ほかの人との協働が不可欠です。
とはいえ、ここはまだ未実施のため、どうなるかはこれからのお楽しみ。
個人的には、私のやっているABDの方法とは違ったアイデアが出てきても面白いなあ、と楽しみにしています。
発表、そしてクロージング(第9回・10回)
これらの授業は、塩尻中学校で「地域ふれあい学習」(総合学習)として行われているものです。授業の成果は、毎年の文化祭で発表されます。
今年も社会情勢を鑑みて、文化祭自体の実施形式が検討されているようですが、あくまで講師の私としての計画では、自分たちで行ったABDの様子を展示したいと考えています。
発表の仕方については、社会情勢によっても変わるかもしれませんし、学校が変われば異なる枠組みがあると思いますので、展示が唯一の正解とは思いません。その都度ある、制約の中で工夫することが重要です。
そして最後の第10回は、半年の振り返りのタイミングになりますが、まだ何をするか決めていません(笑)。どのような形で振り返るのか、残り半分の授業のなかで固まっていくことでしょう。
=====
以上、授業の全体像のご紹介でした。
振り返ると、当初のメディア・リテラシーからはだいぶ複雑で深い内容になっているなぁと思います。が、この授業をひとことで言うには、まだピンとくる言葉が見つかっていません。
それは、全10回を終えたときにまた考えてみようと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
