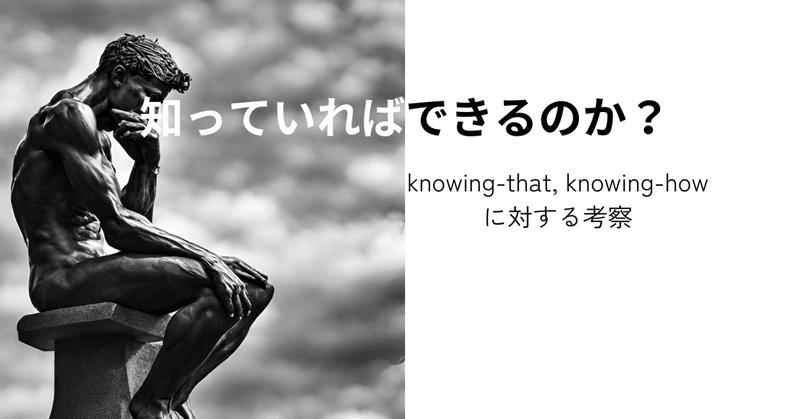
知っていればできるのか?~knowing-that,knowing-howに対する考察~
「知っていればできる」あるいは「知らなければできない」というのは当然のように感じる。しかし、同時に世間では「知っていてもできない」ことがあるように語られることは多い。ここでの「できる」は可能性(possibility)の話ではなく能力(capability)の話だ。いわばこれは「知識」と「能力」は違うということを言っているわけだ。
"事実の知識"と"方法の知識"
言語哲学者G.ライルは「知識」について次のふたつの区別をつけた。
・葛飾北斎は93回転居したということを知っている、ニュートンは万有引力を提唱したと知っている
・自転車の乗り方を知っている、将棋の指し方を知っている
順にknowing-that(~ということを知っている),knowing-how(~という方法を知っている)と名付けられている。(以下k-that,k-howと略記)
この内、k-thatの知識を能力にそのままパラフレーズすることはそもそもカテゴリーミステイクである。「葛飾北斎は93回転供したということができる」は非文(文として成り立たない文)だからだ。
ということでここで問題になるのはk-howについてだろう。たしかに「自転車の乗り方を知っている」なら「自転車に乗れる」と同義に思われる。しかし、k-howでは「知識」と「能力」は同等になってしまう。とすると世間で言われているような「知識」と「能力」の違いはどこから来ているのだろうか。
知識があるならば実践できるのか?
知識→能力という関係性が成り立つときその組み合わせは次の4つになる;
知識がある→できる
知識がある→できない
知識がない→できる
知識がない→できない
この内、「知識があるならできる」、「知識がないならできない」というのが知識が能力と同一である場合だと考えられる。しかし他の命題が何を意味しているのかは不明瞭だ。また本当にこれらの分析は正しいのだろうか(該当する状況がないなら単に空虚な分析が含まれていると言えるだろう)?
知識の標準分析
知識の標準分析とよばれるものがある、伝統的にプラトンに始まる知識の3つの条件に関するもので次のものだ;
aはPと知っている
⇔(1)p(pは真)
(2)Bap(aはpと思っている)
(3)JBap(aのpという信念は正当化される)
ここで、(3)の正当化に関する問題は現代でも議論の対象だが、(1)については基本的に誰もが認めている。例えばとあるマジシャンがあなたの引いたカードを当てるとき、「私はあなたの引いたカードを知っています」と言ったとしよう。そしてマジシャンは数字とスートを言う。しかし、このマジシャンが言った数字とスートがあなたの引いたカードと違った場合、そのマジシャンは実はあなたの引いたカードを知らなかったことになる(その場合マジックは失敗したのだろう)。
このように「知識」とはその対象が真であることを含意しているとされる。ただし、この知識はk-thatに限られる、とされている。(ライルはそもそも当時の認識論(知識に関する哲学)が主知主義(k-thatについての知識)に縛られていることを批判するためにk-howの反例を出したのだ。)たしかに、「自転車の乗り方」を知っているとき、「自転車の乗り方」は真であると言われてもよくわからない。やはり実際に自転車に乗れることがわかって初めて、その知識の正しさが判断されそうだ。
私の意見では、自転車の乗り方を知っていて、かつ実際に乗れるときその知識は真だといいたい。つまりk-thatでは実際にその世界で知識Pが真であるだけでいいが、k-howの知識Pは知っていてかつそれを実践する能力があるときに限りPは真になる。
知識と実践の形式化
さてここで、問題を複雑にしすぎないようにするため形式化してみよう。$${t\Psi A}$$を「tはAと知っている」とする。すると知識の標準分析より$${t\Psi A\vDash A}$$(tがAと知っているのが真なら、Aは真)。このときAは知識に関する文や対象が入るので、Aはすべての文の集合の要素である$${A\in S}$$。したがって、Aはk-that,k-howどちらも取れる。
また、$${\neg t\Psi A}$$は「tはAと知らない」と読み、$${\neg t\Psi A\nvDash A}$$である。これは「tはAと知らないが真なら、Aは真か偽かわからない」ということだ。
次に能力について、$${\delta(t)(A)}$$をtの文Aに対する能力の真偽に関する表示と考える。すなわち$${\delta^+(t)(A)}$$を「tがAできるは真」、$${\delta^-(t)(A)}$$を「tがAできるは偽」($${\delta^+(t)(\neg A)}$$,「tはAできないは真」とする。
さらにこの割り振り方をAが真のとき$${\delta^+(t)(A)}$$,Aが偽のとき$${\delta^-(t)(A)}$$と割り振ることにする。Aはk-howに関する文のはずなので、Aが真になるところでは必ずAできるはずだ。またAが偽となるところでは必ずAできないはずである。
すると、先程の知識と能力の関係は以下になる。
$${ (1)t\Psi A\to\delta^+(t)(A)\\ (2)t\Psi A\to\delta^-(t)(A)\\(3)\neg t\Psi A\to\delta^+(t)(A)\\(4)\neg t\Psi A\to\delta^-(t)(A)}$$
実際にはこれは逆向きの矢印$${\gets}$$についても考えなければならないのだが、ここでは因果的に「知っているからできる」のように読み下す目的のために$${\to}$$だけを調べよう。
(1)tはAと知っているときAは真→Aは真のときtはAできる
(2)tはAと知っているときAは真→Aは偽のときtはAできない
(3)tはAと知らないときAは真か偽→Aは真のときtはAできる*¹
(4)tはAと知らないときAは真か偽→Aは偽のときtはAできない
このようにみると、(2)のときだけ、Aは真→Aは偽となり非妥当である。ただし(3)より、能力は知識と独立して成り立ちうることはわかる。
そこで"知っていてもできない"の例を考えてみよう。例えば、私は自転車に乗ることができない。自転車にほとんど乗らないまま大人になり、自転車を使う機会がないままだからだ。しかし、自転車がなぜ真っすぐ進んで倒れないのか(ジャイロ効果)。自転車の構造がどうなっているのか(各種パーツの名前や用途)は知識として知っている。このようなとき私は自転車の乗り方についてk-thatとして知っていると言える。しかしk-howとしての自転車の乗り方を実践できていないのだ。ということは私はk-howとしての自転車の乗り方の知識を持っていないことになる。つまり「知っているができない」は(k-thatについては知っていてもk-howについては知らないため)そもそも成り立たないということになる。
本当に知っているならばできる
実際この(2)が成り立たないことは、世間で言われている「知っていてもできないことがある」に対する反例になるだろう。ただしよくよく考えてみると世間でそのように言われる際も「知識としては知っていても実践はできない」のように言われているように思う。すなわち、「知識」と「能力」が区別されるとき、知識のほうではk-thatが求められ、能力の方ではk-howとしての知識の実践が求められることがわかった。
ライルが行った知識にたいする区別はその後も盛んに議論され、k-howが今までの知識についての哲学に対してどのような立ち位置を取るのかは議論の分かれるところだ。しかし、世間というレンズを通してみた場合、少なくとも、k-howはk-thatに還元可能、あるいはk-thatには還元できないが、k-howとk-thatどちらの性質ももつ知識があるという立場に立つことになる、というのは面白い事実かもしれない。*²
脚注
*1;「知らないができる」は少し不思議に感じるかもしれない。例を考えると、クイズなどで4択問題からたまたま正解を当てたときなどが当てはまるだろう。(厳密にはこのようなとき正解できたはcapabilityというよりpossibilityに近いかもしれない、そこで次の例も考えよう)。
また無限の猿のジレンマと呼ばれる思考実験がある。猿に無限にタイポライターをランダムに打たせ続ければ、どこかで必ずシェイクスピアの作品と一字一句違わない作品ができあがるはずだ。(このような時、この猿は少なくともランダムな字句を打ち続ける能力をもっており、したがってどこかでシェイクスピアの作品を打つ能力があるといえる)
*2;k-howを巡っては、大きく3つの立場がある。①k-thatにk-howは還元できるという立場②k-thatとk-howは互いに独立であるという立場③k-thatにk-howは還元できないが、ある種のk-howはk-thatを前提に考えられていたり、ある種のk-thatはk-howを前提に考えられていたりと互いに独立とは言えないとする立場。
参考文献
W.G.ライカン,『言語哲学─入門から中級まで』,勁草書房(2005)
池吉 琢磨,中山 康雄,「knowing-thatとknowing-howの区別」,科学基礎論研究37 巻 1 号,(2009-2010)https://www.jstage.jst.go.jp/article/kisoron/37/1/37_KJ00007180013/_pdf
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
