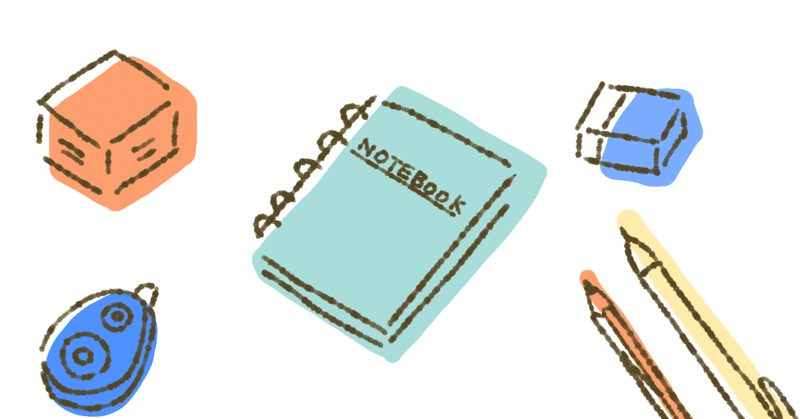
40代ワーママが働きながら通信制大学入学〜50代で卒業するまで(Vol.3)
※これは私が40代後半で通信制大学に入学し、50代にようやく卒業するまでの記録です。話があちこちにそれるかもしれませんが・・・どうぞお付き合いくださいませ。
(前回のお話はこちら)
入学!そして・・・
入学申し込みの後は比較的すぐ入学通知が来て喜んだのも束の間で、
この後すぐに単位を取るための履修科目の選択をすることになりました。
履修科目の選択について
大学を卒業するためには一定の単位を取らねばならず、それは履修する科目によって種類や数が異なります。
普通に大学に通っていれば知り合った友人と「何にする?」「これどうするの?」なんて相談しながら決められたのでしょうが、ここは通信制という独りぼっちの学びの苦しい所・・自分で単位の取り方を読み解き、卒業できるだけの単位組みをしなければなりません。
単位の取り方
最終学歴によって異なりますが、私の入学した大学で、私が卒業するために必要な単位数は62でした。
大体1つの科目に対して1~2の単位数になるのですが、選択できる科目はおよそ100~200くらいありまして、ここからいくつかの種類に分けて取得を決めるのです。
①全員対象科目
②学部対象科目
③学科対象科目
④その他の調整
①全員対象科目について
これは入学した大学・学部によるかもしれませんが、共通で必修(選択に入れなくてはならない)科目です。ざっくり言うと「大学の理念」だったり「コミュニケーション」や「キャリア」といった基本理念や基本スキルの講義が中心となります。
②学部対象科目について
ここからが本番です。何を学ぶのかももちろん大事ですが、「学んだ後にどうすると単位が取れるのか?」まで視野に入れた方が良いです。
私の場合は文学部だったので基本的にはレポート提出が中心になるのですが、講義によってレポートの枚数が1600字だったり2000字だったりします。(当然ながら少ない方が楽です・・・)
加えてよほど内容に興味がないと文章が書けないので、送られてきたシラバス(授業の内容がある程度わかるガイドブックのようなもの)とにらめっこしながら、あれこれ検討を重ねました。
③学科対象科目について
学部の希望科目が決まったら、次は学科の希望科目を選択します。大学や学部によって異なりますが、私は文学部・日本文学・日本語学科だったので、学部では広く「文学」を履修し、学科では専門的な「日本語」に特化した勉強を選択することができました。
例えるなら②の学部対象科目では「日本の近現代文学」を学び、③の学科対象科目では「日本語が持つ音韻とその歴史」について深く知る・・ということが可能でした。
④その他の調整
これは通信大学ならではかもしれませんが、授業によっては対面が必須の講座もあります。つまり、自分のペースで学習するのではなく、指定された日に授業を受ける(+科目によっては宿題の提出もある)ことで単位が取得できるようになっているので、これを組み込む必要があります。
対面の科目は事前に年間スケジュールが提示されているので、仕事の予定と見比べながら、受講したい科目を選択します。
チェックと提出
希望する履修科目が決まったら、最低限必要な単位数がそろっているか確認して提出し、申し込みすれば完了です。
(ちなみに私の場合は最初のチェックが甘くて、提出した履修科目だけでは卒業できないことが1年以上経ってから分かりましたが・・・事務局の方の誰も指摘はしてくれませんでした。「自分のことは自分で」ですよね!良い勉強になりました・・)
※(Vol.4)へ続く予定です。またお時間ある時に、お付き合いくださいませ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
