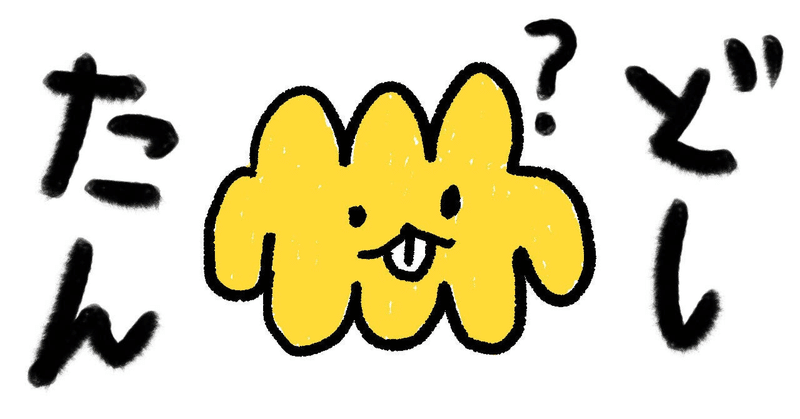
一貫性の罠
ここのところ、あまり読書に気が向かなくてトランサーフィンの第2巻はまだ半分ちょっとしか読み進んでいません。記事を書けるのはもうすこし先になりそうですが、楽しみにされている方はしばしお待ちください。
さてさて、今日は「一貫性」ということについて考えてみたいと思います。人が自分のことを自分だと思っていること、つまりアイデンティティってどのようにして形作られていくのか、考えてみたことはありますか?
いわゆる自我というものは、ほんとうは経験の記憶(サンスカーラ)と心の傾向(ヴァーサナー)と思考が肉体を所有している感覚や自分の名前といったものと一体化することによって生みだされる幻想なのですが、なぜそれが個々の人格として振る舞うことができているのでしょうか?
簡単に言ってしまうなら、昨日の自分と今日の自分をおなじであろうとすることによって、人は自我と人格を維持・強化し、個人として振る舞っています。
「わたしは◯◯な人間だ」
「わたしは△△が好きで□□は嫌い」
「わたしの名前は☓☓です」
「わたしの職業は●●で、職場は▲▲にあって、■■や◇◇という友人がいます」
こういう自分についての情報は、誰でもすぐに言うことができるはずです。自分の名前だったり職業だったり、食べ物の好き嫌いだったりといったことが昨日と今日とで違ってくることは普通、ありませんよね。
逆に毎日、名前が違うだけでなく見た目や性格まで変わるような人がもし居たとしたなら、その人は社会で生きていくことがたいへん難しいはずです。なぜなら、他の人からすれば、もはやその人が誰なのか分からないからです。見た目が変わる人なんて普通はいませんが、多重人格の報告事例によれば、人格が交代すると顔つきだけでなく体つきや声まで変わる人がいるそうです。まあ、これは極端なケースですが。
つまり、人間が社会においてスムースに機能するためには、見た目や名前はもちろん、性格や記憶、知能や好み etc. といった人格と自我を構成するさまざまな要素が「一貫」している必要があります。
一見すると、自我や人格が一貫しているのは当たり前のことであって、一貫するように努力するようなものではないのじゃないか? と思われるかもしれません。でも、ほんとうにそうでしょうか? たしかに、意識的に努力する必要はないでしょう。わたしもそのような努力はした記憶がありません。
でも、だからといって自我や人格が自然に一貫しているわけではなさそうです。たとえば名前は親や親の代わりになる人から与えられ、社会によって承認(戸籍登録)されます。これによって、AさんはこれからずっとAさんとして生きていくことができ、周囲の人はその人をAさんと呼んで他の人と区別することが可能となります。
名前というものは社会から一貫することを強制される属性のひとつです。結婚すると名字が変わったり、芸名やペンネームといって本名とは別の名前を名乗ることもありますが、それらにしても、基本的にその名前において一貫した行動をとることが社会的に期待されています。
Aさんがその後、Bさんと友達になったとします。BさんはAさんがチョコレートが好きだと知っているので、Aさんにチョコレートをあげます。ここでAさんが「わたし、チョコは嫌いなの」と言ってしまったら、Bさんは混乱してしまうでしょう。もちろん、好きだったチョコレートが嫌いになることはあります。でもその場合、AさんはBさんに「あのね、わたしいまはチョコレート好きじゃなくなっちゃったの」と説明しなくてはいけないでしょう。
「好きじゃなくなっちゃった」ということは以前は好きだったということですが、こういう説明が人間同士のコミュニケーションにおいて必要となる理由は、「好きなものは以降ずっと好きであるべき」という暗黙の要求が存在しているからです。このような暗黙の要求は無数にあるはずです。
食べ物の好みが変わることはあって当然のことですし、よいも悪いもない、些細なことです。それであっても、そこに一貫性がないだけで、ちょっと面倒くさいことになってしまいます。ましてや、これが人に対する好き嫌いともなると、ときにとんでもないトラブルにさえなりかねません。
夫婦間において相手のことが嫌いになるということって、実際にはよくあることだと思います(まあわたしは結婚したことありませんが😌)。でも、それを口にすることは決して簡単なことではないでしょうね。ずっと互いを好きでいないといけないという約束なんて、そもそもできっこないのですが、結婚とはなぜかそんな約束の代名詞のようになっていて怖いなとわたしは思います。
一般的な話として、言動に一貫性が著しく欠けている人間は「嘘つき」と呼ばれたり「信用できない」と評価されます。これは、ある意味では仕方ないことではあります。社会というものは約束事(法律、ルールや契約など)によって成り立っています。言動に一貫性がないということは、約束を守ることができないということですから、そのような人は社会にとっては困るわけです。
さて、いろいろと見てきましたが、こういったさまざまな事情によって、意識的にではないにせよ、人は昨日の自分と今日の自分が同じであろうとしています。こういうことの積み重ねによって「わたしであるもの」というゲシュタルトが構築されていくわけです。
上でも述べたように、これは社会で生きていくうえでは必要なことですし、それがうまく出来ている人、つまり行動や人格の一貫性が徹底している人はポジティブに評価されます。
しかしながら、スピリチュアルな観点でみれば、こうした一貫性には悪い面もあると言うことができます。
なぜなら、この世界のすべてのものは変化するからです。人間も例外ではなく、人の意識レベルは変化します。ホーキンズ博士によれば、平均的には人は生涯で5ポイントしか上昇しないそうですが、たった5ポイントの上昇であっても、霊的なパワーは10万倍に増大しますから、その違いは大きいです。まして、探求者が目指しているのは数十から100ポイント以上の上昇です。意識レベルの飛躍は、それまで真実だと思って生きてきた現実から別の真実がある現実へと移行することを意味しています。
社会でうまく機能するために必要な一貫性は、その人が固定された意識レベルで生きている限りにおいて必要であり、それを備えていることはよいことであるといえます。しかし、その人の意識レベルが少なからず上昇しようという場合には、この一貫性が足枷となってしまいます。
たとえばですが、夫婦のうち一方の意識レベルが急上昇したとします。そもそも互いの意識レベルを多少なりとも考慮して結婚したかどうかはともかくとして、それまではうまくいっていました。ところが意識レベルが高まりはじめた人にとっては、もはやパートナーにはなんの魅力も感じなくなってしまいました。それどころか、一緒にいるのが難しいとまで思いはじめます。
あるいは、その人自身の意識レベルは変わっていないのですが、相手の意識レベルが下がってしまうことも実際にあることです。分かりやすい例としてはギャンブルや酒に溺れたり、不倫に走ったりというケースです。こういう場合も、もうこんな相手とは縁を切りたいと思うかもしれません。
後者のケースなら、なんといっても相手には非がありますから、思い切って実際に別れるという判断をするのも、そう難しいことではないでしょう。それができれば、堕落していくパートナーに引きずられて自らも意識レベルを落としてしまうことを回避できるでしょう。
問題は前者の場合で、相手に魅力を感じなくなったことを理由に離婚して欲しいというのは、一般的な視点では自分勝手だと判断されてしまいそうですし、そのように感じる自分にも非があるのではないか、などと考えてしまうということもあるでしょう。情熱的な気持ちが冷めただけなら別れるまでもないかもしれませんが、それは普通、互いの意識レベルに変化がないからです。
結婚してしまっている以上、これはなかなか難しい問題ですが、なんらかの妥協あるいは我慢をして一緒に暮らすことを続けたとしたら、その人の意識レベルはいずれ元のところに戻っていくでしょう。そうならないためには、パートナーを自分と同じか、少なくとも近い意識レベルにまで、うまく導いてあげるしかありませんが、ほとんど無理なことではないかと思われます。
意識レベルは上がったら上がったままというわけではありません。少なくとも意識レベル540を超えるまでは、外側に存在している人やモノ・コトの意識レベルに影響されて常に上がったり下がったりするものといえます。いったん上がっても、周りに足を引っ張るような低い意識レベルの人物がいたり身をおいている環境が悪かったりすると、そのレベルに定着できず、逆戻りしてしまいます。
このように周囲の人物や環境に引きずられてしまうのも、そこに一貫性を保とうという心理が働くからです。自分の内面の変化を表現すると一貫性を失うことになります。そうすると、周囲や環境から非難されるかもしれません。それも問題ですが、それ以上に、自分自身が一貫しないことをよくないことと思っていることが問題です。
探求者においては、意識レベルが高まっていく過程で、現実の見え方(つまり、その人にとっての真実)がどんどん変わっていきます。あるレベルにおける真実は、より高いレベルにおいては別の真実に置き換えられます。低いレベルの真実が誤りというのではないのですが、低いレベルからは高いレベルの真実は理解できません。
すでに悟りや覚醒のレベルに達しているマスターに指導を受けている場合(はっきり言っておくと、このレベルのマスターは日本国内には片手で数えられる人数しかいません。ですから、自称マスターはそのほとんどが嘘です)や、その人自身がその領域へと急激に上昇するような場合はなんの問題もないのですが、気をつけないといけないのは、段階的に進歩している探求者です。つまり、ほとんどすべての探求者です。
この人たちは、「一貫しないことをよしとすべし」です。意識レベルが上昇するといっても、それは普通は非常にゆっくりと進行します。わたしにしても、最初の目覚めからもう10年以上経過していますが、いまだに上昇が続いています。一貫性にこだわる従来の習性そのままだと、意識レベルが上がるたびに、それまでの自分の認識(真実)を否定することを恐れてしまいます。これがさらなる成長を妨げる足枷となりえます。
これが、自分の内面における葛藤だけであるなら、実際にはそんなに深刻な問題ではありません。なぜなら意識レベルそのものは高まっているのですから、以前の自分の真実がなんであれ、いまの自分がみているものが真実であることは疑いようのないことだからです。
しかし現代はSNSを使って自分の理解を外側の世界に向けて発信することが誰にでもできますし、実際にそうしている探求者が数多くいます。同様に、マスターを自称しているような人もまたSNSで弟子だかお客さんだかを集めるための宣伝活動に余念がありません。こういうことそれ自体は、べつに悪いことではありません。
ただ、探求者であれ、自称マスターであれ、その人が書いていることは、その人のその時点の意識レベルにおける真実か、さもなければ真実を追い求めるための推論のようなものです。いずれであれ、その人の意識レベルがその後に上昇したなら、その時に書くであろうことは「前に言っていたことと違うこと」になるわけです。
これは避けられないことですし、むしろ、前言撤回することがないのなら、その人はまったく成長していないということにもなります。そもそもの意識レベルが相応に高い人、たとえば500以上の人であれば、すでに謙虚さも身につけているはずですから、こういう局面もうまく乗り越えることができると思います。しかし、そうでない人は、なかなかできないかもしれません。
探求者は探求している時点で、まだ分からないと思っているのですから、意識レベルにおける真実の置き換わりは本来であれば「おお、なんか分かってきたかも」という風に表現されるはずです。そのような人はなにも問題ありません。しかし、エゴが邪魔をして、それまで分かった風なことを書いてきてしまっている人は、この一貫性の罠にいとも簡単に陥ってしまうでしょう。
悟りや覚醒はそれが起きた当人にとっては自明です。つまり、それが起きたことを誰かに承認して貰う必要がないということです。逆にいえば「これは悟りだろうか?」とか「覚醒したかもしれない」という人は、悟りも覚醒も起きてはいません。ですから、それが自明でない限りは、いま自分が真実だと思っていることは後に別の真実に置き換わるだろうという認識を前提にして、書いたり話したりする方がよいのです。
そうしておけば、自分の見えているものが変わってきたときに、なんの葛藤もなく一貫性を放棄することができるでしょう。そしてそれが、さらなる成長へとあなたを後押ししてくれるはずです。
記事へのリアクションや記事執筆への励ましのサポートありがたく頂戴します🙏 また、プロフィールにAmazonほしいものリストも掲載しています。こちらもぜひよろしくお願いします!
