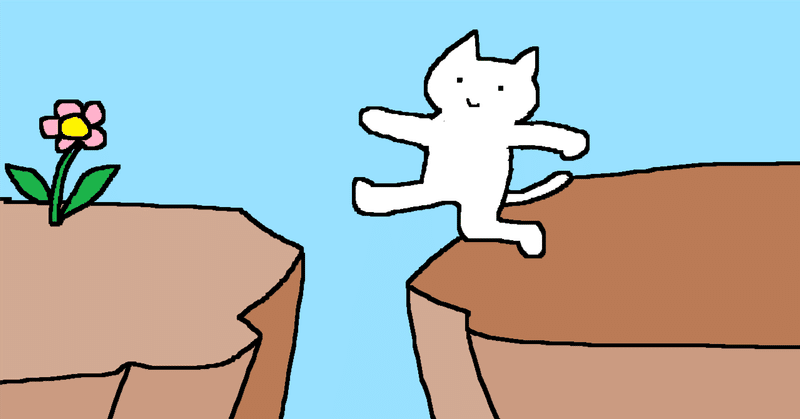
「ちょっといい」に着地したい
いじめがないのが「よい」クラス、みんな明るくて元気で仲良しなのが「よい」クラス。小中学校のころ、「よい」といえばすなわち「問題がない」を指していた。でもそれってヤバいよなあ、といまさら思う。
「問題がないのがいいこと」になってしまうと、なにか起きたら隠蔽するのがベターになる。いい評価を得たいなら、問題をなかったことにするのがいい。これはそう考えてしまう人が悪いのではなくて、評価のシステムのほうが悪い。
もちろん、何事もないのをもってよしとする「無事是名馬」の思想はわかる。トラブルを起こさないのはそれだけで一個の才能だ。毎日を健全に円滑に送れることはすばらしい。それはわかる。
でもこれは「質素な日常においても足るを知り、感謝して生きる」みたいな話だ。組織を前に進めるための思想じゃない。無事であることだけを「よし」とすると、無事でないすべてのことが「悪」になり、したがってなかったことにしようと圧が働く。
本当に「よい」のは、対処方法を見つけて着地できることだったり、起きたことを隠さず議論できることだったりする。起きたものは仕方ないから、そこから前に進む道を探す。評価されるべきはこっち。
本当の意味で「何事もない」なんてことはまずなくて、人と人が暮らしていれば、どこかしら改善の余地のあることが起こる。
「ここの職場に問題はない」と思っていても、それは特定の人が激務を背負うことで成り立っていたり。「どこも悪い点は見つからないのに、入ってきた人がすぐ辞めてしまう」コミュニティは、そもそも新参者に優しくなかったり。
そういうのは「激務の人が背負っている些細な仕事から、周りの人が肩代わりしていく」ことで、ちょっとはよくなるかもしれない。たとえば事務仕事はすべて人に任せて、マネジメントに集中してもらうとか。
コミュニティに新しく来た人には、とにかく丁寧にルールを教えるとか。新しい場所っていうのはいつでも慣れないもので、そこが自分にわからない暗黙の規律で動いていたら、居心地が悪くていたたまれない。
なんていうか「問題」っていう捉え方は悪いのかもしれない。この言葉の響きはどこか「ヤバいもの、ダメなもの、重苦しい」雰囲気がある。「改善点」って言えばもうすこし聞こえがよくなる。よくなるし、このほうが実態に近い。改善点。
日々の暮らしを、できることから少しずつよくしていく。「問題」と大上段に構えるんじゃなくて「ちょっとでもよくなっていったらいいよね、そのためにできることはやろう」の雰囲気が共有できたらいい。
こういう教育を小学校で受けられたらよかったけど、もう大人になってしまったから仕方ない。試しに職場(建築現場)で「新しく現場入りした人に、すべきことを丁寧に説明する資料をつくるの、どうですか。アウトラインをまとめてもらえれば資料に起こすのは私がやります」と言ってみよう。現場に出ない、事務方の人間ができるのはそれくらいだ。
いまいる現場、妙に辞めていく人が多いんだよな。たぶん「なにをしていいのかわからない中でわからないのに指示を出される」のが辛いんだと思う。もちろんこれは仮定に過ぎないので、やってみないと結果はわからない。わかった頃には現場が終わってる可能性もあるけど、やるだけタダなのでやってみる。
問題がないのがいいわけじゃない、そりゃあ無用なトラブルが回避できるに越したことないけど、「何事もなくすべてが健全の順風満帆」なんてこと、まずない。だから目の前の小さなひっかかりとか、問題未満のなにかを、いまよりマシなところに着地させていく。そういう教育を受けたかったよな、なんて思う金曜。
本を買ったり、勉強したりするのに使っています。最近、買ったのはフーコー『言葉と物』(仏語版)。
